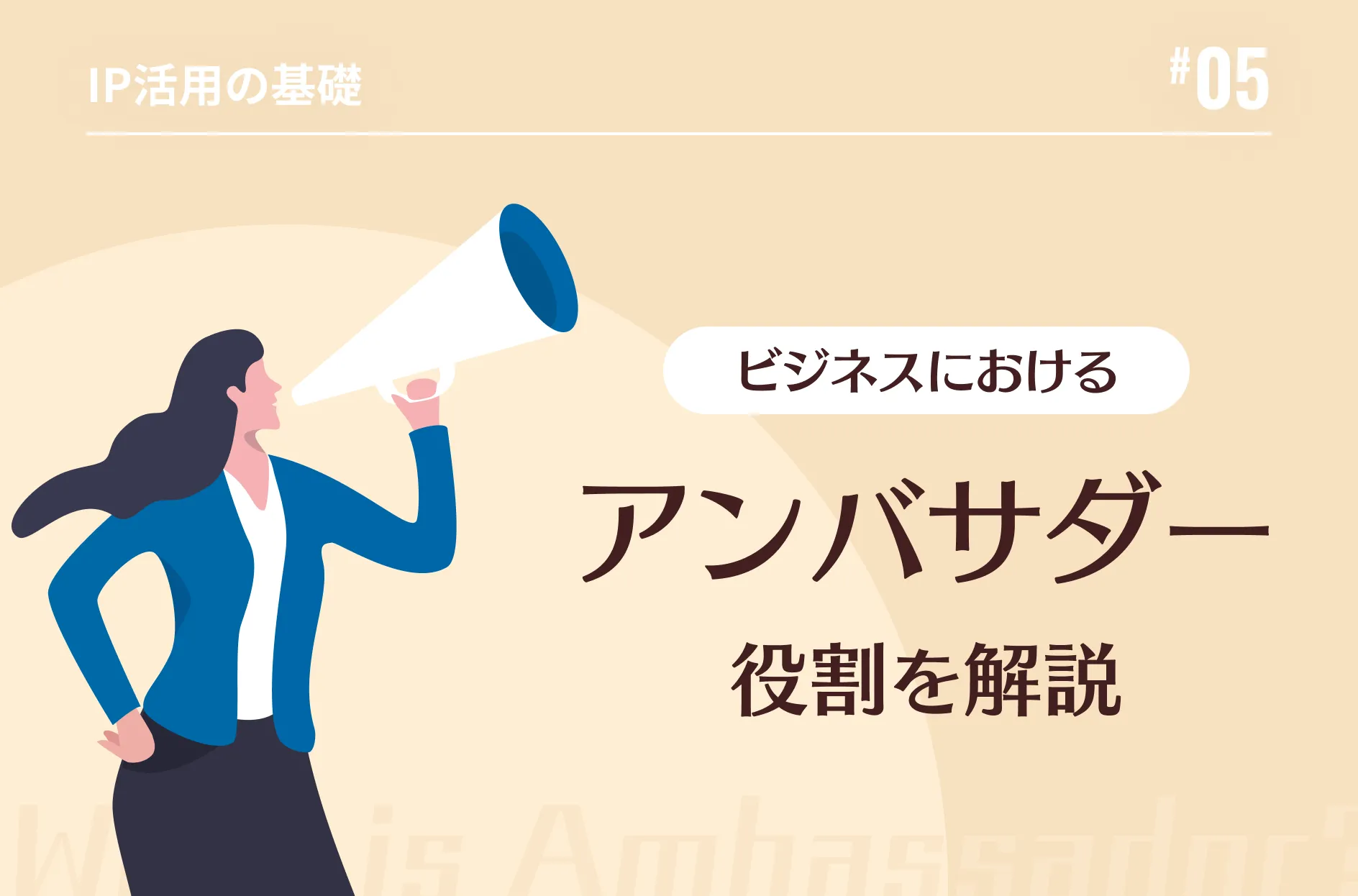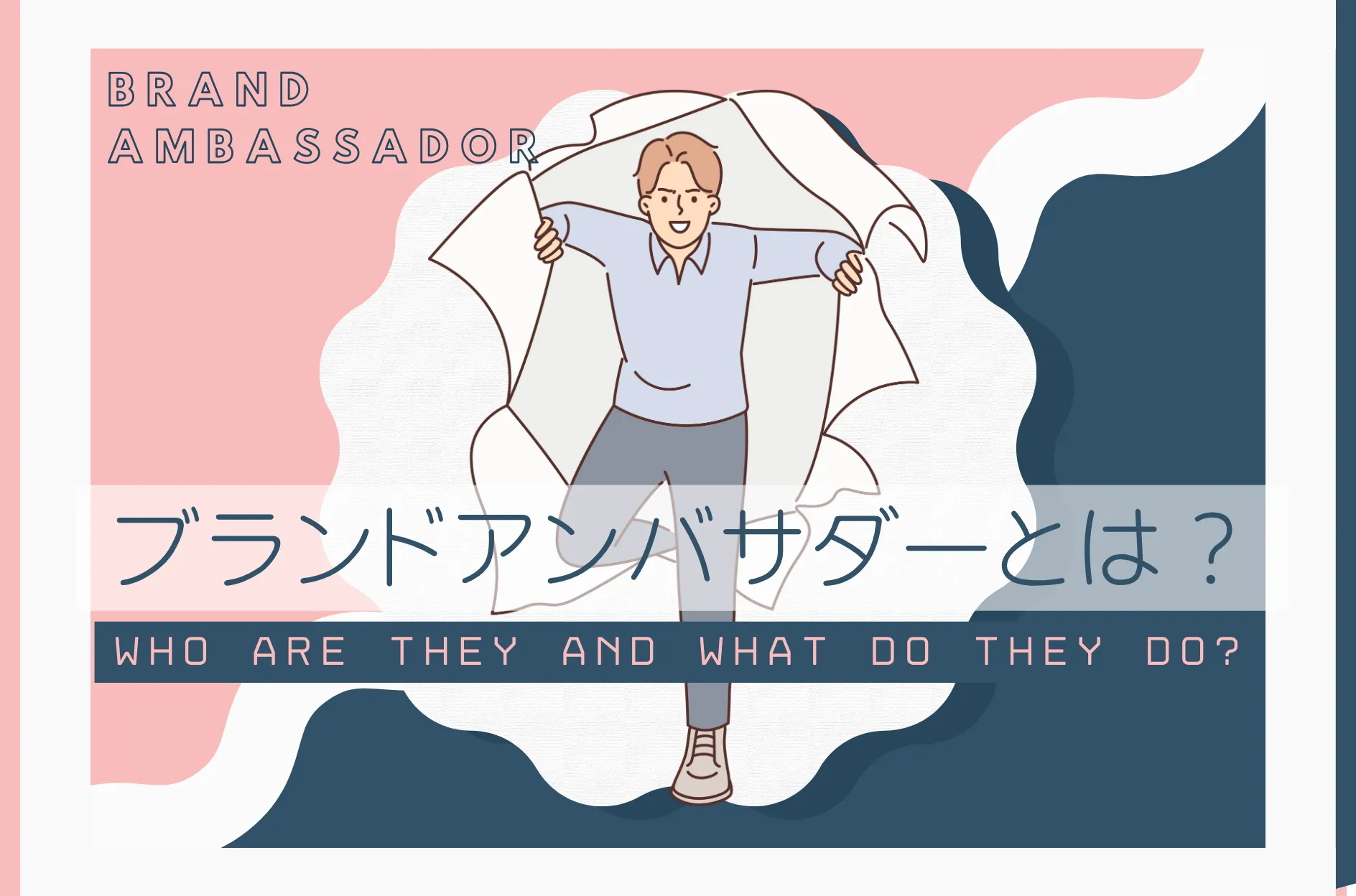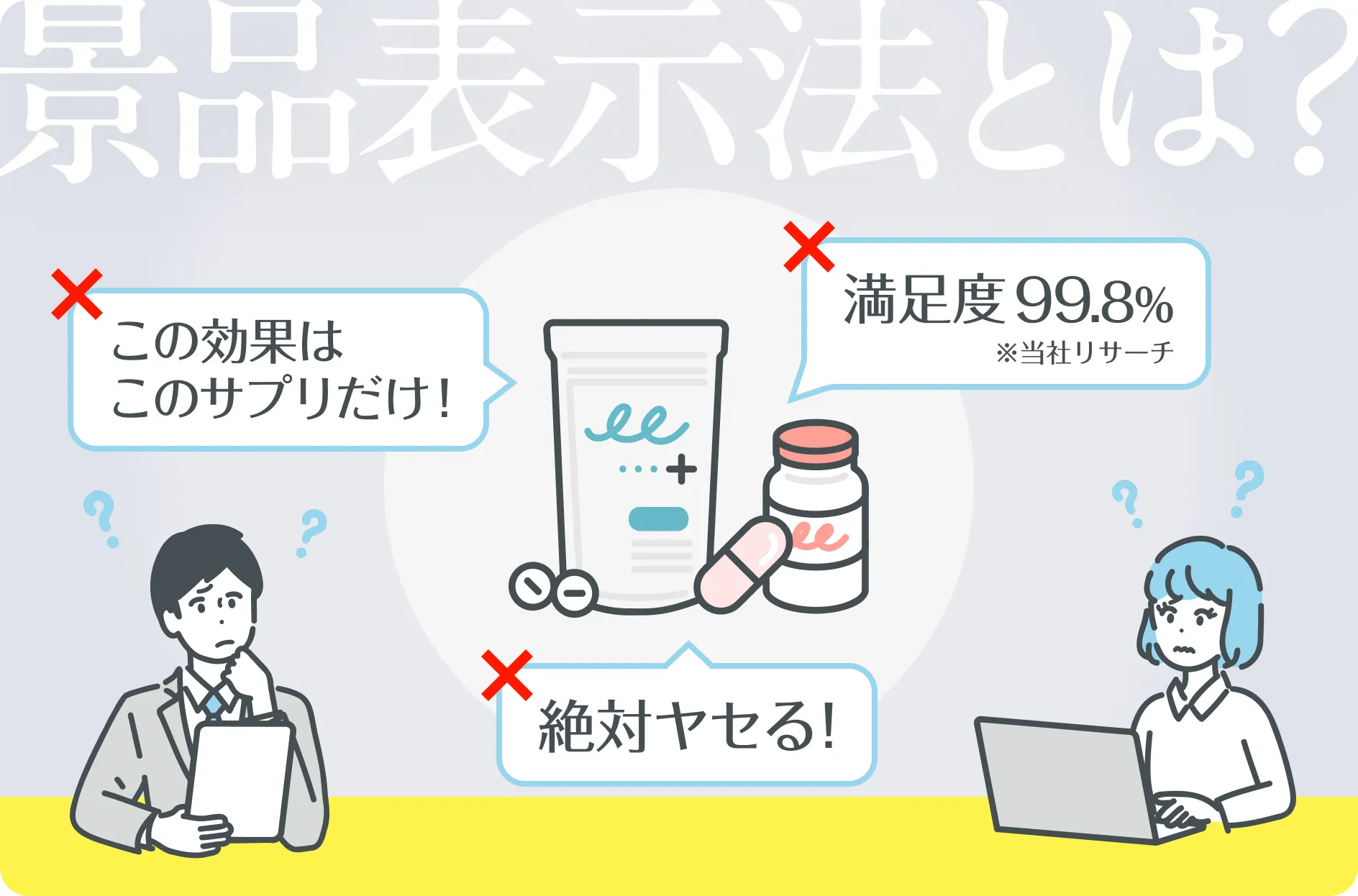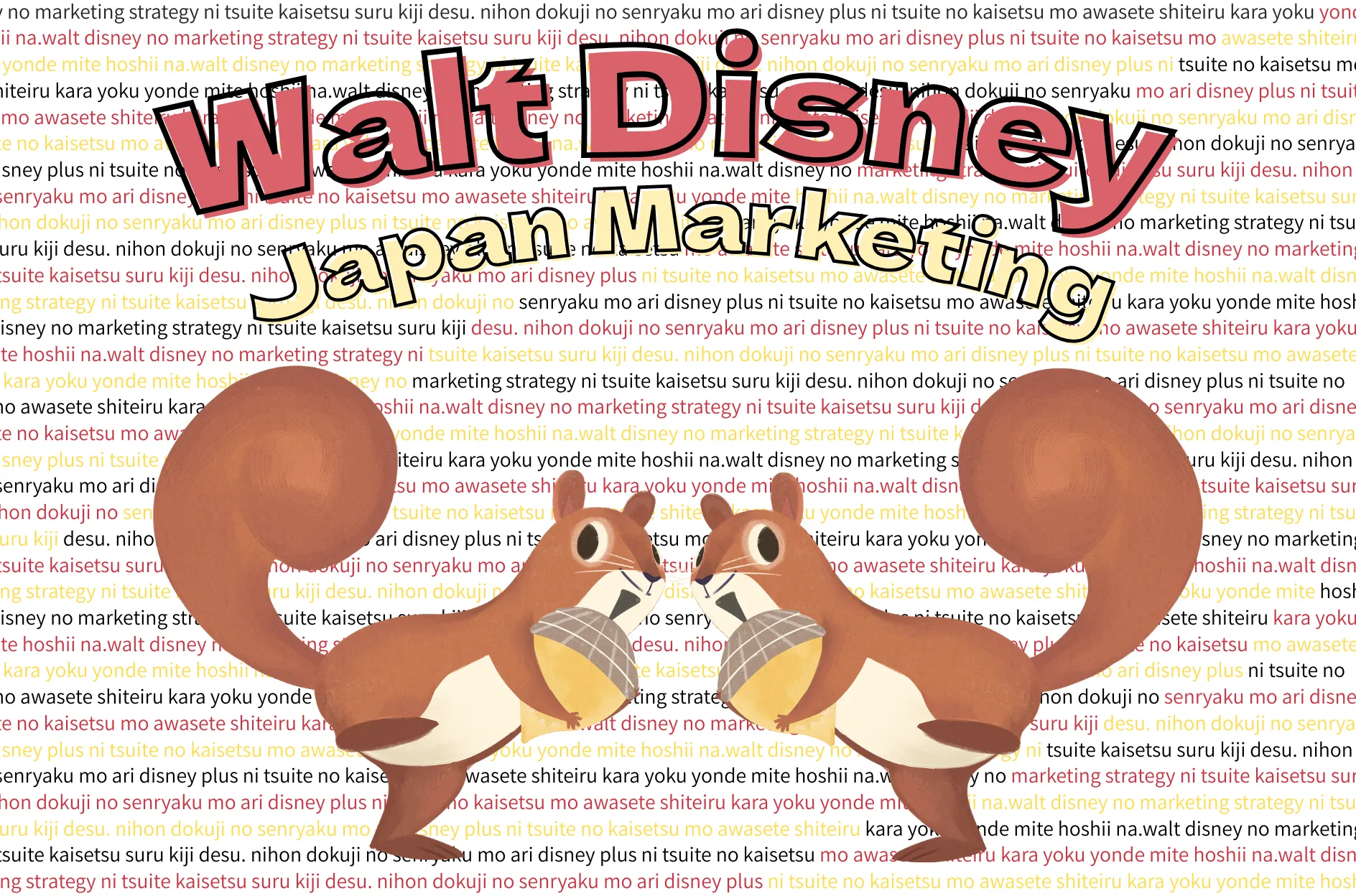IP活用
- ブランディング
アンバサダーマーケティングとは?ワークマンやネスカフェの成功事例・メリット・デメリット
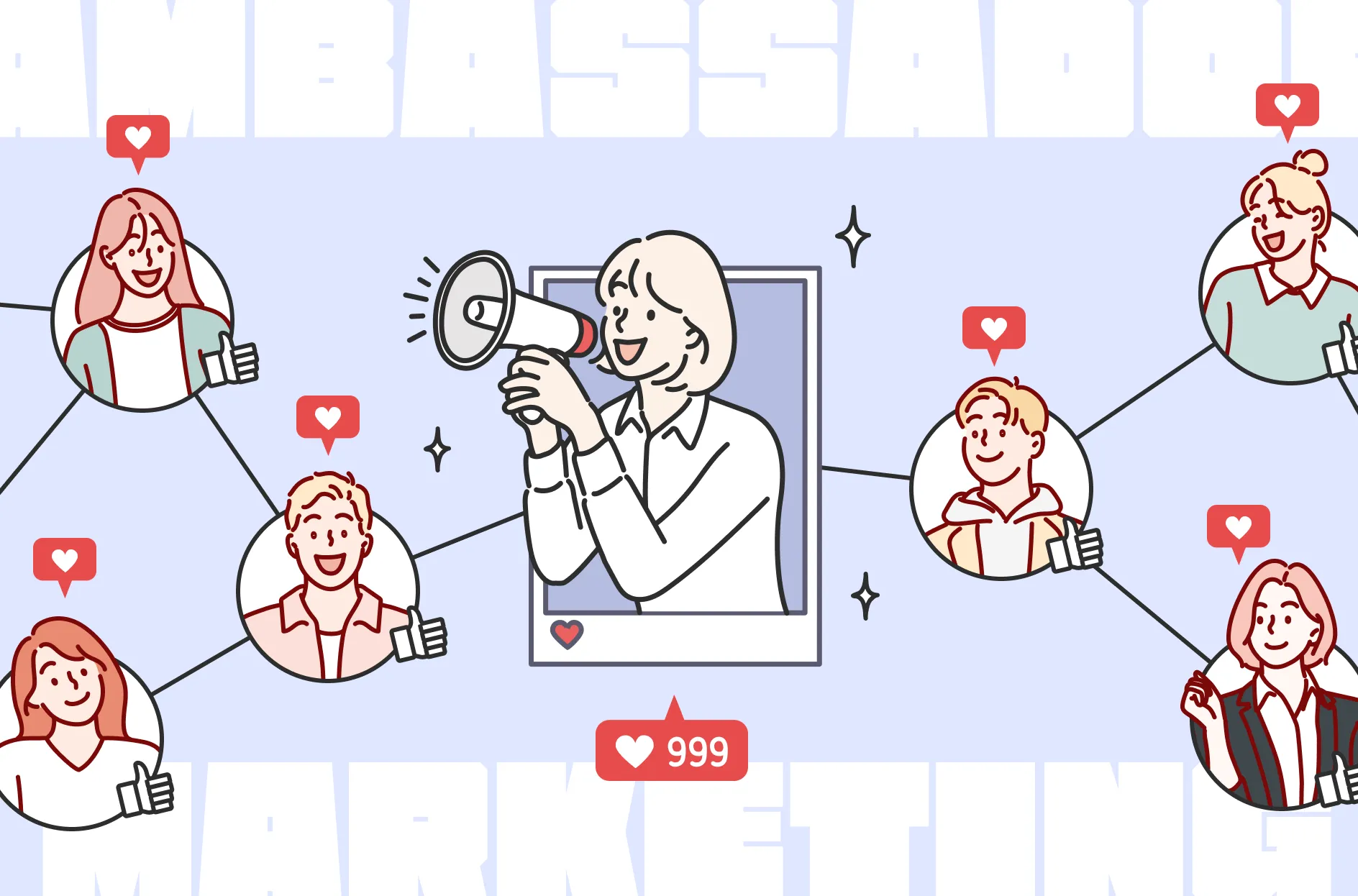
「アンバサダー」と聞くと、著名人がハイブランドの“顔”として情報を発信している姿を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、一般的に自社の商品やサービスを愛用しているユーザーなどをアンバサダーとして起用し、SNSなどを通じて魅力を発信してもらう手法を「アンバサダーマーケティング」といいます。
広告色の強いプロモーションに抵抗を抱くユーザーが増えている今、リアルな体験や共感を軸とした情報発信の価値が見直されています。
本記事では、ワークマンやネスカフェなどの成功事例を交えながら、アンバサダーマーケティングの基本的な考え方や注目されている背景、メリット・デメリット、実施するにあたっての注意点(ステマと誤認されないかなど)について解説します。
- アンバサダーマーケティングとは?
- アンバサダーマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違い
- アンバサダーマーケティングが注目される理由
- アンバサダーマーケティング導入のメリットとデメリット
- アンバサダーマーケティングの成功事例
- アンバサダー起用時のポイントと注意点
- アンバサダーマーケティングの今後の展望
- 宣伝しない“宣伝”が、ブランドを強くする

タレント×マーケティングで
成果を最大化
アンバサダーマーケティングとは?

アンバサダーマーケティングとは、自社の商品やサービスに共感し、実際に利用しているユーザーなどを「アンバサダー」として起用し、SNS上などにその体験や感想を発信してもらうことで認知拡大やファン獲得につなげるマーケティング手法のこと。
いわゆる「広告塔」として契約するのではなく、もともとブランドに愛着のある人たちによって自然発生的に生じた声を活用するため、広告疲れが広がる現代人にも受け入れられやすいのが特長です。
アンバサダーは愛用者に限らず、従業員や取引先、関係の深いコミュニティなどから選ばれることもありますが、いずれにせよ「等身大の存在」であることで、発信に対する信頼性や共感が高まりやすいといえます。
なお、アンバサダーの意味については、以下の記事でくわしく解説しています。
アンバサダーマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違い

アンバサダーマーケティングとよく混同されがちなのが、インフルエンサーマーケティングです。インフルエンサーマーケティングは、主にフォロワー数や拡散力など「影響力」に基づいて起用したインフルエンサーに情報を広めてもらう施策。
一方でアンバサダーマーケティングは「共感性」や「愛着」に重きを置き、拡散力も求められるものの、それ以上に“どれだけブランドを好きか”、“体験者として信頼できるか”が重要視されます。
そのため、アンバサダーマーケティングが戦略として向いているのは以下を検討中の場合でしょう。
- ブランディング
- 顧客のファン化
- ナーチャリング(顧客育成)
アンバサダーは以前よりブランドのファンであった方が任命されることが多いため、ブランドへの想いが強く、知識も豊富です。また、生活者視点でリアルな使用感を伝えられます。
もちろん冒頭で示したとおり、認知度や拡散力を重視して著名人をアンバサダーに任命するケースも少なくありません。
その場合は、もともとブランドのファンであったかは加味していないこともありますが、それでも昨今は、かねてよりブランドのファンであると公言していたり、実際に愛用していたりする方が選ばれる傾向にあります。
なお、著名人が企業やブランドのアンバサダーを務める事例については、以下の記事をご参照ください。
表にまとめると、アンバサダーマーケティングとインフルエンサーマーケティングの違いは以下のとおりです。
マーケティング | 求められるもの | 期待できる効果 |
|---|---|---|
アンバサダー | 共感、愛着 | ・ブランディング |
インフルエンサー | 影響力 | ・認知度向上 |
なおインフルエンサーマーケティングについては、以下の記事でくわしく解説しています。
ステルスマーケティングとの違い・注意点
アンバサダーやインフルエンサーによる情報発信において、とくに注意したいのが「ステルスマーケティング(ステマ)」と見なされないことです。
企業と契約しているにもかかわらず、あたかもアンバサダー個人による自発的な意見であるかのように見せて購買意欲をかきたてるような発言をした場合、消費者を誤認させてしまう恐れがあります。
そのため、アンバサダーマーケティングを行う際は、「PR」表記の徹底や契約の透明性を保つことが不可欠です。信頼性や共感を損なわないためにも、消費者に対して正直で誠実な情報提供を意識する必要があります。
なお、ステマの定義や最新のガイドラインに関しては、こちらの景品表示法に関する記事をご確認ください。
アンバサダーマーケティングが注目される理由
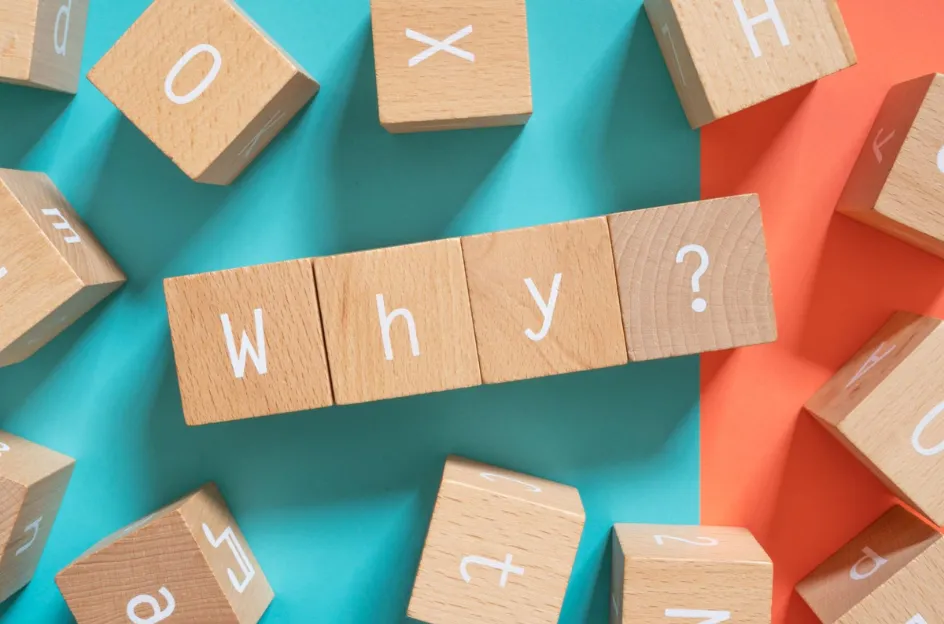
ここ数年、企業が積極的にアンバサダーマーケティングに取り組むようになった背景には、消費者の購買行動やSNSの使用方法が大きく変化してきたことが挙げられます。
単なる“広告”では人の心を動かすのが難しい今、リアルな声や体験談に基づく「共感」と「信頼」が、新しいマーケティングの軸として浮上しているのです。
SNS上の「共感」や「信頼」を軸にした購買行動が主流に
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSにおいて、フォロワーとの関係性が深い人の発信のほうが説得力を持つ傾向があります。これはフォロワー数が多いことよりも、「誰がどんな思いで使っているか」「どんな言葉で伝えているか」といった文脈が重視されているからです。
特にZ世代やミレニアル世代は、企業の打ち出す広告よりも“使用者によるリアルな口コミ”を参考にする人が多く、共感できる人物が紹介している商品に自然と興味を持つ傾向にあります。
アンバサダーによる等身大の発信は、こうした世代の消費者にとって“信頼できる情報源”として機能しやすいのです。
発信に広告感が薄く、受け入れられやすい
広告色が強い投稿は「押し売りされている」と感じられ、敬遠されがちです。実際、広告(テレビCM、インターネット広告、タクシーCMのいずれか)に対して「鬱陶しい、邪魔、目障り」というイメージを抱いている人は75.5%にも及ぶというデータもあります。
参照:株式会社リチカ(PR TIMES)「【広告・CM意識調査】を実施「広告を見たい」はわずか13%、一方「興味関心にあったクリエイティブなら必要」は39.4%」
その一方で、アンバサダーによる発信は、もとよりその商品やブランドを好きだった、一ユーザーによる正直な紹介のため、押し売り感が少なく、読み手にも受け入れられやすいでしょう。
企業が無理にメッセージを押しつけるのではなく、ファンの声を媒介にして価値を届けられることこそがアンバサダーマーケティングの強みであり、SNS時代にマッチしているポイントといえるでしょう。
コミュニティ形成・ロイヤルユーザーとの関係構築にも有効
アンバサダーを中心に、ブランドに共感を寄せるファン同士がつながり、コミュニティが形成されることもあります。さらには単発のプロモーションではなく、継続的にブランドと関わってくれる“応援団”を育てていくことで、ロイヤルユーザーの獲得にもつながるでしょう。
アンバサダーとの関係を大切にすることで、商品開発や改善へのフィードバックがもらえたり、新たな企画への参加を促せたりと、企業とユーザーの距離が縮まりやすくなるのも大きな利点です。
企業とファンの関係を強めることで、自社が直接リーチできない層へのアプローチが可能になるだけでなく、リピーター増加にもつながるため、中長期的に事業の継続をもたらす施策になりえます。
インフルエンサー起用の高騰・炎上リスク回避策にもなる
いまや著名人へのアンバサダー依頼だけでなくインフルエンサーを起用したプロモーションも高額になることが多く、企業によっては継続的に行うのが難しくなってきました。さらに、過去の言動や思想などに注目が集まり、起用後に炎上するケースも少なくありません。
一方ユーザーをアンバサダーに任命する場合は、そもそもブランドへの理解や愛着が強く、信頼できる人選がしやすいのが特徴です。比較的コストを抑えつつ、長期的な関係性を築ける点にも、企業からの注目が集まっています。
アンバサダーマーケティング導入のメリットとデメリット
アンバサダーマーケティングは、企業のファンや愛用者といったユーザーを巻き込んで実施するマーケティング施策です。多くの利点がある一方で、導入や運用における注意点も存在します。ここでは、その具体的なメリットとデメリットを整理します。
アンバサダーマーケティングのメリット

1. コスパのよい発信力を確保できる
従来の広告出稿費や著名インフルエンサーへの高額な報酬を考えると、ユーザーをアンバサダーに起用することは、コストパフォーマンスに優れています。
活動に際しても報酬というかたちではなく、商品提供や限定イベントへの招待といったインセンティブで支援するケースも多く、費用対効果が高い施策といえるでしょう。
2. 生活者目線のリアルな意見が受け入れられやすい
アンバサダーは実際の利用者であることが多いため、商品の使用感や効果などを生活者目線で言葉にして伝えてくれます。広告要素が少ない分、ユーザーにとっても“自分ごと化”しやすく、口コミとして信頼を得やすいのが特徴です。
3. 商品開発・改善にフィードバックが活かせる
アンバサダーとの交流を通じて、ユーザーだけでなく企業も生活者視点の貴重な意見を得ることができます。そのまま新商品の開発や既存商品のブラッシュアップにつなげられるケースもあり、マーケティングと商品開発が連動しやすい点も魅力です。
4. 長期的なファンコミュニティづくりにつながる
一度きりの単発プロモーションにとどまらず、アンバサダーとの継続的な関係性構築を行うことで、企業やブランドの熱量あるファンコミュニティが形成されます。結果としてロイヤルカスタマーの醸成やLTV(顧客生涯価値)の向上も期待できるでしょう。
アンバサダーマーケティングのデメリット
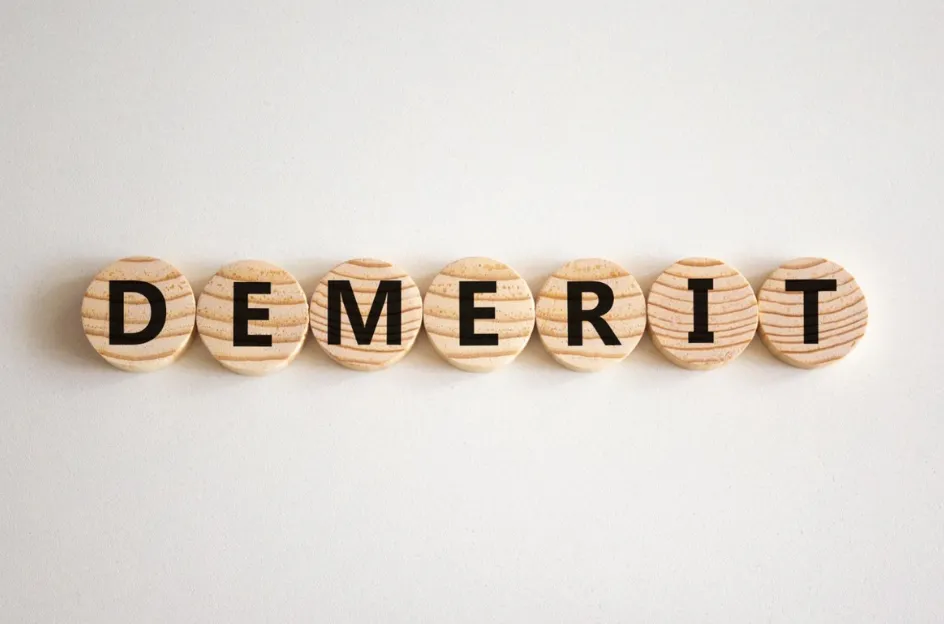
1. 人選や育成、関係性構築に時間がかかる
アンバサダーは単なる「発信者」ではなく、企業と価値観を共有する「仲間」ともいえる存在です。そのため適切な人材の選定や育成、信頼関係の構築には時間も工数もかかります。
2. 発言内容をコントロールできない
あくまで“個人の発信”であるため、意図せずアンバサダーが自社ブランドイメージと合わない発言、行動を行うリスクも存在します。契約時にはガイドラインの整備や対応フローの準備が欠かせません。
3. 発信力にばらつきがある
一定の反応が予測できるインフルエンサーと異なり、一般ユーザーをアンバサダーに選んだ場合は、SNS投稿の拡散力・影響力にばらつきがあります。期待したほどリーチが伸びないケースもあるため、複数人を起用する、複合的なKPIを設定するなどの工夫が必要です。
4. 継続的な運用体制が必要
ただ一度アンバサダーを起用しただけでは成果は見込めません。定期的なコミュニケーション設計や活動の可視化、インセンティブの見直しなど、長期的な視点を持って運用体制を整えることが求められます。
なお、著名人をアンバサダーに起用した場合の報酬については、以下の記事を参考にしてみてください。
アンバサダーマーケティングの成功事例

アンバサダーマーケティングの成功例の代表としてよく知られているのが、ワークマンとネスカフェの取り組みです。どちらも“自社のファン”をアンバサダーに起用することで、自然なかたちで認知と購入の導線を構築し、新たな市場を切り拓きました。
ワークマン:実用性×共感性で“ワークマン女子”の開拓に成功
ワークマンはいわずと知れた、作業用品を中心とした小売店を全国に展開する企業ですが、特筆すべきポイントはその柔軟性。
まず、自社製品である作業用レインコートに関するブロガーやYouTuberの意見をキャッチアップし、商品開発に生かした結果、今や人気ブランドとなった「AEGIS(イージス)」を誕生させました。
そして同じく自社製品である溶接工用の「綿かぶりヤッケ」は、キャンパーでもあるブロガーの「サリーさん」の助言をもとに、バーベキュー時の火花に強い「フルジップコットン・パーカー」に生まれ変わって大ヒット。
そういった経緯をふまえ、2019年10月にはアンバサダーマーケティングに注力していく意思を表明します。当時、自発的にワークマンの商品を愛用して情報発信していた20名のユーザーをアンバサダーとして起用し、2020年にその方々とコラボした製品のみで行うファッションショーを企画。
さらに同年末にはアンバサダーをさらに増やし、ほかの販促施策に頼らずアンバサダーマーケティングのみで商品を売り抜く体制づくりを行うことを宣言しました。
参照:ワークマン「ワークマンは「アンバサダー・マーケティング」を本格化します」
その後、宣言どおりアンバサダーの意見を参考に、女性をメインターゲットにした新業態店舗「#ワークマン女子」の出店を果たし、大躍進を遂げます。
しかもその立役者となった前述のサリーさんは、以降もヒット商品を連発し、2023年5月にはワークマンの社外取締役に就任。これは上場企業としては初めての取り組みとなりました。
参照:ワークマン「【上場企業初!!】 カリスマインフルエンサーがワークマンの社外取締役に就任 YouTuber/ブロガー「サリーさん」は当社初のアンバサダーで#ワークマン女子店の生みの親」
もとより作業用品を開発していたことから優れた機能面は保持していたものの、そこにユーザーの声をうまく掛け合わせたことで、ファッション性やサイズ展開といった部分にも武器を増やすことに成功し、売り上げ増加と新規顧客獲得につなげることができました。
参照:HERSTORY「女性視点プラスで売上増大 #ワークマン女子。新規顧客開拓のカギは「異常値」「声」「女性社員」」
ワークマンがアンバサダーマーケティングを成功させたポイントは、やはりユーザーの声を真摯に受け止め、実際に商品開発や新店舗開拓に挑んだ柔軟性でしょう。
ネスカフェ(ネスレ日本):オフィス内の“共感体験”を活用した拡散モデル
そもそも日本国内で「アンバサダー」という言葉を広めるきっかけになったといわれるネスカフェ(ネスレ日本)。リズムにのって「ネスカフェ アンバサダー」と宣伝する広告をご覧になったことのある方も多いのではないでしょうか?
ネスレ日本がネスカフェ アンバサダーを始動させたのは2012年秋のこと。発端となったのは2009年、コーヒーマシン「ネスカフェ バリスタ」の発売です。この個人向けのマシンは当初から売り上げ面で好成績をおさめていたのですが、目標としていた「全家庭への普及」には時間を要すと判断しました。
そこでアンバサダーになれば、職場で従業員同士、コーヒーの実費(1杯20円)以外は無料でマシンを利用できるという施策を始めたのです。
ネスカフェ アンバサダーの条件は以下の5つ。
- ネスレの会員登録をしている
- ネスレ日本から届くメールを受信できる
- 定期便を利用し、マシンに利用する商品を購入する
- 1回のお届けに際し、1本以上のつめかえパックを購入する
- 1回のお届けにつき4,000円以上(税込/送料除く)購入する
参照:ネスレ日本「ネスカフェ アンバサダーお申し込みページ」
結果、募集してからわずか2年強で16万人ものアンバサダーを集めることに成功し、2020年には45万人以上の応募を獲得し、現在も拡大をつづけています。
参照:リクルートワークス研究所「ネスカフェ アンバサダー 45万人はいかに生まれたのか?」
しかも、アンバサダーのいる職場では自宅用にマシンを購入するユーザーも増えているそうで、アンバサダー施策によって、商品を実際に自身が取り入れた際のシミュレーションができ、そのうえで魅力を感じられているということがわかります。
参照:日本マーケティングリサーチ協会「自発的なファン活動を生むアンバサダーというしくみ」(pdf資料)
ネスカフェ アンバサダーの場合、その対象となる製品=マシンの認知度を広める相手は職場の方々なのでクローズドにも感じられますが、かねてより「コーヒーブレイク」という言葉が存在するとおり、1日1杯のコーヒーがリフレッシュする機会をもたらしたり、チームメンバーとのコミュニケーションのきっかけになったり、アンバサダーになることで“体験”を増やすことで、売り上げ貢献だけでなく大きな効果を生み出しているでしょう。
アンバサダー起用時のポイントと注意点

アンバサダーマーケティングを成功させるためには、単に「フォロワーが多い人をアンバサダーに選べばよい」というものではありません。
なぜ自社がその人をアンバサダーに任命したのか、きちんと脈絡があり信頼できるものとして受け入れられる必要があります。そのためには起用前から運用まで綿密な設計が重要です。
ここでは、アンバサダー施策において押さえておきたいポイントと注意点を解説します。
起用する目的を明確にする
まず大切なのは、「なぜアンバサダーを起用するのか」という目的の整理です。たとえば、認知拡大やSNSでの拡散が主な目的であれば、発信力の高いユーザーを候補に挙げるべきでしょう。また、この場合はアンバサダーマーケティングではなく、インフルエンサーマーケティングを検討してもよいかもしれません。
一方で、共感やロイヤリティを重視したい場合は、既存顧客の中からとくに愛用歴が長い、あるいは友だち紹介などをしてくれているファンを選ぶことが有効でしょう。
近年では、ユーザー投稿(UGC)の創出を狙ったアンバサダー起用も増えています。目的によって起用する人材の属性や運用方法が大きく異なるため、最初の設計段階でしっかりと意図を固めて社内で共有しておくことが必要です。
フォロワー数より“親和性”を重視する
アンバサダー選定時には、SNSのフォロワー数や影響力だけで判断してしまう企業も少なくないですが、より重要なのは「ブランドとの親和性」です。
繰り返しになりますが、普段からそのブランドや商品を愛用している方、あるいは企業の世界観や価値観に共感している方を起用することで、情報発信の内容にリアリティと説得力が生まれ、結果、潜在・顕在顧客の信頼を得やすくなり、商品購入やサービス利用への自然な導線が築けます。
情報発信の際のルール・ガイドラインを整備する
リアルな声を求めるのであれば、アンバサダーには自由に発信してもらいたい一方で、企業として守るべきルールも存在します。とくに、広告表記に関するガイドラインの遵守は重要です。
「ステルスマーケティング(ステマ)」と誤解されないよう、タイアップであることの明記や、表現上の誇張を避ける指示などをあらかじめ伝えておきましょう。アンバサダー起用時にきちんと契約書に明記したり、マニュアルを用意したりすることも有効です。
継続的なコミュニケーションと感謝の姿勢を忘れない
アンバサダーはあくまで企業の“味方”であり、大切な共創パートナーです。起用後も、定期的に交流できる場を設け、情報共有やフィードバックを丁寧に行いましょう。
また、発信内容など普段のアンバサダー活動に対するお礼など、感謝の姿勢を持ち続けることも信頼関係の維持には欠かせません。イベントへの招待や限定ノベルティの贈呈など、目に見える“ご褒美設計”もおすすめです。
アンバサダー自身が楽しめる施策にする
施策の成功には、アンバサダー自身が心から楽しめるかどうかも大きく影響します。企業の期待を一方的に押しつけたり活動をコントロールしたりするのではなく、「自分らしい言葉で発信できる」「リアルな体験ができる」といった、“楽しくて継続したくなる”仕組みをつくる工夫が必要です。
たとえば、商品を使ったチャレンジ企画やオフ会形式のイベントなど、アンバサダーが「やってみたい」と思えるコンテンツを用意することも成功のカギとなるでしょう。
アンバサダーマーケティングの今後の展望
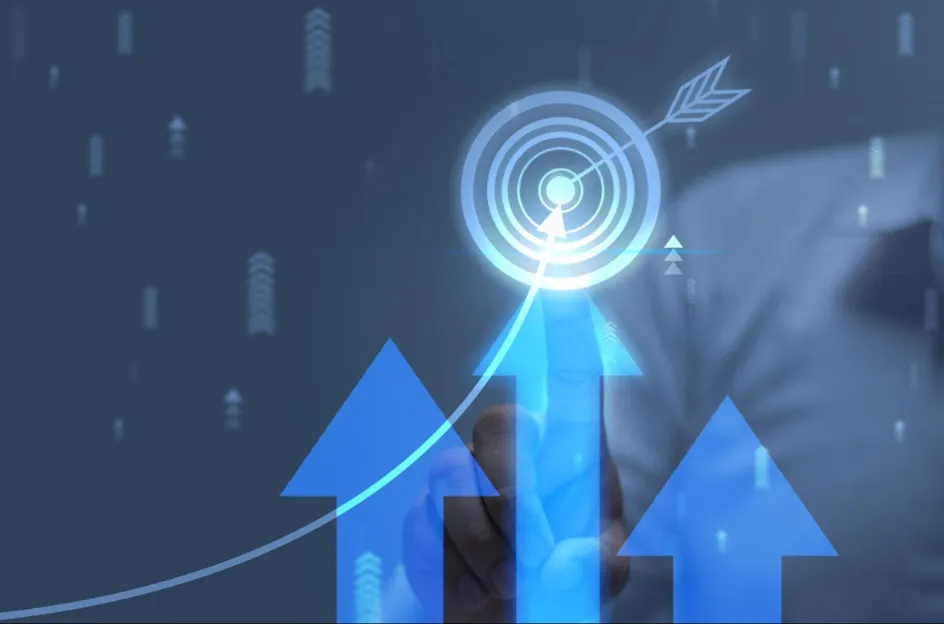
アンバサダーマーケティングは、一時的なトレンドではなく、今後さらに多様化・深化していくマーケティング施策として注目を集めています。ここでは、これからの主な展望を4つの軸で整理してご紹介します。
インフルエンサーマーケティングとの併用が主流に
かつては「インフルエンサー施策」か「アンバサダー施策」かという二択で考えられることもありましたが、近年では両者を組み合わせて活用するケースが主流となりつつあります。
たとえば短期的な話題化はインフルエンサーマーケティングで叶え、継続的なファンづくりはアンバサダーマーケティングで行う、といった棲み分けが進んでいます。ターゲット層や商材によって、発信者の“熱量”と“拡散力”を使い分ける柔軟な設計が重要です。
顧客参加型のコミュニティマーケティングにも発展
アンバサダー施策は「一部の選ばれた人による情報発信」だけでなく、ブランドの“共創”に参加する動きへと発展しています。
たとえば新商品のネーミングをファンと一緒に決める、限定イベントへの招待を通じて深い関係性を築くといった体験型のコミュニティマーケティングの一部として、アンバサダー施策が実施されているのです。
これは社会への貢献意欲が高いといわれているZ世代にもフィットしやすく、積極的に参加して“ともにつくっている”という感覚を生み出すことで、双方向性のあるブランド体験を生み出します。
BtoB分野での社内アンバサダー施策も拡大中
BtoCにとどまらず、BtoB企業においてもアンバサダー活用の動きが加速しています。なかでも注目されているのが「社員アンバサダー」です。
たとえば自社製品や働き方に誇りを持って発信する社員のSNS投稿を通じて、自社製品やサービスの契約につなげたり、採用ブランディングや営業活動の補完に成功する企業も増えています。
たとえば「アンバサダーマーケティング」の発祥といわれているAdobeでは、従業員をブランドアンバサダーとして育成し、SNSで積極的に情報発信をするように促しています。その結果、Adobe Creative Cloudの申込数が20%も増加したそうです。
参照:イマジナ「imajina news vol.11- 社員アンバサダー・・・って?」
リアルな声で企業の“信頼感”を高める手法として、アンバサダーマーケティングはBtoB領域においても今後さらに広がっていくでしょう。
デジタルツールの導入で運用効率化
アンバサダーの選定・契約・投稿管理・レポーティングまでを一括で管理できる専用のプラットフォームやSaaSの導入も進んでいます。
これにより従来属人的だった運用業務が効率化され、少人数のチームでも複数のアンバサダーを一元的にマネジメントできるようになりました。また、発信の成果をデータで可視化することで、施策の改善や説得力ある社内報告にもつなげやすくなります。
宣伝しない“宣伝”が、ブランドを強くする

アンバサダーマーケティングは、単なる一時的な話題づくりではなく、「共感」「信頼」「継続性」を軸に、ブランドとファンとの長期的な関係を築く施策です。広告色の強いプロモーションが敬遠されるなか、ユーザーに自然に情報が届く手法として注目されています。
施策を成功させるには、アンバサダーの選定の戦略性、活動内容の設計と育成体制、そしてブランドとの信頼関係の構築が重要です。報酬やガイドラインの整備など、丁寧な設計によってこそ本来の効果が発揮されるでしょう。
また、アンバサダーは「広告塔」ではなく、ともにブランドをつくり、成長する“共創者”として捉えるべきです。一方的にお願いするのではなく、愛着や当事者意識を育てていくことで、より本質的なファンづくりと成果につながるでしょう。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
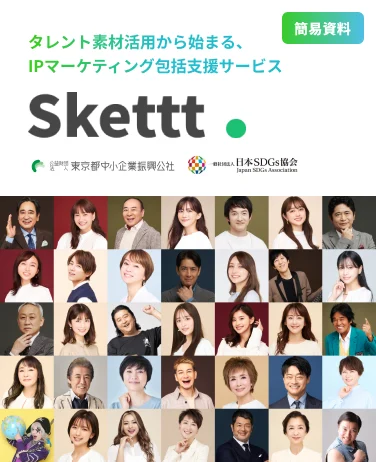
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
- ブランディング
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag