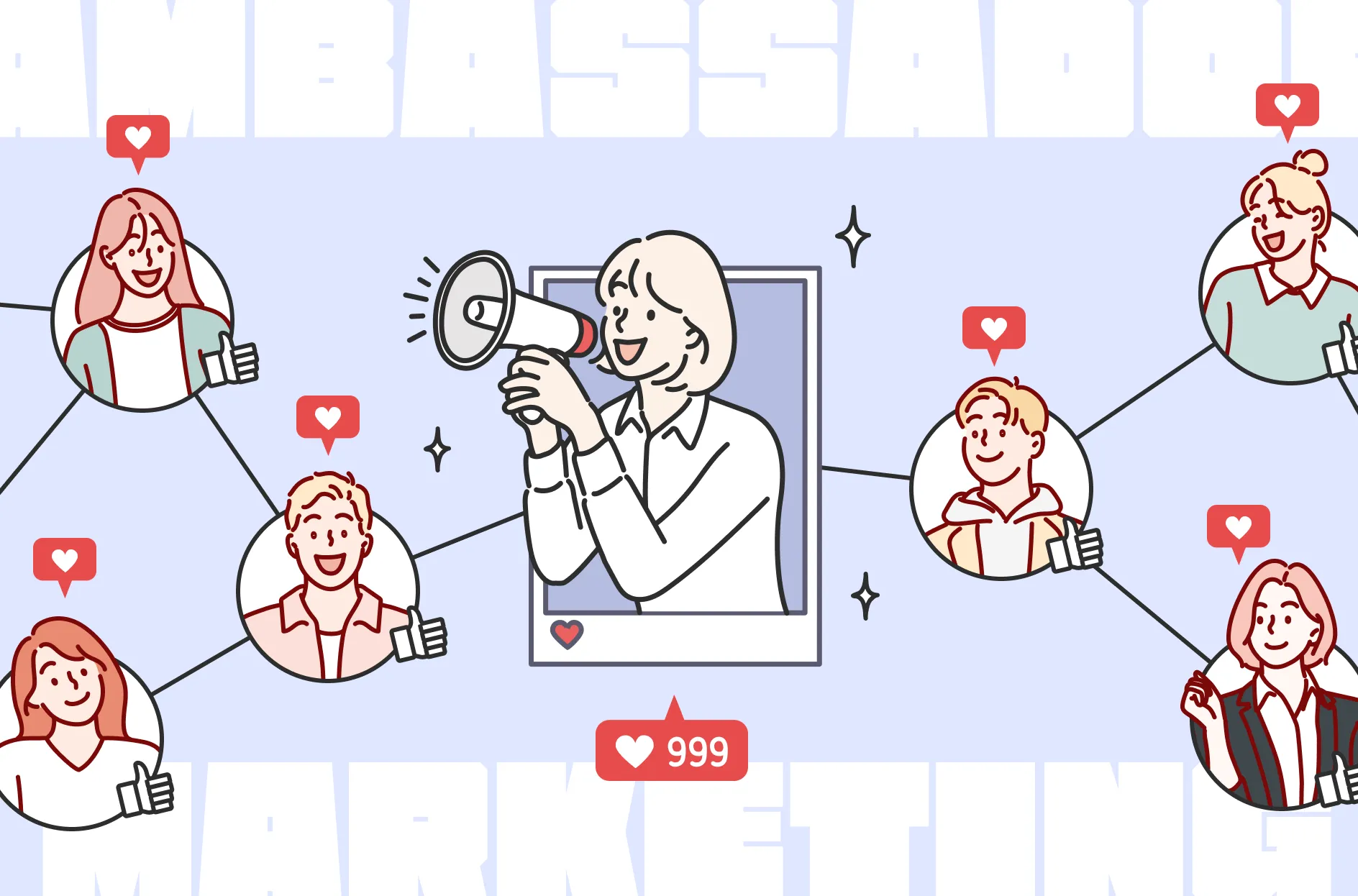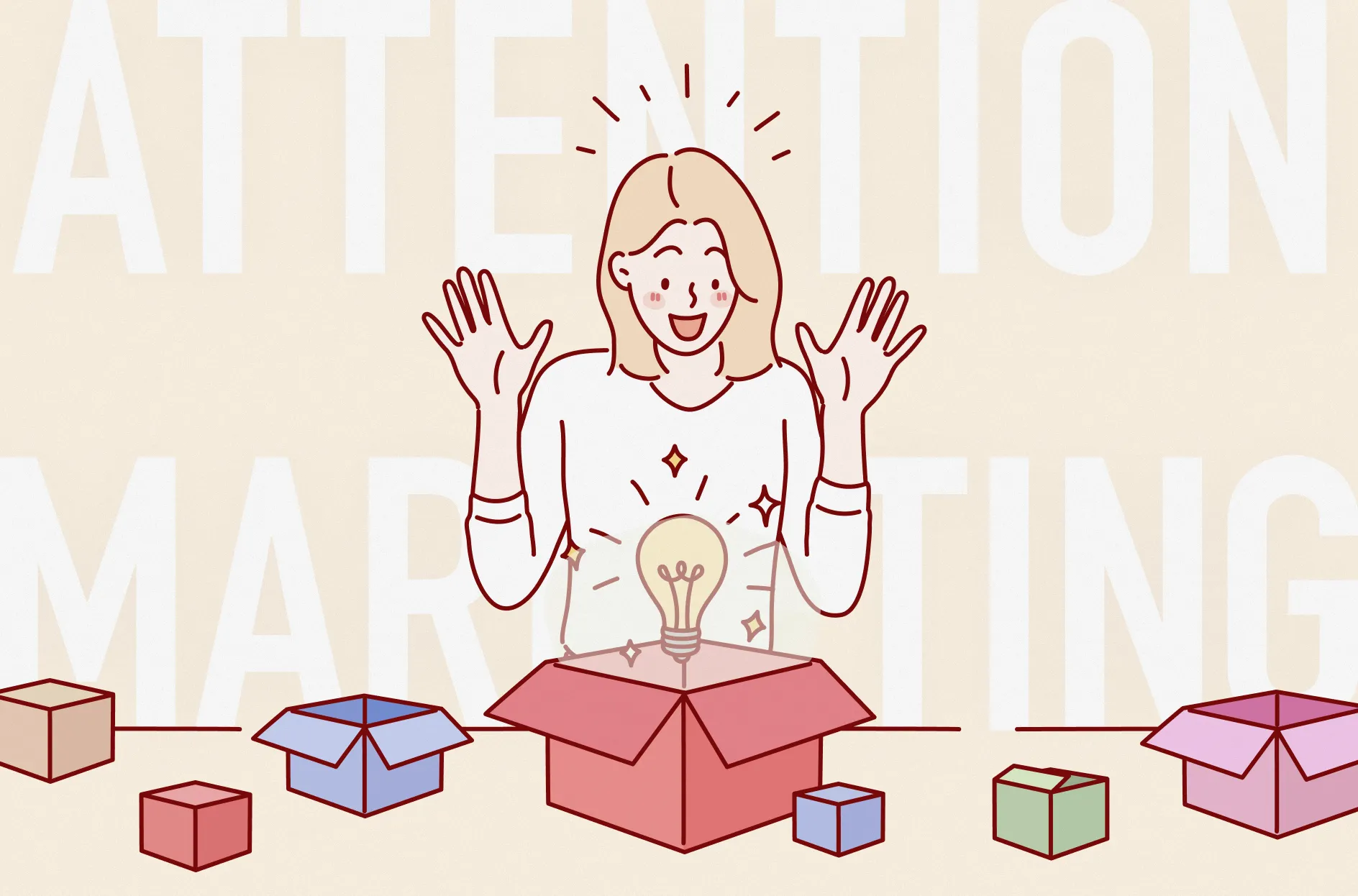マーケティング戦略
ファンマーケティングの事例紹介!成功・失敗を分ける飲食店やイベントの戦略術

近年は、企業が一方的に打った広告よりも、商品のファンによるSNS上のレビューや拡散が、消費者の購買行動を左右することも多くなりました。
そこで注目されているのが「ファンマーケティング」。自社や商品のファンと信頼関係を築き、中長期的なブランドの共創・売上の増加を図る戦略です。
この記事ではファンマーケティングの成功事例と、イベントの重要性、飲食店やローカル企業の具体的な手法、ファンマーケティングを成功させるための3原則などを解説します。実践する際の参考にしてください。
- 成功事例① ヤッホーブルーイング:「熱狂的なファンづくり」で競争を超える
- 成功事例② カゴメ:「応援される企業」だから社会貢献もできる
- 成功例から見える「イベント」の重要性:接点を“体験”で強化
- 飲食店・ローカル企業のファンマーケティング戦略
- 失敗“あるある”:ファン心理を誤解した施策はNG!
- 事例から見えてきた「ファンマーケティング成功の3原則」
- ファンマーケティングは“顧客との関係性構築”の再定義

タレント×マーケティングで
成果を最大化
成功事例① ヤッホーブルーイング:「熱狂的なファンづくり」で競争を超える

ここからはファンマーケティングの成功事例をご紹介していきますが、そもそもファンマーケティングについてくわしく知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。
「よなよなエール」が有名な株式会社ヤッホーブルーイングは、1997年の創業以来、クラフトビールを通してファンにささやかな幸せを提供し続けている企業です。
同社が製造しているさまざまなビール、そして、株式会社ワンダーテーブルと協業している公式ビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」の料理を味わえる、クラフトビール好きのための飲み会イベント「よなよなエールの宴」。
また、2010年の「宴」から始まった、スタッフとファンが一体化できる大規模野外イベント「よなよなエールの超宴」も、毎回好評を得ている企画です。よなよなエールの宴は1回につき2時間半程度ですが、「超宴」は前夜祭を含めて3日間(2025年)。ファンにとっては、非日常的で至福の時間になることでしょう。
参照:ヤッホーブルーイング「よなよなの里 | よなよなエール公式ウェブサイト「よなよなの里」」
他に、「大切な誰かと未来の約束をすること」で購入予約ができる、限定販売商品「約束のよなよなエール」も、実際の販売は2032年と2042年ですが、2025年7月の時点で既に予約受付が終了しているほどの人気企画です。
ヤッホーブルーイングは、趣向を凝らした数々の企画にファンを巻き込み、「自分ごと」として楽しんでもらうことで、ブランドへの共感や共創を促進させています。
参照:ヤッホーブルーイング「約束のよなよなエール | 10年後と20年後に発売されるビール」
ヤッホーブルーイングが、ファンにこれほど愛されるブランドへと成長した理由のひとつには、スタッフの顧客対応が優れていることも挙げられるでしょう。
たとえば、2年前に妊娠を理由に「しばらくお酒が飲めなくなる」とコメントをしていたユーザーから久しぶりに注文を受けたスタッフが、「今回の注文で(飲酒)解禁ですか?」とお話ししたところ、そのユーザーは「自分のことを覚えてくれていた」と喜ばれたそうです。
ヤッホーブルーイングの顧客対応が優れている理由は、顧客情報の一元化にあります。以前は媒体やイベントごとに分かれていた顧客情報を一元化し、カスタマーサポートの担当者が常時確認できるようになったことは大きいでしょう。
ケーススタディなどのマニュアルは特にないため、スタッフはそれぞれ目の前の情報を確認し、ファンが望むことを考えながら、臨機応変に対応しているそうです。
ファンマーケティングを成功させるには、ファンを「広告塔」として見るのではなく、自社ブランドを育てる「仲間」として捉える姿勢がポイントです。ファンと自社の連帯が強まることで、顧客ロイヤリティや満足度の向上につながるでしょう。
参照:日経クロストレンド「ヤッホー実践 「神対応」が自然に生まれるカルチャーのつくり方」
成功事例② カゴメ:「応援される企業」だから社会貢献もできる

1899年に、創業者がトマトの栽培に挑戦したことから始まったカゴメ株式会社。自社で生産から加工・販売まで一貫して行い、着々と成長してきたカゴメにも、売上が伸び悩んだ時期がありました。
野菜飲料を中心に売上金額が下がっていた当時、過去の売上データから「売上の3割を占めるのは、2.5%の優良顧客である」と判明。
その事実を受けたカゴメは「自社商品の購入金額に加え、ブランドへの愛情が非常に高い顧客」を「カゴメファン」と定義し、ファンを維持しつつ増やすための施策を行うことにしました。
これが、2015年にコミュニティ「&KAGOME(アンドカゴメ)」を立ち上げたきっかけです。
2024年の時点で会員数は6万人に増え、オンラインでの交流以外に工場見学や商品の試食体験など、さまざまなイベントも開催しています。
参照:株式会社PR TIMES「カゴメのコミュニティサイト「&KAGOME」が活動ポイントプログラムで募金を実施 | 株式会社イーライフのプレスリリース」
コミュニティで特に成功しているのは、登録会員のみが応募可能なプレゼント企画で、休眠ユーザーの掘り起こしやUGCの生成など、優れたコンテンツになっているといいます。
2019年にカゴメが行ったNPS調査によると、コミュニティ会員のNPSスコアは43.5%で、ほかの接点と比較して高いことがわかりました。
参照:Commune(コミューン)「「KAGOMEらしさ」を追求したコミュニティ。ファンを中心に据えたマーケティング戦略に迫る」
また、カゴメでは2020年1月に、日本の野菜不足を解消する取り組みとして「野菜をとろうキャンペーン」を開始しました。キャンペーンの一環として、野菜摂取推進プロジェクトに参加している企業との料理教室や食育体験イベントなど、さまざまな企画を実施しています。
参照:カゴメ株式会社「KAGOME STORY 会社案内」
カゴメの場合は、こうした企業の社会的責任に基づく取り組みもファン形成に結びついた、稀有な事例といえるでしょう。この事例から、企業の理念とファンの価値観が一致することも大切なポイントであるとわかります。
参照:カゴメ株式会社「みんなとカゴメでつくるコミュニティ &KAGOME(アンドカゴメ)」
なお、このように企業と顧客、あるいは顧客同士を深く結びつけるコミュニティを開設・運用するマーケティング戦略を「コミュニティマーケティング」といいます。
成功例から見える「イベント」の重要性:接点を“体験”で強化

ヤッホーブルーイングとカゴメの成功事例に共通する点は、イベントへの「参加体験」がファンの「記憶」に残り、「語りたくなる体験」になっていることです。
参加者限定グッズの企画開発やバックステージを見せる演出などによって、ファンの記憶に残りやすくすることで、SNSへの投稿、つまりUGCの創出につながるでしょう。
オフラインイベントではすべてをフォローしきれないため、SNSやアプリ、コミュニティなどオンラインツールを活用することで、全国のファンとの距離を縮める工夫も必要です。
オフライン・オンラインにかかわらず、「参加した」という熱量がファン心理を育てるといえるでしょう。
飲食店・ローカル企業のファンマーケティング戦略

ファンマーケティングは、飲食店やローカル企業にも活用できます。たとえば地方のカフェや居酒屋が、地元の常連客とともに新メニューを開発することもできるでしょう。まずは期間や数量を限定して提供し、よい反応を得られたら正式にレギュラーメニューとして加えるという段階を追えば、リスクも抑えられます。
顧客との共創によって得られるメリットは、ほかにもあります。意見を求めても、店舗への愛着がない顧客からは無難な回答しか得られないおそれがありますが、共創関係をしっかり築けているファンであれば、的確なアドバイスを期待できるでしょう。
自社のみでアイデアを出すことが難しい場合も、ファンから想定外の意見を得られる可能性があるのです。
ポイントカード・周年イベントなどによる顧客育成も大切です。来店理由を作ることで、リピート率の向上が見込めます。
SNSを運用して定期的に店舗情報などを発信し、ファンと日常的に交流するよう心がけましょう。たとえ小規模な店舗でも、ファン作りは可能です。距離の近さが武器になるはずです。
失敗“あるある”:ファン心理を誤解した施策はNG!

ここでは、ファンマーケティングにおける失敗例を挙げます。
たとえば会員専用サイトやSNSなどで、企業側が伝えたい情報だけを一方的に押しつけるかたちで配信することで、ファンの共感を得られずに失敗するケースです。ファンの共感を得るには、普段からコメントなどを分析して、ニーズに合う情報を発信しましょう。
ある程度コミュニティの規模が大きくなった企業に多いケースとしては、古参ファンに頼りきりとなり、既存顧客向けの施策を優先して、新規顧客の開拓を後回しにすることも挙げられます。
古参ファンをあまりにも優先させてしまうとコミュニティが閉鎖的に映り、新規ファンが参加しにくい場となるでしょう。
新規に限らず「コミュニティの会話を見ているだけ」のファンも存在します。そのような人たちも気軽に参加できて、ファン同士が交流しやすい場にすることで口コミ効果を得られ、将来的には商品購入にもつながります。誰もが入りやすい場づくりを心がけましょう。
新規顧客開拓のためにインフルエンサーやアンバサダーを起用して、一時的に集客や売上の増加に成功しても、ファン化に直結せず、離脱されてしまうケースも考えられます。顧客目線での「共創」が、ファンマーケティングを成功させるカギといえます。
なお、インフルエンサーマーケティングやアンバサダーマーケティングについては以下の記事をご参考ください。
事例から見えてきた「ファンマーケティング成功の3原則」

これまで取り上げた成功事例から見えてきた、ファンマーケティングを成功させるための3原則を解説します。
まず顧客を単に「商品を売る相手」として捉えるのではなく、一緒にブランドを作る「共創相手」としての関係を築くことです。
企業が一方的に商品や情報を与えるのではなく、顧客にもブランドづくりに参加してもらうことでロイヤリティを高め、ファン化につなげます。
2つ目は、共有できるストーリーや価値観を顧客に語ることです。インターネットによって知りたい情報を瞬時に調べられる現代は、商品を普通に購入するのではなく、「ストーリー性」を重視する顧客が増えているためです。
- どのようにしてこの商品ができたのか
- このサービスを始めたきっかけは何か
- このブランドには、どのようなコンセプトがあるのか
自社ブランドや商品・サービスに顧客が共感できるストーリーを持たせ、SNSなどを通してほかの人々に共有してもらうことで、ファンマーケティングは成功に近づくでしょう。
3つ目は「売上目的」ではなく、「関係育成」を軸にしたファンマーケティング設計を行うことです。
ブランドに愛着を持っているファンは、身近な人々に情報を伝えようとする傾向があります。ファンと良好な関係を育てることで、さらなる集客効果を得られるようになるでしょう。
ファンマーケティングは“顧客との関係性構築”の再定義

ファンマーケティングは、企業と顧客を単なる売り手と買い手としての関係から、一歩深めてくれる手法です。実行後にすぐ効果が出る施策ではありません。中長期的にファンとの関係と信頼を積み重ねていくため、数年先を見据えた計画が求められます。
成功の鍵は「顧客の声に耳を傾け、誠実に向き合うこと」です。ファンを単なる顧客ではなく、企業の「仲間」として考える姿勢が未来を拓くでしょう。
ぜひファンマーケティングを取り入れ、今回ご紹介した事例や成功の3原則を役立ててください。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
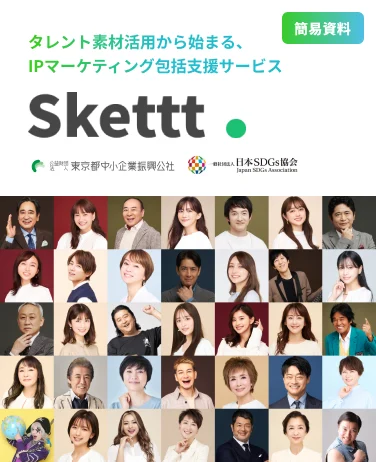
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag