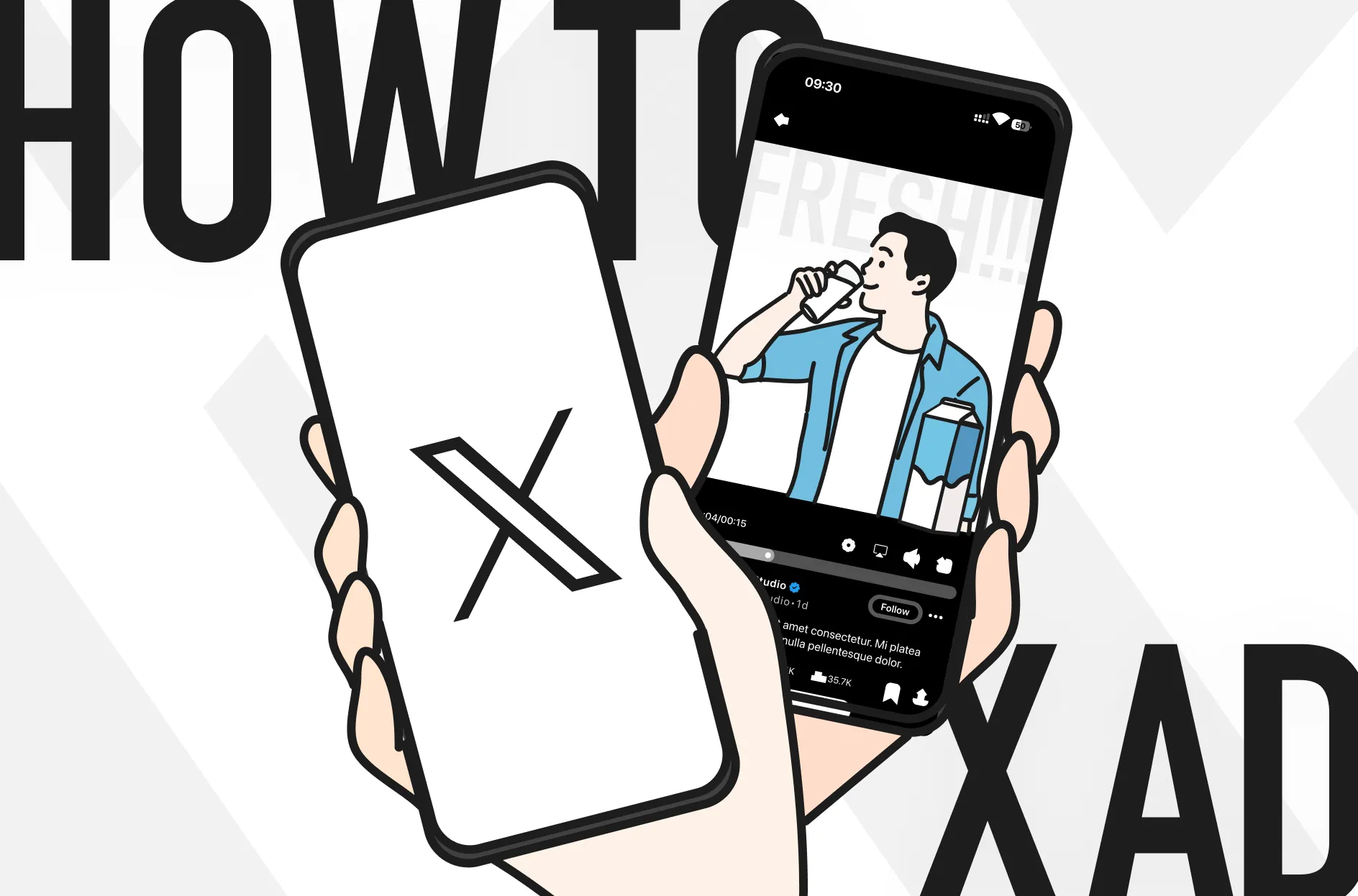マーケティング戦略
オーディオ(音声)広告とは?Spotifyやradiko、バス・電車のアナウンス広告も注目

近年、Spotifyなどの音楽配信サービスやradikoなどのインターネットラジオが広がり、スマートフォンで音声コンテンツを楽しむユーザーが増えています。その流れのなかで急速に成長しているのがオーディオ広告。
この記事では、そもそも音声広告(オーディオ広告・オーディオアド)とは何か、その詳細やメリット、注目される理由、導入する際の活用ポイントについて解説します。
新たな広告方法を模索している方や音声広告の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- 音声広告(オーディオ広告)とは
- オーディオ広告の主な種類と媒体
- オーディオ広告の特徴とメリット
- なぜ今、音声広告が注目されているのか?
- 音声広告の導入・活用ポイント
- “耳”を活用した静かなアプローチで、ブランドはもっと届く

タレント×マーケティングで
成果を最大化
音声広告(オーディオ広告)とは

音声広告とは、音声のみで構成された広告媒体のことを指します。視覚情報を使わずに「耳から入る広告」としてユーザーに届けられるのが特徴です。
「音声広告」「オーディオ広告」「オーディオアド」いずれも一般的に呼ばれています。ただし、時にオーディオアドはデジタル音声広告のみを指すこともあるので、文脈などで見極めるようにしましょう。
音声広告は通勤・通学や家事をしながら聞ける“ながら利用”にマッチしており、現代のライフスタイルに合った広告手法として注目されています。
オーディオ広告の主な種類と媒体
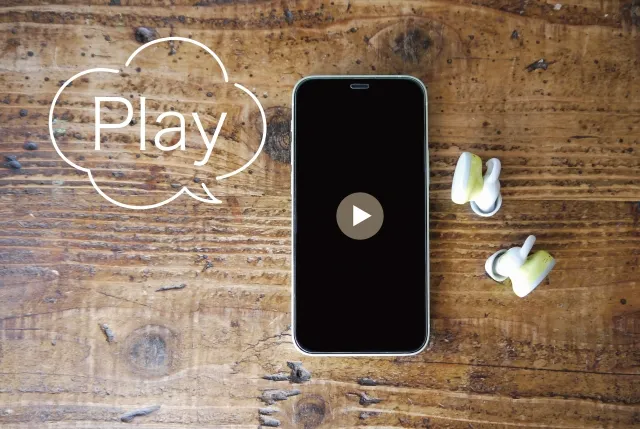
「音声広告」と一口に言っても、その形態や配信される媒体は多岐にわたります。従来のラジオCMにくわえて、近年はあらゆる領域においてデジタルプラットフォームの普及が進み、生活のあらゆる場面に音声広告が組み込まれるようになりました。
ここでは代表的な媒体をいくつか取り上げ、音声広告の多様性を紹介します。
Spotifyなど音楽配信サービス
まず注目されるのが音楽ストリーミングサービスとの連動広告です。Spotify(スポティファイ)をはじめとするプラットフォームでは、ユーザーが楽曲を聴いている合間に広告が挿入されます。
画面を操作していなくても自然に耳に届くため、ブランドのメッセージをストレスなく届けやすい点が特長です。ユーザーの年齢や再生履歴などに基づいたターゲティングも可能で、効率的な広告配信が実現します。
Spotifyは無料登録のユーザーも長時間触れており、1日に平均2時間以上利用されている(2020年10月時点)とのことなので、多くの方にリーチすることができます。
参照:Spotify 広告
世界的にはPodcast市場の拡大も進んでおり、多くの音楽配信サービスがPodcast(ポッドキャスト)も同時に配信していることから、音楽ファンのみならず、Podcaster、あるいはPodcastファンたちも自社ブランドのターゲットに取り込むことができるでしょう。
アメリカなどに比べると日本ではまだPodcastはそこまで普及していないという見方もありますが、若年層から中高年層まで幅広く広まっているところであり、先んじて今から広告を配信して第一想起を獲得するというのも一つの戦略として有効でしょう。
なおPodcastリスナーはアメリカにおいても日本においても、基本的に教育水準が高く、雇用状況や収入もいいという傾向があるため、興味関心を引くことができれば、購買やサービス入会といったアクションを起こしてくれる見込みもあります。
また特に日本市場では、専門性の高いニッチなコンテンツが人気を集めやすいので、なにか特定の領域に特化した商品・サービスの広告とマッチしやすいかもしれません。
参照:evolia「ポッドキャスト広告(音声メディア):日本とアメリカのポッドキャスト事情‐今後の日本市場の展開予想‐」
YouTubeなど動画配信サービス
次に挙げられるのがYouTubeのオーディオ広告です。動画サービスであるYouTubeには「ながら視聴」のユーザーも多く、画面を見ていない状態で利用しているケースも少なくありません。
特に音楽コンテンツだけを切り離したYouTube Musicを利用するユーザーも多く、「YouTubeを耳で楽しむ」のは、もはや広く知られる使い方なのです。
こうした利用シーンに特化したオーディオ広告は、音声だけで訴求することができるため、手軽にブランド認知を高められる手段として注目を集めています。
YouTube オーディオ広告は2022年に開始されましたが、正式ローンチ前のテスト期間中、ベータ版オーディオ キャンペーンの87%が広告想起率の向上に、81%がブランド認知度の向上につながったと発表されています。
参照:Google 広告 ヘルプ「YouTube を聴取しているユーザーにリーチできる「オーディオ広告」がリリースされました」
なお、YouTube広告については以下の記事を参考にしてみてください。
ラジオ(radikoなどインターネットラジオふくむ)
もちろんラジオCMも健在です。従来、ラジオ番組は特定の地域のみにおいて放送されていたり、ニッチなテーマに絞ってトークが繰り広げられていたり、リスナーをセグメントする傾向にありました。
それは同時に、リスナーに近いターゲット層を持つ商品・サービスの広告を番組内で放送すれば、届けたい層に直接ブランドメッセージを伝えることができる媒体であるともいえます。
さらに昨今はインターネットラジオが普及し、ユーザーはより多くの選択肢の中から聞きたい番組を選んで、聞きたいタイミングで聞くことができるようになりました。
広告主目線では、PCやスマートフォンでラジオ、Podcastを聴取できる音声コンテンツプラットフォームradiko(ラジコ)に広告を配信すれば、細かくターゲティングを設定することが可能です。
その完全聴取率は98%、しかもブランドへの興味関心や購入・利用意向も20%以上増幅させることに成功しています。
ラジオの持つ親近感にデジタルのターゲティング精度が加わり、従来型メディアとデジタル広告の橋渡し役として今後も注目を集めつづける媒体でしょう。
バス・電車など公共交通機関のアナウンス広告
公共交通機関のアナウンス広告も忘れてはなりません。電車やバスの車内アナウンスに「次は〇〇駅前、△△ビルは徒歩すぐ」といった情報とともに広告を組み込む手法です。
乗客は近隣住民やその土地を訪れた来訪者と考えられるので、地域密着型の集客や店舗誘導に強みがあります。
通学や通勤など日常的に利用する方も多いため、日常的に反復訴求が叶い、結果、認知度や広告想起率の向上、ひいては繰り返し広告に接触することで自然とそのブランドに好意を抱く「ザイオンス効果」も期待できるでしょう。
ザイオンス効果をふくむ、広告における心理効果については以下の記事をご覧ください。
このように、音声広告は「ラジオCM」という従来の枠を超えて、デジタル音楽配信、動画プラットフォーム、インターネットラジオアプリ、交通機関など、多様な場所で生活に自然に溶け込むように展開されています。
企業にとってはターゲットや目的に応じて媒体を柔軟に選べる時代に突入したといえ、その選択肢の豊富さ自体が音声広告の魅力だといえるでしょう。
オーディオ広告の特徴とメリット

音声広告には、主に以下のようなメリットがあります。
- 「ながら聞き」のニーズ・聴取完了率が高い
- 日常に溶け込み、自然と人々の記憶に残る
- 購買・利用意欲に影響を与える
- 視覚疲労のあるユーザー層にリーチできる
- コンテンツ制作リソースを削減できる
それぞれくわしく解説していきます。
「ながら聞き」のニーズ・聴取完了率が高い
音声コンテンツは通学・通勤などの移動中や家事、仕事、勉強などの最中に「ながら聞き」されることが多く、日々の日常に溶け込みやすいため聴取率が高いのが特長です。
しかも動画広告はユーザーにスキップされることも多いですが、先述のとおりradikoでは98%、Spotifyでも96%と聴取完了率が高いのも音声広告の魅力のひとつといえるでしょう。
参照:Spotify Advertising「聴取完了率96% Spotify広告の強さの理由」
安定したリーチが期待できるマーケティング手法といえるのではないでしょうか。
日常に溶け込み、自然と人々の記憶に残る
前述のとおり、音声広告は「ながら聞き」をするユーザーが多いことから日常生活になじみやすいです。移動中や仕事、家事、勉強、そしてランニングやジムでのトレーニング中など、習慣に紐づいた接触が多いため、繰り返し聴取する可能性が高いでしょう。
くわえてラジオやPodcastのリスナーは特定の番組の固定ファンであることも多いため、同一の番組に毎回広告を出稿すれば、意図的に同じ層に同じ広告を届けることも可能です。
何度も接触することで認知度や広告想起率の向上、先述のザイオンス効果の発揮が期待でき、つまり新規顧客の獲得から見込み顧客の囲い込み、そしてファン化まで促すことができるのです。
そのうえ、映像広告に比べて音声広告のほうが「自分ごと」として捉えやすく、そのストーリーや情報の内容の記憶率も、さらにはその記憶の維持率も高いということがわかっています。
参照:株式会社radiko(PR TIMES)「音声広告は映像広告と比べて記憶の維持率が高い!radiko、その理由を脳科学的実証実験で解明」
たとえば新商品・サービスの認知度拡大、リブランディングの発表、また競合の多い業界であれば、特許取得など独自性のアピール、理念やパーパスなど購買動機を後押しするストーリーテリングにも役立つでしょう。
購買・利用意欲に影響を与える
音声広告は移動中にも聞かれやすいと言及しましたが、Spotifyによると、移動中のリスナーは感情が活性化されており、このときに音声広告に触れると、ランダム配信時よりもエンゲージメントが11.3%増、広告想起率が5.3倍と非常に高くなると発表されています。
参照:Spotify Advertising「聴取完了率96% Spotify広告の強さの理由」(前出)
移動はもちろん通勤・通学に限りません。買い物に向かうこともあるでしょう。徒歩で好きなプレイリストを聴きながら、自家用車でカーラジオを聴きながら、バスや電車でアナウンスを聴きながら、それぞれSpotify広告、ラジオCM、公共交通機関のアナウンス広告に接触する機会があるということです。
リーセンシー効果とは、直前に触れた広告がその後の行動に大きく影響するというものですが、何度も接している音声広告を聴取したあとは、購買意欲にもよい効果を発揮するかもしれません。
ほかの媒体に映像広告も出稿しているブランドであれば、音声広告に触れることで以前見聞きしたその視覚的な広告も思い出し、相乗効果によって購買意欲を誘発するといわれる「イメージャリートランスファー効果」も期待できます。
視覚疲労のあるユーザー層にリーチできる
2023年に実施されたクロス・マーケティングの調査では、全国の20~79歳のうち69%が直近1か月以内に目の疲労を感じていると回答しています。
参照:株式会社クロスマーケティング「【お知らせ】目に関する調査(2023年)」
こうした層にとって、映像や文字による広告は負担になりやすいものです。しかし、音声広告なら目を使うことはないため、ストレスを感じにくいでしょう。
またSNS広告に慣れたユーザーにとって、耳から届く広告は新鮮に感じ、他の広告より受け入れられやすいのではないでしょうか。そのため、バナーや動画広告の代わりとして、多くの企業が注目しています。
コンテンツ制作リソースを削減できる
動画広告は、長尺・短尺を問わず、企画やキャスティング、撮影、編集といった複数の工程が必要になるため、どうしても費用や制作時間が大きくかかります。
その点、オーディオ広告は、音声データや簡単なナレーションを中心に構成できるため、動画広告と比べて低コストかつ短期間で制作が可能です。出稿費もそのほかの広告よりも比較的安価に済みます。
ユーザーに届けたいイメージやメッセージを音声で表現できれば、あまり制作リソースを割かずに作れる広告であるため、初めて広告運用する企業も導入しやすいといえるでしょう。
なぜ今、音声広告が注目されているのか?

スマートフォンや音楽配信サービスの浸透によって、私たちが耳から情報を得る機会は大きく増えました。ポッドキャストやオーディオブックの利用者も拡大し、音声広告を取り巻く環境は急速に変化しています。
改めて今、音声広告が注目されている理由について解説していきます。
音声広告が注目される背景
通勤や家事、運動中などの「ながら聞き」文化が定着しつつあることも影響し、Podcastやオーディオブック市場は拡大しつづけ、人々の耳から情報を得る時間も増えているといえるでしょう。
もちろんスマートスピーカーの普及も、音声広告との相性を高めています。AI音声技術の進化によって自動生成や低コスト制作が可能となり、広告主も新規参入しやすい環境になりました。
このように、音声広告は生活の一部として受け入れられつつあるため、多くの企業が新しい広告として取り入れようとしているのです。
市場規模の拡大
ドイツのデータ収集プラットフォームであるStatistaによると、世界の音声広告市場は2025年時点で71億6,000万USドルの規模に成長すると予測されており、2030年には154億6,000万USドルを突破するといわれています。
参照: Statista「Digital Audio Advertising - Worldwide」
デジタル領域のリサーチを行う株式会社デジタルインファクトの調査によると、国内のデジタル音声広告の市場は2020年の16億円から2025年には420億円規模に拡大すると見込まれています。
参照:デジタルインファクト「デジタル音声広告の市場規模は2020年に16億円、2025年には420億円に」
またwebマーケティング会社のナイル株式会社による15~69歳の男女2,614人を対象にした調査では、2023年の時点で聴き放題の音楽配信サービスの利用者(無料・有料含む)は47%を超えていることがわかっています。
特に10〜20代の若年層の利用率はいずれも67%と高く、こうした若年層による広がりが市場の成長を後押ししていると考えられます。
参照:ナイル株式会社(PR TIMES)「約半数が音楽配信サービスを利用 10代20代は6割超え 人気は「Spotify」「Apple Music」(Appliv TOPICS調べ)」
このように、オーディオ広告は現代のデジタル化を背景に、新しい広告のかたちを築きつつあります。
音声広告の導入・活用ポイント

音声広告を取り入れる際には、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
スモールスタートでテストする
まずは認知度拡大、集客、売上拡大など、音声広告を出稿することでどういった効果を得たいのか、目標・目的を明確にします。
それからいよいよ出稿に臨みますが、いきなり大規模に挑戦するのではなく、まずは低予算・一部エリアのみの配信などターゲットを絞ってテスト配信を行い、ユーザーの反応を確認しましょう。
その後、改善点を見極めてから拡大することで、無駄なコストを抑えられます。一度配信したことで予期していなかったユーザーのニーズを知り、新たな目標が見えてくることも珍しくありません。
冒頭の5秒でユーザーの興味を惹きつける
音声広告で成果を出すためには、冒頭の5秒がカギになります。広告に慣れているユーザーには、すぐにスキップする習慣のある方も多いためです。
また、ながら聞きをしているユーザーは、広告に興味が沸かないと他のことに意識を移してしまうでしょう。そのため冒頭にインパクトを残し、ユーザーに最後まで聴いてもらえるよう工夫することが重要なのです。
たとえば、炭酸飲料の広告なら「プシュッと蓋を開ける音」や「シュワシュワと弾ける音」を冒頭に入れるなど、好印象な記憶を引き出すような仕掛けはいかがでしょうか。
ナレーションは明瞭に音質を最適化する
広告で使用するナレーションは、はっきりと聞き取りやすい発声であることが重要です。リスナーが内容を正しく理解できるようにするためには、声のトーンや話し方に加えて、BGMや効果音の活用にも工夫をこらしたほうがよいでしょう。
また、配信前には音量や音質を丁寧に調整し、どんな環境でも快適に聴けるクオリティを確保することが欠かせません。
なお、声優へのキャスティングを検討中の場合は以下の記事も参考にしてみてください。
既存の音源を有効活用する
オーディオ広告には、すでに公開している自社のテレビCMや動画広告の音声部分を流用することも可能です。新規制作するよりも工数を減らし、スピーディーに配信できるため、音声広告に不慣れな場合もトライしやすいでしょう。
ただし自社の広告の音声とはいえ、起用したタレントの契約条件に音声広告への流用の可能性をふくめていなかったり、他者が制作した音楽を勝手に使用していたりする場合は、もちろん自社判断だけで自由に配信することはできません。
契約条件や権利などをクリアにしたうえで、活用するようにしましょう。
次のアクションを促すフレーズを入れる
オーディオ広告は、最長でも30秒程度と短いものが多いため、ユーザーの印象に残すためには「次のアクションを促すフレーズ」を必ず広告内に入れましょう。
たとえばドラッグストアなどで取り扱っている商品を宣伝したいのであれば、「お近くのドラッグストアへ」のように端的に、起こしてほしい行動を想起させるのがおすすめです。
他の広告と掛け合わせ、効果を高める
先述のとおりオーディオ広告は、記憶に残りやすいこともメリットです。この特性を活かし、さらには同じく先述のイメージャリートランスファー効果も狙って、動画広告やディスプレイ広告と組み合わせれば、相乗効果でより広告効果を高められるでしょう。
成果を測定して改善につなげる
音声広告も他の広告と同様に、広告到達数・再生完了率・クリック誘導数などの指標を追うことが大切です。配信後のデータを分析することで、次回のクリエイティブやターゲティング、広告費の最適化ができます。
“耳”を活用した静かなアプローチで、ブランドはもっと届く

広告が飽和し、生活者がwebサイトを閲覧中などに無意識のうちにバナー広告を無視する「バナーブラインドネス」という現象が、マーケティング業界において問題視される時代になりました。
参照:Readpeak「Banner blindness: The growing challenge for digital advertising」
通勤や家事、運動中などに自然に触れられる音声広告は、一時的な流行ではなく、たしかな効果を持つ手段として市場が拡大しています。
多様化する広告手段のなかで、耳という限られた部分から、しかし確実にメッセージを届けられるのが音声広告のメリットです。
新しい宣伝方法に悩んでいるのであれば、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
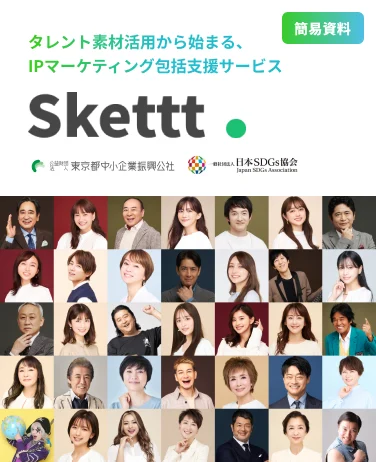
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag