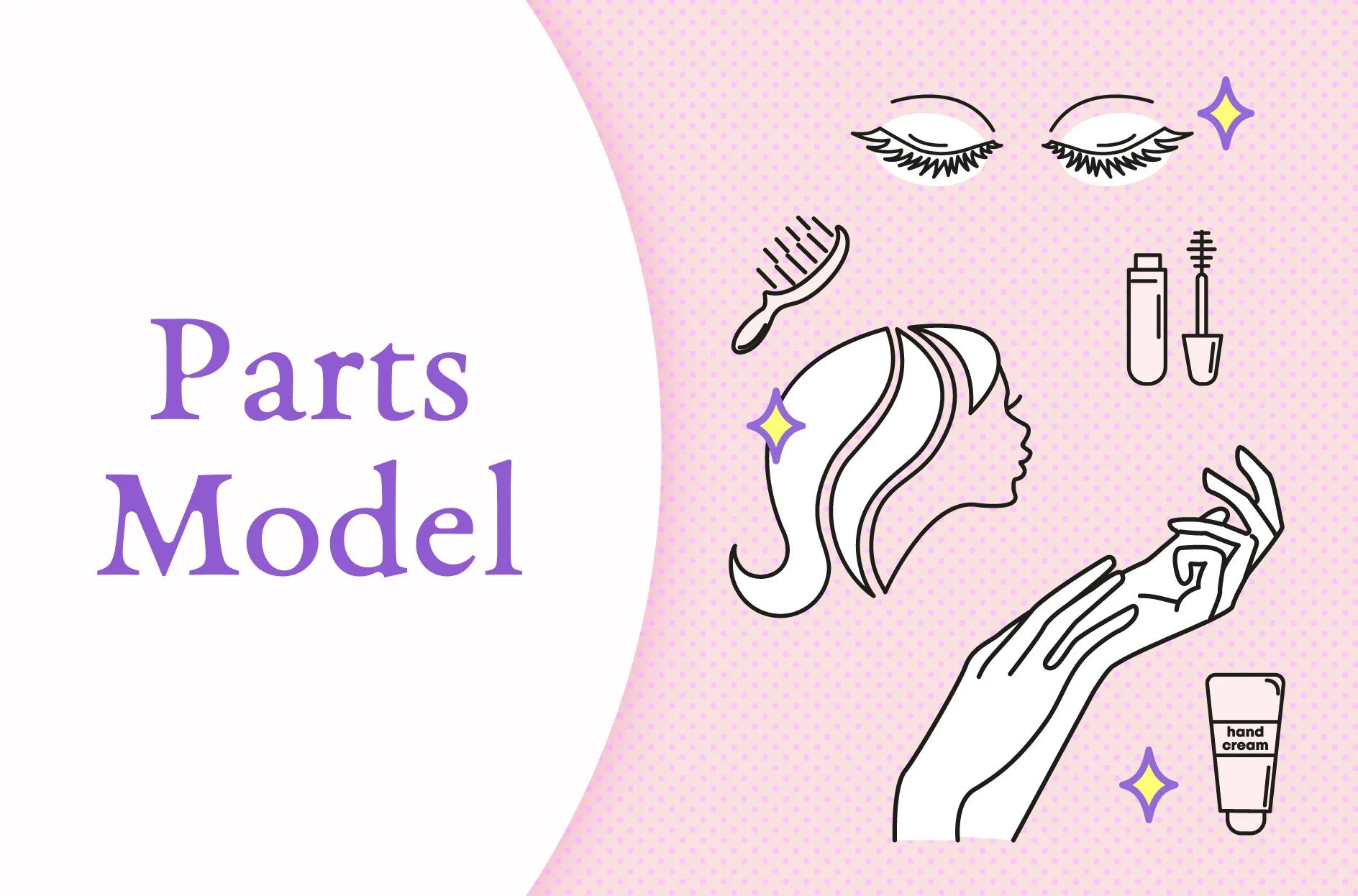マーケティング戦略
イベントマーケティングとは?効果や手法の例・企画の立て方を解説

近年、企業のマーケティング活動において「イベントマーケティング」が注目を集めています。背景には、広告の形態が多様化する一方で消費者に届きにくくなっていることや、商品・サービスの体験価値を重視する消費行動の広がりがあります。
オンライン広告だけでは顧客との関係構築が難しいと感じている担当者にとって、イベントは直接的なコミュニケーションの場として有効でしょう。
本記事では、イベントマーケティングとはなんなのか、その効果・手法の例、成果につなげるための企画の立て方などを解説します。自社のマーケティング施策を検討するうえでのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
- イベントマーケティングとは
- イベントマーケティングの効果・メリット
- イベントマーケティングの手法の代表例
- イベント企画の立て方
- イベントマーケティングで体験を価値に変える

タレント×マーケティングで
成果を最大化
イベントマーケティングとは

顧客に商品やサービスを知ってもらい、ファン化を促す方法として、イベントマーケティングが注目を集めています。
イベントマーケティングの定義
イベントマーケティングとは、セミナーや展示、体験型イベントなどを通じて、顧客や潜在層に直接体験を提供し、商品やサービスの理解、ファン化を促すマーケティング手法のこと。
広告は一方向の情報発信になりがちですが、イベントマーケティングは参加者と双方向のコミュニケーションを重視する点が特徴です。
広告との違いは?
広告は幅広い層に情報を届けられますが、企業から消費者への一方向の情報発信になりがちな手段です。
一方、イベントマーケティングは、参加者が実際に体験したり、質問したりすることで、企業と顧客の関係性を深められます。このような直接的な接点は、商品やサービスの理解を深めるとともに、ブランドへのロイヤリティ向上にもつながります。
イベントマーケティングで目指す3つの効果
イベントマーケティングの主な目的は、以下の3つです。
- 認知拡大:実際に体験することで印象に残りやすく、口コミやSNS拡散も期待できる
- 顧客との関係構築:直接のコミュニケーションを通じて信頼関係を築く
- ブランドロイヤリティ強化:参加者がファンとなることで、長期的なブランド価値向上に寄与する
顧客のファン化を目指すマーケティング戦略、顧客同士の交流を強めるコミュニティマーケティングについては以下の記事をご覧ください。
注目度が高まっている背景
近年、広告だけでは顧客との関係構築が難しくなっていることや、消費者の体験価値への関心の高まりが、イベントマーケティングの注目度を押し上げています。
特にコロナ禍での外出制限を経て、リアルな体験の重要性が再認識され、体験型消費(コト消費)が活発化しています。
たとえば、株式会社グローバルプロデュースの調査によると、過去にカンファレンス型イベントを企画・実施したことがあるBtoB企業の担当者108名のうち、約6割が「新規商談数の増加」を、約7割が「企業認知度の向上」を実感しています。
さらに約8割が直近1年間のデジタル広告のCPAの上昇を感じ、約半数の企業がデジタル広告とイベントの併用を強化する方針を示していることから、戦略的にイベントを活用する動きが広がっているといえます。
イベントマーケティングの効果・メリット

イベントマーケティングには認知度向上やリード獲得、顧客ロイヤリティ向上などの効果が期待できますが、ここでは特に押さえておきたいポイントを解説します。
認知度向上と記憶への定着
イベントマーケティングを実施することで期待できる効果のひとつは、認知度の向上です。広告やオンライン施策だけでは伝わりにくい商品・サービスの魅力も、実際に触れたり体験したりすることで参加者の記憶に残りやすくなるでしょう。
さらに、体験した内容は口コミサイトやSNSで広がりやすく、企業や商品の認知度向上に寄与します。直接体験を通じてブランドを理解してもらえる点が魅力です。
見込み顧客獲得と意欲の把握
イベントでは一度に多くの見込み顧客と接点を持つことができ、参加者の関心度や行動から意欲の高さを把握できます。このため、商談やフォローアップを効率的に進めることが可能です。
その場に立ち会うからこそ、参加者のリアルな反応や興味の度合いを即座に把握でき、その後の営業活動に役立てられるでしょう。
顧客ロイヤリティ向上とデータ活用
参加者が商品やサービスを体験することで、実際の価値や魅力を肌で感じられるためファン化が進み、結果としてリピート購入やブランド価値の向上につながります。
また、参加者の属性や反応データを分析することで、次回以降のイベント改善や他のマーケティング施策に活用できるのも大きな利点となるでしょう。
イベントマーケティングの手法の代表例

イベントマーケティングにはさまざまな手法があるため、代表的な施策と特徴を解説します。
セミナー
セミナーは、自社の持つ専門知識や最新情報を伝えることで、参加者の信頼を獲得する手法です。自社で開催、または他社と共催するケースもあるでしょう。オンラインで実施するウェビナーも一般的です。
また、セミナーは目的に応じて大きく2種類に分けられます。「情報提供型」はセミナーそのものが価値となり、参加者に有益な知識を届けることが目的。そのため、有償で実施されることも多いです。
一方、「顧客獲得型」は自社商材の理解を深めてもらい、購入や商談につなげることを目的に実施されます。
展示会
展示会は、新商品やサービスを直接体験してもらい、購入やリード獲得につなげる手法です。運営会社や自治体が集客を担当する場合もあり、自社で集客負担をかけずに参加できます。リード創出やブランディング、商品理解促進などのフェーズに適しているでしょう。
ミートアップ
ミートアップは、小規模でフラットな交流の場を作るイベントです。参加者との意見交換や情報共有を通じて、ファンやビジネスパートナーとの関係を深める目的で実施されます。セミナーのように一方向に情報を伝えるのではなく、参加者とやりとりしながら進められる傾向があります。
体験型イベント
試食・試用・ワークショップなど、参加者が実際に商品やサービスを体験できるイベントです。五感に訴えるアプローチで印象に残りやすいため、ブランド理解や購買意欲の向上につながるでしょう。
ユーザー交流会
既存顧客とのつながりを強化し、ファン化やリピート購入につなげるイベントです。参加者同士でナレッジを共有したり、コミュニティを形成することで、ブランドロイヤリティの向上や解約防止にも役立てられるでしょう。
ハイブリッド活用で効果を最大化
オンライン施策を活用することで、世界中の参加者にリーチできます。ウェビナーや配信型イベントの録画、アクセスデータを活用すれば、参加者の視聴状況や関心度を把握でき、フォロー対象の優先順位付けや次のアプローチに役立てられるでしょう。
さらに、その情報をオフラインイベントと連携させることで、個々の関心に応じたパーソナライズ施策が可能となり、リード獲得につなげたり商談の精度を高めたりすることもできます。
たとえば、オフラインのミートアップや体験型イベントに加え、オンラインのセミナーや交流会を組み合わせることで、参加者の幅を広げながら、自社に最適なイベントマーケティング戦略を構築できるでしょう。
また実際に試用できる商材がある場合は、イベント会場でサンプルを提供して感想をSNS上で投稿してもらうことで、その後につなげることも可能です。
サンプリングマーケティングについては以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてご覧ください。
イベント企画の立て方

効果的なイベントマーケティングを実施するには、企画段階から注力することが重要です。具体的に、どういった流れで企画を作るか解説します。
1. 目的・KPIの設定
まずはイベントの目的を明確にします。認知拡大、リード獲得、顧客ロイヤリティ向上など、何を達成したいかを定め、それに沿ってKPI(進捗指標)とKGI(最終目標)を設定しましょう。KPIを具体的に定めることで、イベントの成果を計測しやすくなります。
2. ターゲットと形式の選定
対象となるターゲット層を具体的に決めます。BtoBの場合は業種、BtoCの場合は性別、年齢層などを明確化し、目的に合ったイベント形式を選びます。セミナー、展示会、体験型イベントなど、形式によって得られる効果や運営方法が異なるため、目的に応じて選ぶことが大切です。
まだ認知されていない新規ブランドの場合は、著名タレントを呼んで広告塔になってもらうというのも一つの手です。著名人をイベントに招致する際の費用や詳細は、こちらの記事をご覧ください。
3. 集客・告知
イベントの成功には集客が不可欠です。SNSや広告、メール、DMなど複数のチャネルを組み合わせ、ターゲットに最適な方法で告知します。告知段階で参加者の興味を引く内容や特典を提示することも効果的でしょう。
DMの文章の参考にこちらの記事もご覧ください。
4. 当日の運営
参加者の体験価値を高めるため、スタッフの配置やトークスクリプト、進行手順を事前にシミュレーションします。役割分担や対応策を明確にすることで、スムーズな運営と参加者の満足度向上につながります。
5. 終了後のフォロー
アンケートやCRMシステムを活用して参加者の反応や属性を分析し、次の商談や施策に活かします。営業部門と連携し、獲得リードを迅速にフォローすることが、イベントの成果を高める鍵となるでしょう。
成功のためのポイント
効果的なイベントの裏には、細やかな準備と事後の振り返りが欠かせません。開催前にはリスクを洗い出し、想定されるトラブルや参加者からの質問に備えましょう。オンライン開催の場合は、配信機材や接続環境の確認、事前リハーサルも必要です。
また、イベント終了後は設定したKPIがどの程度達成されたかを振り返ります。参加者数やアンケート回答率、商談化率や売り上げなどを確認し、得られたデータを次回に活かすことで、イベントを単発で終わらせず、継続的に成果を積み上げられます。
イベントマーケティングで体験を価値に変える

広告離れが進む現代において、体験を通じた顧客とのコミュニケーションはブランド理解や信頼構築に有効です。セミナーや展示会、体験型イベント、ユーザー交流会など、目的に応じて実施することで、参加者に印象的で有意義な体験を提供できます。
イベントを成功させるためには、まず「体験そのものの価値」を意識することが大切です。単に情報を伝えるのではなく、参加者が実際に触れ、試し、感じることができる設計にすることで、学びや気づきが自然に深まり、ブランドへの共感も高まります。
イベント後のフォローも重要です。メールや限定コンテンツで体験の余韻を活かし、次の行動につなげましょう。
体験を価値に変えることが、イベントマーケティングの本質です。質の高い体験と丁寧な運営・フォローで、単発イベントで終わらず、リード獲得や商談、ブランドロイヤリティ向上につなげられるでしょう。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
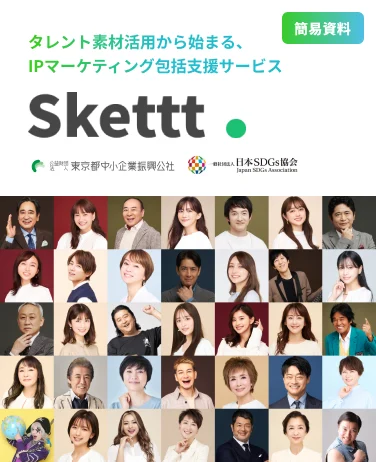
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag