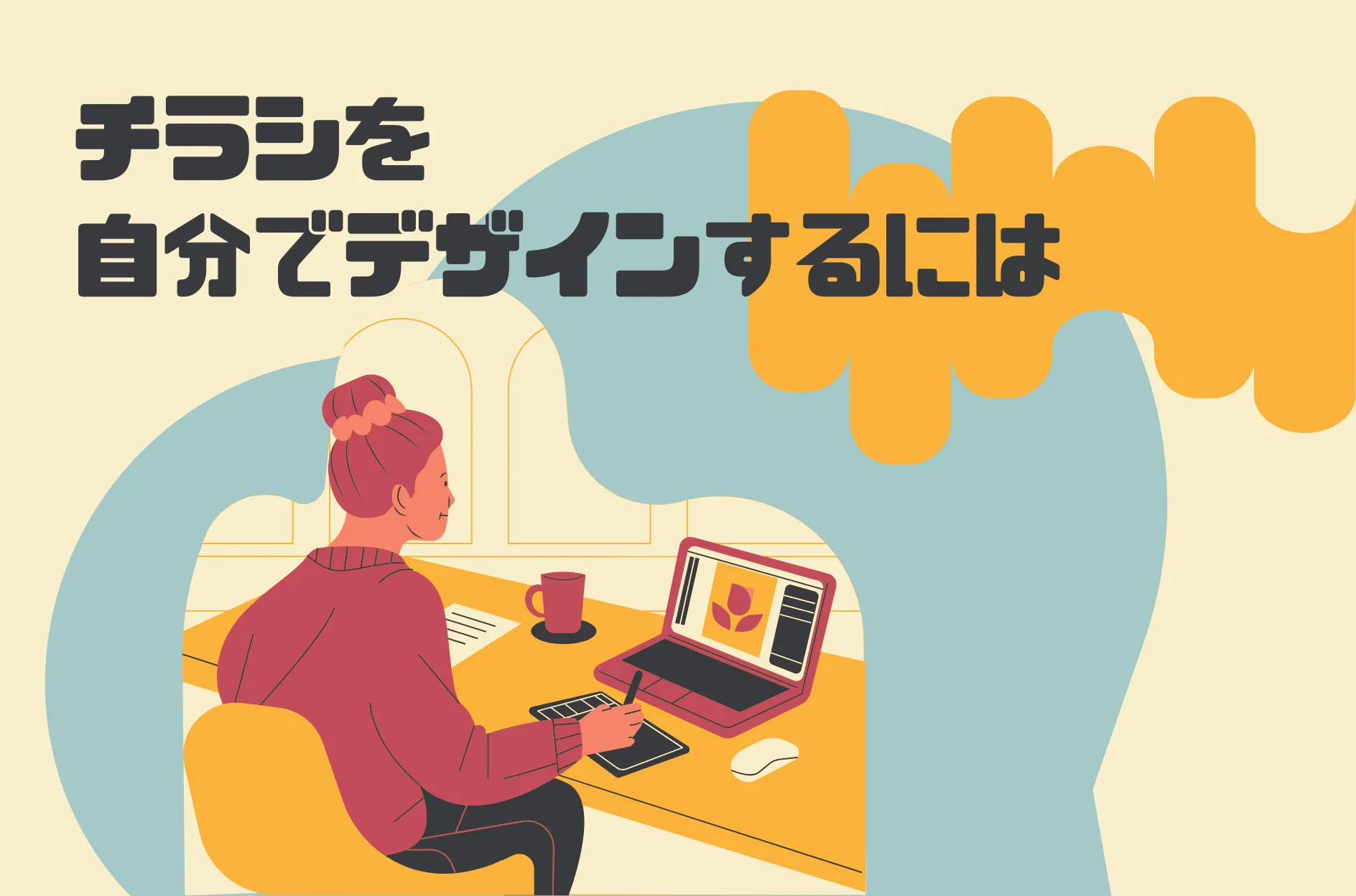マーケティング戦略
営業成果につなげる!ダイレクトメールの挨拶文・文例ガイド

ダイレクトメール(DM)は営業活動や販促施策において、ターゲットと直接つながる有効な手段です。その挨拶文は、最初に読まれる重要なパートであり、たった数行で印象が決まるため、読者の関心を引けるかどうかが左右されます。
とはいえ、形式的すぎる文面では思いが伝わりづらく、営業色が強すぎる場合は敬遠されてしまうこともあります。本記事では、そんなダイレクトメールの挨拶文をより効果的に届けるために例文を交えながら考え方や工夫のポイントをご紹介します。
- ダイレクトメールにおける挨拶文の重要性とは
- 挨拶文の基本構成と書き方のコツ
- 目的・場面別の文例・テンプレート集
- 季節の挨拶に使えるフレーズ集【春夏秋冬】
- 送付状・添え状の書き方と活用例
- ダイレクトメールでよくあるNG挨拶文と改善ポイント
- 挨拶文でDMの営業成果は変わる

タレント×マーケティングで
成果を最大化
ダイレクトメールにおける挨拶文の重要性とは

ダイレクトメールにおいて挨拶文は、続きを読むか・読まないかの分かれ目となる非常に重要なパートです。特にBtoB(企業向け)の営業DMの場合、相手は日々多くの文書に目を通しているため、冒頭の数行で関心を引けるかどうかが勝負になります。
また、ダイレクトメールは一方的に情報を届けるコミュニケーション手段だからこそ、挨拶文には丁寧さや誠意を感じさせる表現が欠かせません。単なる定型文ではなく、「この人からの手紙は読んでみよう」と思わせる工夫があるかどうかが、その後の反応を左右します。
特に新規開拓や休眠顧客への再アプローチなど、関係性の浅い相手ほど、第一印象となる挨拶文の質が信頼獲得のカギを握ります。営業色を出しすぎず、親しみと誠実さを両立させた文面が、読者の心を動かすきっかけとなるのです。
挨拶文の基本構成と書き方のコツ

ダイレクトメールの挨拶文には、読み手に好印象を与え、次の内容へと自然に導く役割があります。書き出しから結びまでを丁寧に組み立てることで、信頼感と親しみやすさを両立した文面に仕上がります。基本構成は以下の流れです。
1.宛名・敬称
法人宛であれば「株式会社○○ ご担当者様」、個人宛であれば「○○様」など、相手に応じた宛名を記載します。
2.季節・時候の挨拶
「初夏の候」「日頃よりご愛顧いただき誠にありがとうございます」など、時期や関係性に応じた挨拶を加えると丁寧な印象になります。
3.自己紹介・本文導入
自社の紹介や新製品の案内などを簡潔に述べつつ、相手にとっての利点や背景を添えることで読みやすさが増します。
4.要件・提案内容
売り込み感が強くならないように注意しながら、読み手にとってのメリットを主題にして伝えると自然です。特にBtoBビジネスにおいて導入実績や業務効率化など相手視点の情報が有効です。
5.結びの言葉・締め
「ご検討のほど、よろしくお願いいたします」「ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください」など、前向きでやわらかな表現で締めくくりましょう。
文章のトーンは、BtoBの場合は丁寧かつ論理的な文体が、BtoCの場合は親しみやすさや感情に寄り添った表現が効果的です。どちらの場合も「伝えたいこと」ではなく「相手が知りたいこと」を意識するのがコツです。
目的・場面別の文例・テンプレート集

ダイレクトメールの挨拶文は、送る相手や目的に合わせて内容や表現を変えることが重要です。ここでは代表的な5つのシーンごとに例文とポイントを紹介します。
新規開拓DM:初めてのご案内時
「拝啓 ○○の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。突然のご連絡失礼いたします。このたび、御社の○○に関する取り組みを拝見し、大変興味を持ちました。貴社のさらなるご発展に向け、微力ながらお役立てできることがあればと存じ、ご案内を差し上げた次第です。」
初対面の相手には丁寧な自己紹介を入れつつ、売り込み感を抑えた表現が効果的です。
キャンペーン案内DM:イベント・期間限定オファーなど
「平素よりお世話になっております。〇月〇日から期間限定で特別キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会にご利用ください。」
期間限定の特典を強調して、緊急性やメリットを伝えましょう。
季節のご挨拶DM:年賀・お中元・お歳暮の添え状
「拝啓 新春の候、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。」
季節感を取り入れつつ、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
展示会や面談後のフォローレター:ご来場・ご面談への御礼
「先日は弊社ブースにお立ち寄りいただきありがとうございました。今後ともご期待に添えるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。」
感謝を伝え、次のアクションへつながるよう期待感を持たせましょう。
休眠顧客向け:再提案やアップセル用DM
「ご無沙汰しております。株式会社○○の□□です。このたび新たなサービスを開始しましたので、ご紹介させていただきます。」過去の取引への感謝を込めつつ、自然に新提案を行うと効果的です。
これらの例文はあくまで基本の型ですが、実際に送る際は、自社の商品・サービスの特徴や、相手との関係性、タイミングなどに合わせてアレンジすることが重要です。
文面に少し手を加えるだけでも印象は大きく変わります。丁寧かつ自然な言葉選びを意識しながら、送る相手や目的にフィットしたメッセージを心がけましょう。
季節の挨拶に使えるフレーズ集【春夏秋冬】

ダイレクトメールの挨拶文は、時候の挨拶を添えることで、丁寧で印象のよい文面になります。特にBtoBの場合はビジネス文書の慣習であり、形式的な礼儀を重んじる企業間のやり取りで信頼感や誠実さを伝える手段として有効です。
初対面や関係性が浅い相手にも、配慮の行き届いた印象を与えられます。一方BtoCの場合は、やわらかく親しみやすい雰囲気を与える効果が期待できます。
ただし、丁寧さを心掛けるあまり硬い表現になってしまうと、不自然に感じられることもあるため注意が必要です。
【春(3~5月頃)】
- 春暖の候
- 新緑の候
やわらかな季節感を伝える表現で、入学や新生活などの前向きな雰囲気を演出できます。明るく爽やかな文面にしたいときに向いています。
例:春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
【夏(6~8月頃)】
- 盛夏の候
- 残暑厳しき折
暑さを気遣う一言を添えることで、季節感を与えつつ、相手への配慮が感じられる文面になります。お中元や夏季キャンペーンDMの冒頭などにおすすめです。
例:残暑厳しき折、皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます。
【秋(9~11月頃)】
- 実りの秋
- 秋冷の候
落ち着いた季節感が伝わり、展示会や新商品の案内にも使いやすい表現です。穏やかなトーンで信頼感を与えたいときに向いています。
例:秋冷の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。
【冬(12月~2月頃)】
- 年末ご多忙の折
- 厳寒の候
寒さや年末の忙しさを気遣う表現を添えることで、相手への配慮が感じられる文面になります。年末年始のご挨拶や冬の販促DMに最適です。
例:年末ご多忙の折、貴社ますますのご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
時候の挨拶は、相手や文面全体のトーンに合わせて少しやわらかくしたり、省略したりすることも可能です。あくまで自然な流れのなかで使うことを意識すると、より効果的です。
送付状・添え状の書き方と活用例

資料やパンフレットを送付する際は、送付状(添え状)を同封することで、丁寧で信頼感のある印象を与えることができます。特にBtoBの営業DMの場合、たとえ形式的なものであっても一言添えるだけで、相手への気遣いや誠意を伝える効果があるでしょう。
送付状は一般的に、頭語や時候の挨拶から始まり、続いて簡潔な自己紹介や要件の説明、同封資料の案内、そして今後の連絡やお願いを含む締めの挨拶といった流れで構成されます。
たとえば、「○○の資料もお送りいたします」「ご検討いただけましたら幸いです」といった一言を加えるだけでも、受け取る側の印象は大きく変わるものです。
あらかじめ送付状フォーマットを社内で準備しておけば、案件ごとに一から文章を考える手間を省くことができ、業務の効率化にもつながります。送付状は小さな工夫で信頼感を高める、DMの印象を左右する大切な要素といえるでしょう。
汎用的な送付状テンプレート
【送付状本文】
拝啓 ○○の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、○○のご案内資料をお送りいたします。
ご多忙の折とは存じますが、ぜひご一読いただけますと幸いです。
まずは書面をもちましてご案内申し上げます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
【活用のポイント】
このテンプレートは、業種や目的を問わず幅広く活用できる汎用的な文面です。「○○」の部分に季節の挨拶や案件名を加えたり、宛名を入れたりすることで、状況に応じたアレンジが可能です。
ダイレクトメールでよくあるNG挨拶文と改善ポイント

ダイレクトメールは、挨拶文の書き方ひとつで相手の反応が大きく変わります。特に注意したいのが、ありきたりで形式的すぎる文面や、営業色が強すぎて警戒される表現です。
加えて、相手の関心やタイミングを無視した内容は、読まれる前に破棄される可能性もあります。
たとえば、以下のような文面は避けたほうが無難でしょう。
【NG例】
「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、この度弊社では新サービスを開始いたしましたのでご案内いたします。」
一見丁寧な印象ですが内容がありきたりで、誰に対しても同じ文面を送っているように感じられます。
【改善例】
「拝啓 日頃より大変お世話になっております。さて、○○に関心をお持ちの皆様に向け、新たなサービスをご案内させていただきます。」
相手に合わせた一言を加えるだけでも、関係性や関心に寄り添った文面に感じられます。挨拶文は相手との接点を築く第一歩と考え、定型文に頼らず一工夫を加えることが大切です。
挨拶文でDMの営業成果は変わる

ダイレクトメールにおける挨拶文は、単なる形式的な導入ではなく、読み手との関係構築の第一歩です。最初の数行で信頼感を与えられるかどうかが、その後の反応を大きく左右します。
丁寧で自然な文面は「この会社なら信頼できそう」という印象を与え、読み手の関心を引き出すきっかけにもなるでしょう。
また、挨拶文は事前にいくつかフォーマットを用意しておくことで、自社のDM施策全体の質を底上げすることが可能です。場面や相手に応じて柔軟に使い回せるテンプレートがあれば、複数のDM作成にも対応しやすく、業務の効率化にも役立ちます。
DMの効果を高めたいときほど挨拶文をおろそかにせずに、目的や読み手に合った表現を工夫することが大切です。小さなひと手間が、営業成果の差を生むことにつながります。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
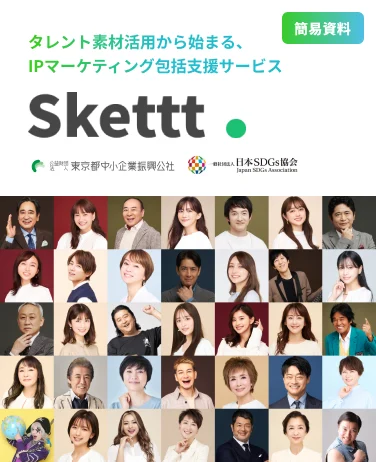
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag