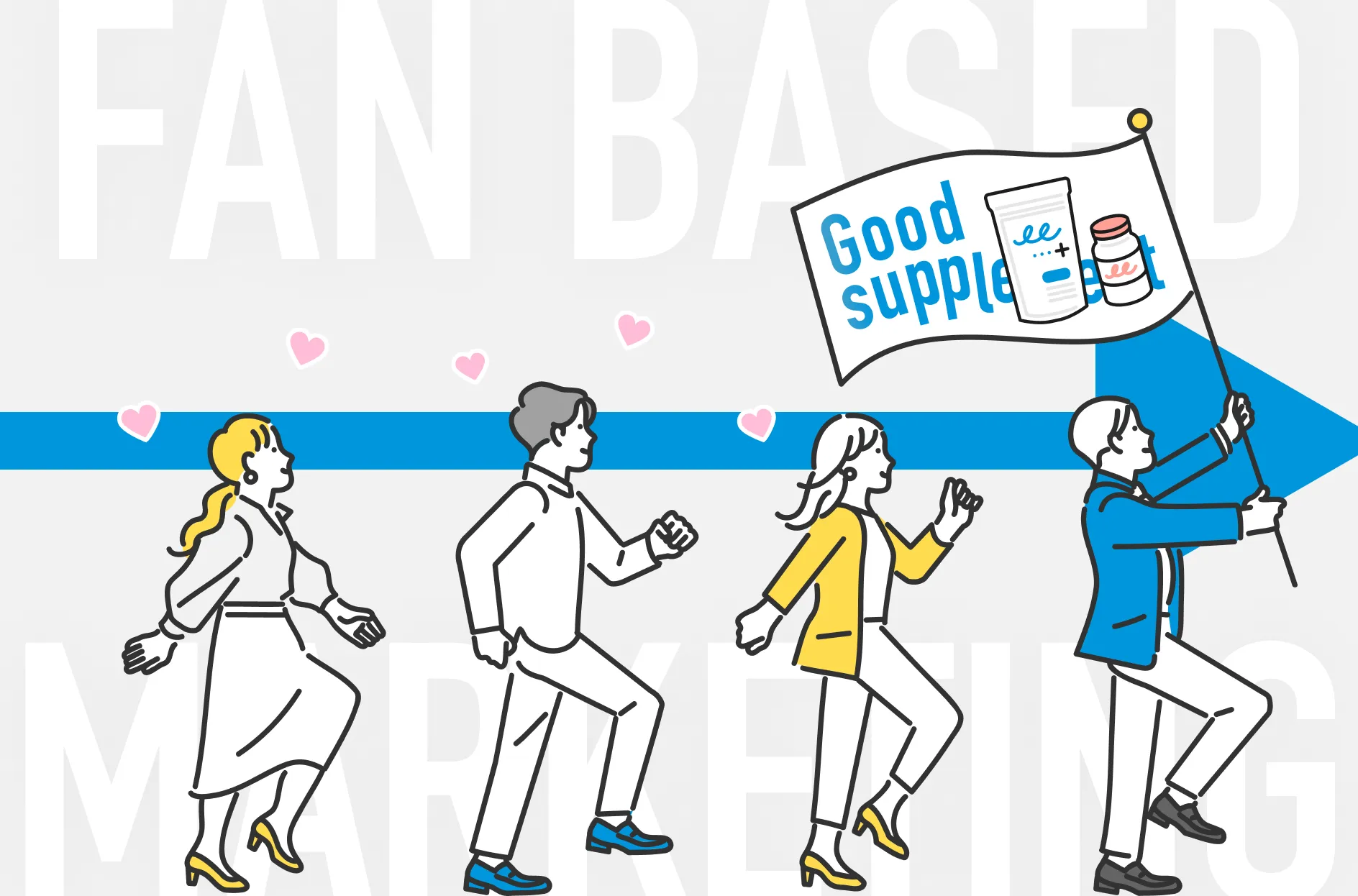マーケティング戦略
コミュニティマーケティングの成功事例4選:AWSやスノーピークに学ぶ企業戦略

SNSによる顧客との交流が増えている現代は、たとえ自社の売上に直結しなくとも、より深い「つながり」に投資する時代となりつつあります。
現代の企業に必要なものは、一度きりの施策ではなく、ブランドの成長エンジンとなるコミュニティの力です。コミュニティによって、顧客との関係は「点」から「面」に変わります。
この記事ではコミュニティマーケティングの成功事例を4つ紹介すると同時に、成功した企業に共通する要素を解説します。実際にコミュニティマーケティングを展開する際の参考にしてください。
- コミュニティマーケティングの成功事例①:AWS(JAWS‐UG)
- コミュニティマーケティングの成功事例②:スノーピーク(Snow Peak Way)
- コミュニティマーケティングの成功事例③:カインズ(CAINZ DIY Square)
- コミュニティマーケティングの成功事例④:mineo(マイネ王)
- 成功事例に共通する3つの要素
- 売らずに語る、語らずとも伝わるブランドへ

タレント×マーケティングで
成果を最大化
コミュニティマーケティングの成功事例①:AWS(JAWS‐UG)

ここからは早速コミュニティマーケティングの事例を紹介します。先にコミュニティマーケティングについて、その概要や基本情報を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
AWS(Amazon Web Services)とは、アマゾンが提供する、全世界で利用されているクラウドコンピューティングサービスです。AWSを利用すると、提供されている300種類以上のサービスを組み合わせて、アプリの開発やシステム運用などに活用できます。
JAWS-UG(AWS User Group - Japan)は、日本のAWSユーザーたちがサービスに対する知識と交流を深めるために設立されたコミュニティで、地域別・目的別の支部があります。
JAWS-UGを立ち上げたのは、AWSJ(当時はADSJ:Amazon Data Services Japan)の社員だった小島英揮さん。2009年12月、小島さんはAWSJを主体としたJAWS-UGを設立しました。
2010年2月23日にJAWS‐UGのキックオフイベントが開催され、2011年3月には東京リージョンを開設。同年の3月4日には各地のJAWS-UGリーダーが東京に集結し、活動は盛り上がりを見せました。
しかし翌週、東日本大震災が発生。この際多くのWebサイトがダウンしたため、JAWS-UGの中心メンバーとAWS社員はボランティアチーム(通称タイガーチーム)を結成し、AWSの無償提供・Webサイトの構築支援にあたりました。
この体験を機に、AWSとユーザー、さらにはユーザー間にも強い絆が生まれたとのことです。現在も拡大を続け、日本有数の規模を誇るJAWS-UGは、コミュニティマーケティングという分野を確立した立役者ともいえるでしょう。
参照:アマゾン ウェブ サービス(AWS クラウド)
参照:ASCII.jp「AWS卒業の小島英揮さんがJAWS-UGの舞台裏を語り尽くす」
参照:JAWS-UG(AWS User Group – Japan)
コミュニティマーケティングの成功事例②:スノーピーク(Snow Peak Way)

オートキャンピングメーカーとして有名な株式会社スノーピークは、登山家でもあった初代社長の山井幸雄さんが、1958年に新潟県の燕三条で開いた金物問屋が始まりです。
スノーピークでは、人生を構成する「衣食住働遊」の5つに合わせた事業を展開しています。例えばオートキャンプ用品や衣服の製造販売、キャンプ料理を提供するレストランの経営などです。
この事業に、コミュニティマーケティングの要といえる、キャンプイベント「Snow Peak Way」「Snow Peak Way PREMIUM」も含まれます。
Snow Peak Wayは、すべての社員がキャンパーとして参加し、ファンとともに焚火を囲んで楽しむキャンプイベントで、Snow Peak Way PREMIUMは2017年から開催されている、ブラックカード以上の会員を対象としたイベントです。
Snow Peak Wayを始めたきっかけは、日本でのオートキャンプブームが終わり、アウトドア関連の企業が次々と経営難を迎えたことでした。
当時、例にもれず窮地に追い込まれたスノーピークは、顧客とともにキャンプを楽しみ、直接声を聞くことで打開策が見つかるのでは、という期待をかけ、Snow Peak Wayを開催したそうです。
そのためスノーピークでは、1998年以降、ディーラーの数を大幅に削減し、広告に充てていた費用をコミュニティイベントに投じるなど、2年がかりでマーケティング戦略の改革を行いました。
開催当時はまだコミュニティマーケティングの重要性が広がる前でしたが、2000年頃に施策が実を結びだし、2024年の時点で、30万人を超える会員やファンで構成されるほど、大がかりになりました。
Snow Peak Wayで社員が直接交流することが顧客のファン化につながり、オンラインイベントとの連動で、さらに強固な関係性を築いています。
また、商品の販売後も顧客との関係を継続させる仕組みを作った「永久保証」もマーケティング改革のひとつで、この結果、LTVの改善と顧客満足度の向上につながりました。
参照:「スノーピーク * Snow Peak」
参照:MarkeZine(マーケジン)「ブランドはお客様と一緒に創っていくもの スノーピークのコミュニティ施策の裏にあったストーリー (1/3)」
参照:CXin(シーエックスイン)「ファンコミュニティの成功事例11選」
コミュニティマーケティングの成功事例③:カインズ(CAINZ DIY Square)

1989年に株式会社いせやから分社・独立して設立したのが、株式会社カインズです。同社は大規模ホームセンターのほか、会員制卸売店舗「C’z PRO」やカフェ「CAFE BRICCO」など、さまざまな業態で全国展開しています。
カインズでは「写真を撮って飾る」「掃除する」「料理する」といった、暮らしを楽しむために自分で行うすべてのことを「DIY」として捉え、DIYに取り組む顧客を「DIYer(ディアイワイヤー)」と呼んでいます。
そして2019年に、このDIYerをサポートするために生まれたプロジェクトが「DIYer100万人プロジェクト」です。
オフラインだけでは顧客との接点が少なく、可能なサポートも限られるため、カインズは2021年に、DIYer同士がオンラインとオフラインでつながるコミュニティ「CAINZ DIY Square(カインズ ディアイワイスクエア)」を立ち上げました。
2024年時点で会員数は4万人にのぼります。コミュニティに参加している顧客のLTVは、カインズ会員全体の平均より高いそうです。
今後はコミュニティで顧客の要望や意見を聞き、ニーズに合う商品を開発し、提供する流れを作りたいとのことでした。
参照:株式会社カインズ「CAINZ DIY Square | カインズDIY総合サイト」
参照:株式会社カインズ「ホームセンターのCAINZ 公式企業サイト」
参照:株式会社宣伝会議「「DIYをライフスタイルに」のミッション達成を目指すカインズのファンコミュニティ」
参照:coorum(コーラム)「株式会社カインズ|DIYをライフスタイル(生活文化)に!カインズが取り組む「コミュニティ」の導入背景と展望とは」
コミュニティマーケティングの成功事例④:mineo(マイネ王)
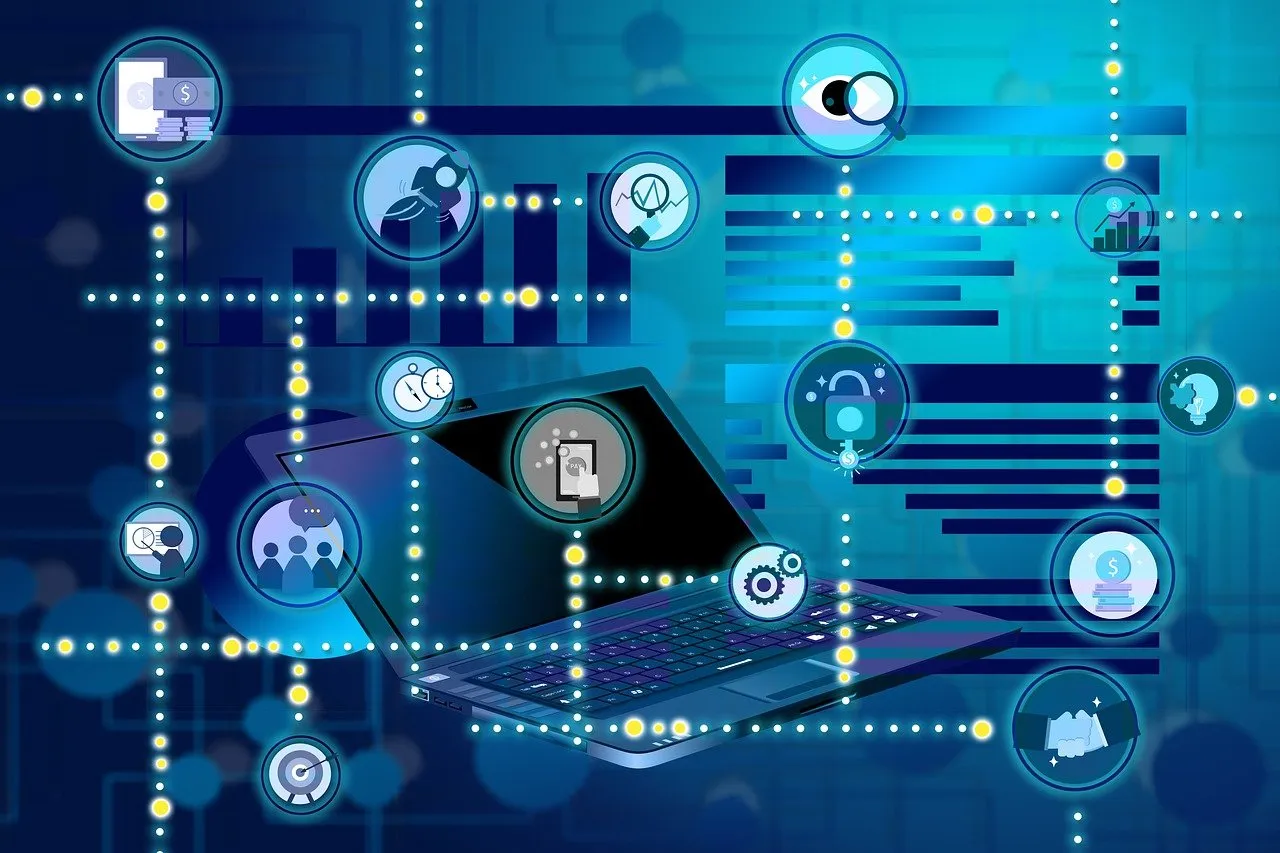
通信サービスmineoのファンコミュニティ「マイネ王」は2015年1月にスタートして、2025年時点で86万人もの会員数を誇ります。
MVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)業界は競合が多く、価格以外の価値を提供して差別化を図らなければ生き残ることが難しいということが、mineoがコミュニティをつくるきっかけでした。
マイネ王は通常の交流コーナーだけではなく、アイデアを投稿できる「アイデアファーム」やゲーム、パケット活用コーナーなど、コンテンツがとても充実しています。
さらに、mineoはオフラインイベントにも注力しています。mineoの情報を開示し、ユーザーの意見を聴取するほか、食事込みの懇親会も開くそうです。
通常のオフラインイベントは日本各地で行われ、抽選で30~40人の会員が参加するとのこと。スタッフが仲間意識を持って接することでユーザーへの誠意が伝わり、ファン化につながったといいます。
しかし、130万回線(2025年時点)すべての契約者が参加するのは難しいため、mineoはオンラインで楽しめる企画を打ち、コミュニティの活性化を成功させました。
アプリのレーダー機能を使った陣取りゲームで、地方在住ユーザーの反響が特に多く、このイベントを機にマイネ王へのコメント数も増えたといいます。
マイネ王が成功したポイントとしては、自社の提供サービス(通信)とコミュニティの内容がかみ合っていたことでしょう。
マイネ王も会員数が伸び悩んだ時期はありましたが、会員同士でパケットのやり取りをできる機能や、貯めたパケットをシェアする機能を増やした際に、新規登録者数が伸びたそうです。
参照:株式会社Hakuhodo DY ONE「お客様と一緒にブランドを育てていく。mineoから学ぶファンマーケティングの本質 【DIGIFUL】デジフル」
参照:mineo(マイネオ)コミュニティサイト - マイネ王
成功事例に共通する3つの要素

ここでは、コミュニティマーケティングの成功事例に共通する、3つの要素を解説します。
成功している企業に共通する要素のひとつは、コミュニティがファンの“熱量”を尊重する設計になっていることです。コミュニティには、積極的なファンによる投稿が多く見られるでしょう。
しかし、投稿せずに眺めて楽しむファンは、それ以上に多いといわれます。そのため、投稿したことがないファンの熱量をいかに上げられるかが重要です。
コミュニティマーケティングの成功事例に共通する要素として、売上を直接求めず、コミュニティを「余白」のある空間にしていることも挙げられます。
コミュニティはファンと企業、もしくはファン同士がブランドや商品・サービスに関する話題で盛り上がる場所として位置づけ、ECサイトとは切り離して考えるべきでしょう。
コミュニティで購入を促す行為が目立つと、未参加の顧客に「商品を押しつけられそう」と敬遠されるおそれもあります。
金銭や景品といった特典でコミュニティへの登録者を増やす手法も、おすすめできません。そのような手法で登録者を増やしても、持続性やブランドへの熱量を期待できないことが多いためです。
また、成功しているコミュニティに共通しているのは、自発的な情報発信が生まれる設計になっていることです。交流の活発なコミュニティでは、常に「商品の意外な活用方法」「FAQ投稿」などのUGCが創出されています。
コミュニティにおける情報発信の多くは、実際に購入して利用した商品やサービスに対するファンによるものです。つまり、ほかの顧客にとって信頼性の高い「口コミ」が多いといえるため、コミュニティが活発であるほど、新規登録者も増えやすくなるでしょう。
なお、コミュニティマーケティングと類似している、ファンマーケティングやファンベースマーケティングに興味のある方は、以下の記事もご覧ください。
売らずに語る、語らずとも伝わるブランドへ

コミュニティマーケティングの目的は、ファン化した顧客が自然に自社ブランドを選び、集まってくる流れを作ることです。
コミュニティで顧客と交流を深め、熱心なファンへと育てると、次第にブランドや商品・サービスに興味を持ってもらえるようになり、販売数の増加へとつながります。
コミュニティは企業側が一方的に与える場所ではなく、ファンのブランドへの信頼が生む資産であることを再確認しましょう。
コミュニティマーケティングを実施する際は、スノーピークが2年かけて足場を整えたように、投資対効果(ROI)を性急に求めず、数年にわたる中長期的な視点でコミュニティの構築を進めることがポイントです。
スタート時の規模は小さくてもかまいません。少人数でも熱心なファンを集めて、ファン同士がコミュニケーションしやすい場所を少しずつ育てることが、成功のカギといえます。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
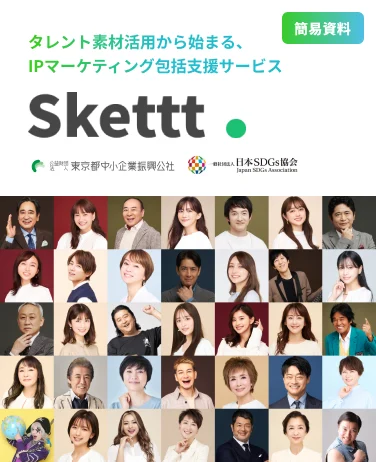
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag