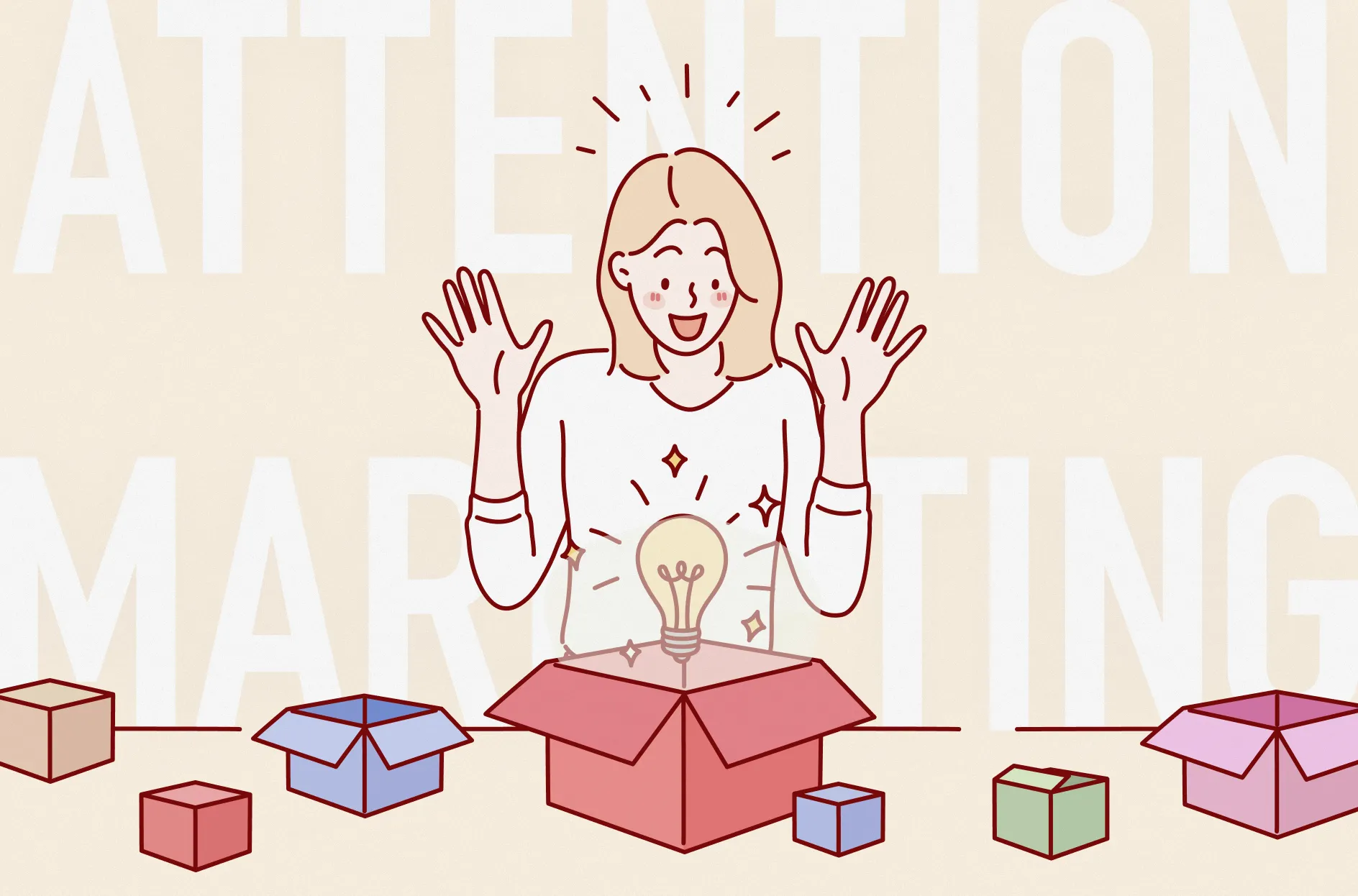マーケティング戦略
ファンベースマーケティングとは?ファンマーケティングとの違いや成功事例
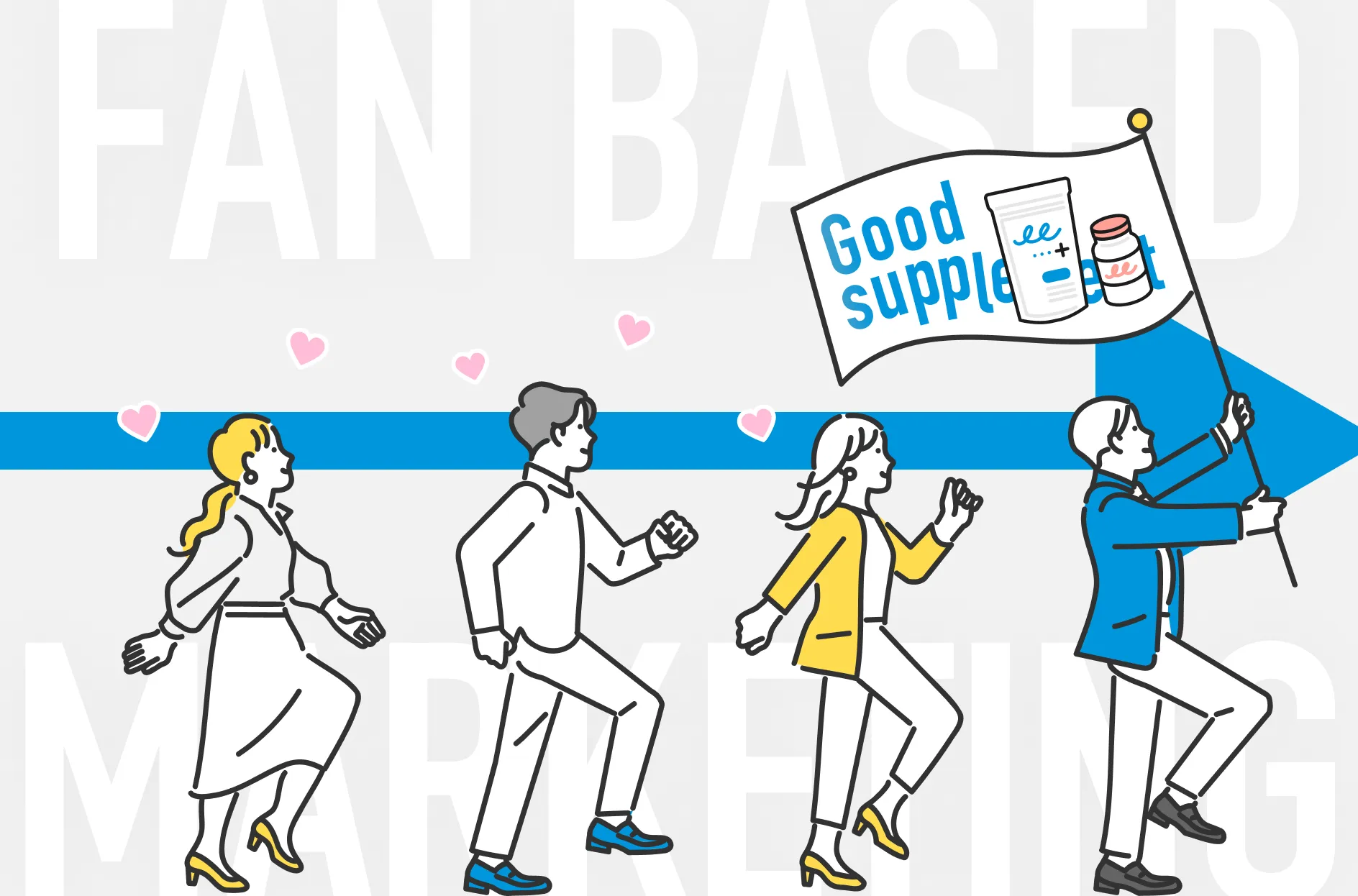
一時的なブームで終わらせず、長く愛されるブランドをつくるにはどうすればいいのでしょうか。近年は、熱量が高いファンとの関係性を深め、ともに成長していくアプローチに注目が集まっています。
本記事では、そんなファンベースマーケティングの考え方とその効果について紹介します。
- ファンベースマーケティングとは?
- ファンマーケティングとの違いは?
- なぜ今ファンベースマーケティングが注目されているのか?
- ファンベースマーケティングのメリット
- 成功事例から学ぶ「ファンベース」の実践法
- 実践ポイント:ファンベースマーケティングをどう取り入れるか?
- ファンと育つブランドが、未来のスタンダードに

タレント×マーケティングで
成果を最大化
ファンベースマーケティングとは?

ファンベースマーケティングは、クリエイティブ・ディレクターの佐藤尚之(さとなお)氏が提唱したマーケティングの考え方です。
佐藤氏は、情報があふれ広告が届きにくくなった現代において、「好き」という感情を企業と顧客の関係の中心に据えることが重要だと説いています。
また、「ファンは企業の基盤であり、好きという感情は信頼とつながりを生み、長期的な支持を可能にする」と述べています。
参照1:日経クロストレンド「改めて学ぶファンベース「さとなお集中講義」 漫画でスッキリ理解」
参照2:fanbase company「ファンベースとは」
このマーケティング手法は、単に新規顧客の獲得を目指すのではなく、すでにブランドや企業の理念を理解し、支持している既存のファンの信頼と熱量を重視します。
ファンの熱量を高めながら関係を深めていくことで、安定的な売上と事業価値の向上を目指すことが特徴です。
さらに、ファンとの関係は単なる売買にとどまらず、企業が大切にしている価値を理解し、それを周囲に広めてくれる存在として捉えることができます。
こうしたつながりが強まることで、企業とファンの間により深い信頼が育まれ、持続的な発展へとつながっていきます。
ファンマーケティングとの違いは?

「ファンベースマーケティング」とよく似た言葉に「ファンマーケティング」がありますが、この2つは目的やアプローチの面で異なります。
ファンマーケティングは、ブランドや商品に共感や愛着を持つファンの存在を軸に、新たなファンの獲得や認知の広がりを目指すマーケティング手法です。
SNSやイベントの実施、インフルエンサーの起用などを通じてファンの自発的な情報拡散を促し認知度を高め、購買行動に導くことに強みがあります。
一方でファンベースマーケティングは、すでに存在するファンとの関係性をより深く、持続的なものにしていくことを重視します。新規獲得よりも進化や共創、そして「継続的な支持の維持」に重きを置き、ファンとブランドの信頼関係をじっくり育てていくのが特徴です。
このように、ファンマーケティングが新規ユーザーの獲得を重視する施策だとすれば、ファンベースマーケティングは既存ファンとの関係深化を重視する長期戦略です。購買者ではなく、価値観を共有する仲間としてファンと向き合う姿勢が求められます。
なお、ファンマーケティングの概要や具体的な活用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
なぜ今ファンベースマーケティングが注目されているのか?

ファンベースマーケティングが近年注目を集めている背景には、いくつかの社会的・環境的な変化があります。
まず、SNSの浸透により、誰もが発信できる時代となり、情報量は爆発的に増加しました。その結果、企業の発信も他の情報に埋もれやすくなったのは事実でしょう。
ファンベースマーケティングの提唱者である佐藤氏は、この状況を「情報“砂の一粒”時代」と表現し、多様なコンテンツが溢れるなかで、企業が届けたいメッセージをユーザーに受け取ってもらうこと自体が、非常に難しくなっていると述べています。
参照:朝渋「「”ファンベース”は、ファンマーケティングやファンビジネスとは全く違う」 ~ 著者と語る朝渋読書会 佐藤 尚之さん ~」
現代は新規顧客に情報が届きにくい環境です。そうしたなかで注目されるのが、すでにブランドや企業に関心を持っているファンの存在です。
情報が届きにくい時代だからこそ、関心を寄せてくれているファンに向けて丁寧に情報を届け、関係性を深めていくアプローチが重要視されてきました。
また、日本全体の消費者人口が減少していることも見逃せません。新規顧客の母数が減るなかで、既存ファンのLTV(顧客生涯価値)を高める戦略が、企業の持続的成長にとって欠かせないテーマなのです。
Z世代やミレニアル世代を中心とした価値観の変化も重要です。推し活や応援消費といった「好き」を起点とした行動が広がるなかで、ファンとともに価値を共有し、共創するスタンスがブランド支持の鍵となりました。
推し活マーケティングの詳細については、別記事で詳しく解説しています。
ファンベースマーケティングのメリット

ファンベースマーケティングに成功すれば、一時的なキャンペーンに頼らずとも、ファンの継続的な支持によって売上やブランド価値を安定的に伸ばし続けることが可能です。なかでも注目したいのは、長期的な売上の安定と信頼関係の構築です。
熱量の高いファンは、一度購入して終わるのではなく、ブランドに共感し、継続的に商品やサービスを支持してくれる存在です。彼らは売上の下支えとなるだけでなく、企業のメッセージや理念を自発的に広めてくれる力を持っています。
キャンペーンによる短期的な反響とは異なり、安定した支持を得られる点が、ファンベース戦略の最大の魅力といえるでしょう。
また、ファンとの対話を通じて得られるVOC(顧客の声)は、貴重なヒントの宝庫です。ファンの意見をもとに商品開発やプロモーションの方向性を設計することで、よりニーズに合ったサービスの提供が可能になるでしょう。
これは単なる市場調査ではなく、ブランドに対する共感をベースにしたリアルなインサイトといえます。
ファンとの関係性を強化することで、ブランドロイヤリティの向上も期待できます。ロイヤルファンによる積極的な発信は、他の消費者の関心を引くきっかけにもなり、新たな顧客の獲得にもつながるでしょう。
こうしたファンの声を企業活動に活かす仕組みが、企業の成長エンジンとなっていくのです。
成功事例から学ぶ「ファンベース」の実践法

ファンベースの考え方を実践している企業の成功例を3つ紹介します。それぞれの事例に共通するのは、「売る」よりも「信頼される」姿勢を重視し、ファンとの関係づくりに力を注いでいる点です。
サンリオ:推し文化との共鳴と共創戦略
サンリオは、キャラクター人気投票やSNSを活用し、ファンが自らの推しを応援する文化を育ててきました。数多くのキャラクター展開によって、多様な「好き」を尊重し、ファンの愛着に寄り添いながら、長期的に応援し続けられる仕組みを構築しています。
たとえばアニメキャラクターやアパレルブランドとのコラボグッズの販売や、ファンとの距離を縮めるサンリオピューロランドの運営などは、まさにファンベースマーケティングの実践といえるでしょう。
参照1:プリズマティクス「サンリオマーケ×濱野幸介【wow!シリーズ】対談前編「これは、ナルホド、凄いことだなと、本当に実感しています」
参照2:サンリオオンラインショップ
サンリオのマーケティング戦略については、こちらの記事にてよりくわしく解説しています。
アットコスメ:年間100万人以上が参加するライブ配信でファンと直接対話
コスメ・美容情報サイトのアットコスメは、「教えて!美容部員さん ライブショッピング」というライブ配信を通じて、年間累計100万人以上が視聴する規模のファンベースマーケティングを実施しています。
美容部員が商品の使い方やケア方法を詳しく解説し、視聴者からの質問にリアルタイムで応答。双方向コミュニケーションにより、ユーザーの声を丁寧に反映しながら、信頼関係を築いています。
さらに、配信を通じて商品をECサイトに直接誘導する仕組みも整えており、ファンとの継続的な関係構築と購買促進を両立させています。
参照1:A8.net「今注目のファンベースマーケティングとは?成功事例や実践方法をご紹介」
参照2:インプレス「年累計100万人以上がライブ配信を視聴! @cosmeが実践するユーザーとのコミュニケーション方法とは」
コメダ珈琲店:語りたくなる“居場所”をつくるファンコミュニティ
コメダ珈琲店は、「さんかく屋根の下」というファンコミュニティサイトを立ち上げ、ファン同士が語り合えるオンラインの居場所を提供しています。
サイトのオープンからわずか1週間で7,000人もの登録者が集まり、その後も順調に増え続けているこのプラットフォームは、フォトコンテストや投稿機能を通じて、ファンの能動的な参加が自然と引き出される仕組みが特徴です。
参照:Yahoo!ニュース「喫茶店「コメダ珈琲店」のファン交流サイトがオープン! 業界トップの新しい“常連づくり”の形とは?」
リアル店舗の居心地の良さと、デジタル上での交流が好循環を生み、ファン同士の交流を促進する場となりました。顧客が「好き」を発信できる場を整えることで、ファンコミュニティとして機能しているといえるでしょう。
参照1:BE PLANNING「今注目のファンベースマーケティングとは?事例や成功のポイント」
参照2:さんかく屋根の下
実践ポイント:ファンベースマーケティングをどう取り入れるか?

ファンベースマーケティングを導入するには、短期的な売上ではなく信頼され続けるブランドを目指す視点が欠かせません。特に重要なのが、「売る」ことよりも「共感される・語られる」プロセスを設計することです。
まずマーケティングの出発点として、売上やアクション率、顧客単価といった定量データだけに頼るのではなく、ファンの声や投稿内容など、定性情報を丁寧に拾い上げる姿勢が求められます。
SNSのコメントやイベント参加者の感想には、ブランドとの深い関わり方のヒントが隠れているでしょう。
社内にもファン視点の文化を浸透させることが重要です。現場の担当者だけでなく、経営層も含めてファンの声を共有し、意思決定に反映させることで、ブレないブランド体験が提供できるようになります。
また、ファンが自然と語りたくなるような体験設計も欠かせません。
ただ商品を届けるだけでなく、自身の体験や価値観と重ね合わせられるようなストーリーやコミュニティづくり、驚きや共感を生む演出を通じて、モノ以上の価値を求める顧客との関係性を築くことが鍵となります。
ファンと育つブランドが、未来のスタンダードに

ファンベースマーケティングは単なる戦略ではなく、企業の姿勢や価値観に根ざした哲学に近い考え方です。効率や即効性だけを追うのではなく、ファンとの対話や信頼関係の構築を重ねながら、長く愛されるブランドを育てていくことが求められます。
一過性のブームに頼らず継続的な支持を得るためには、企業の理念や取り組みを丁寧に伝え、共感を生む姿勢が不可欠です。顧客は「モノを買う人」ではなく、「ブランドと一緒に歩む仲間」へと変化しています。
ファンとともに育ち、時代に求められる価値を生み出すブランドこそが、これからの社会にとってスタンダードになっていくはずです。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
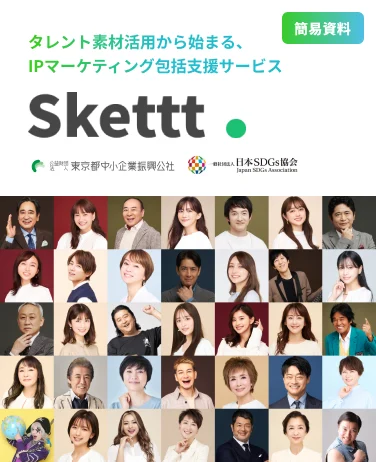
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag