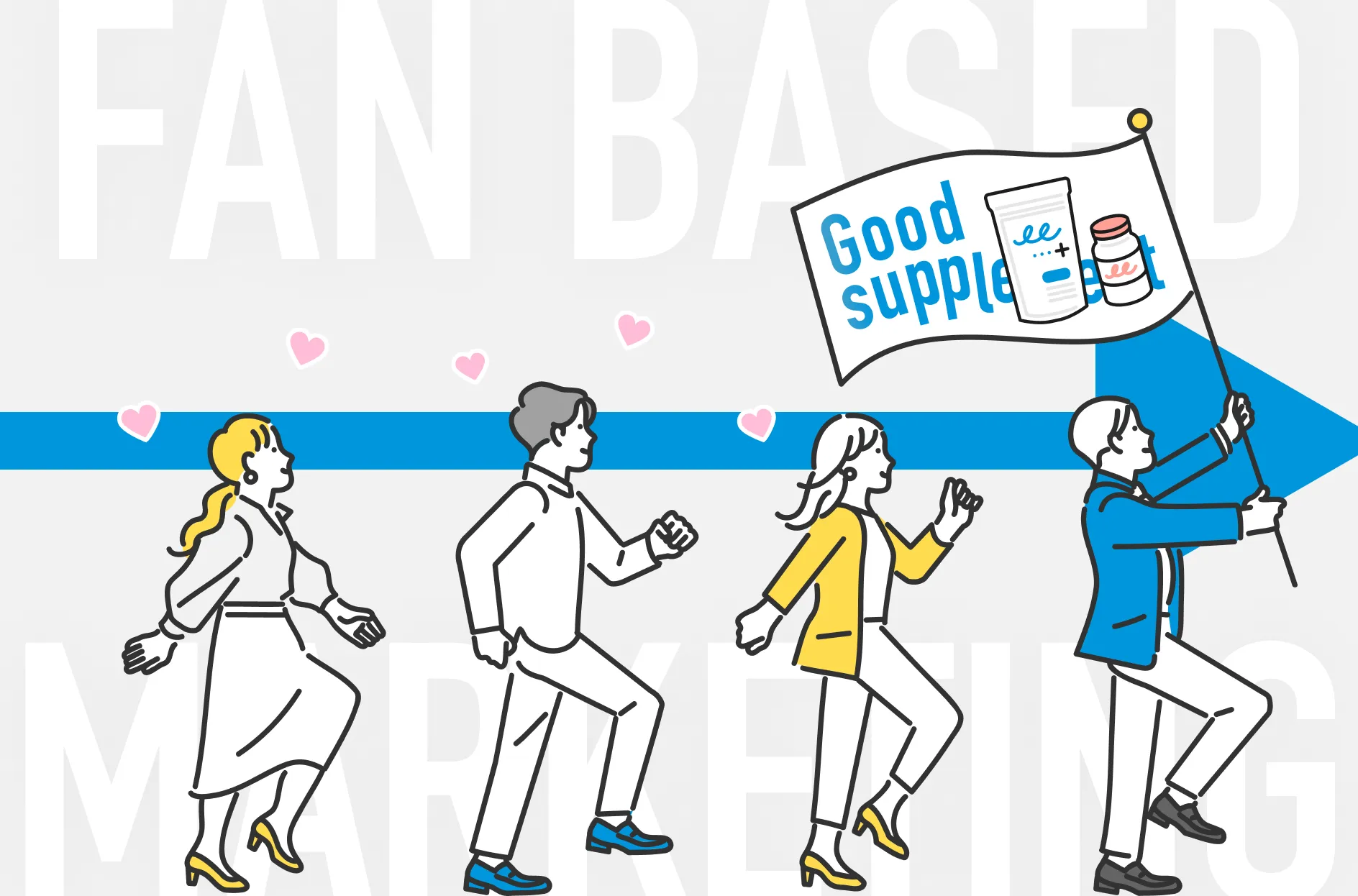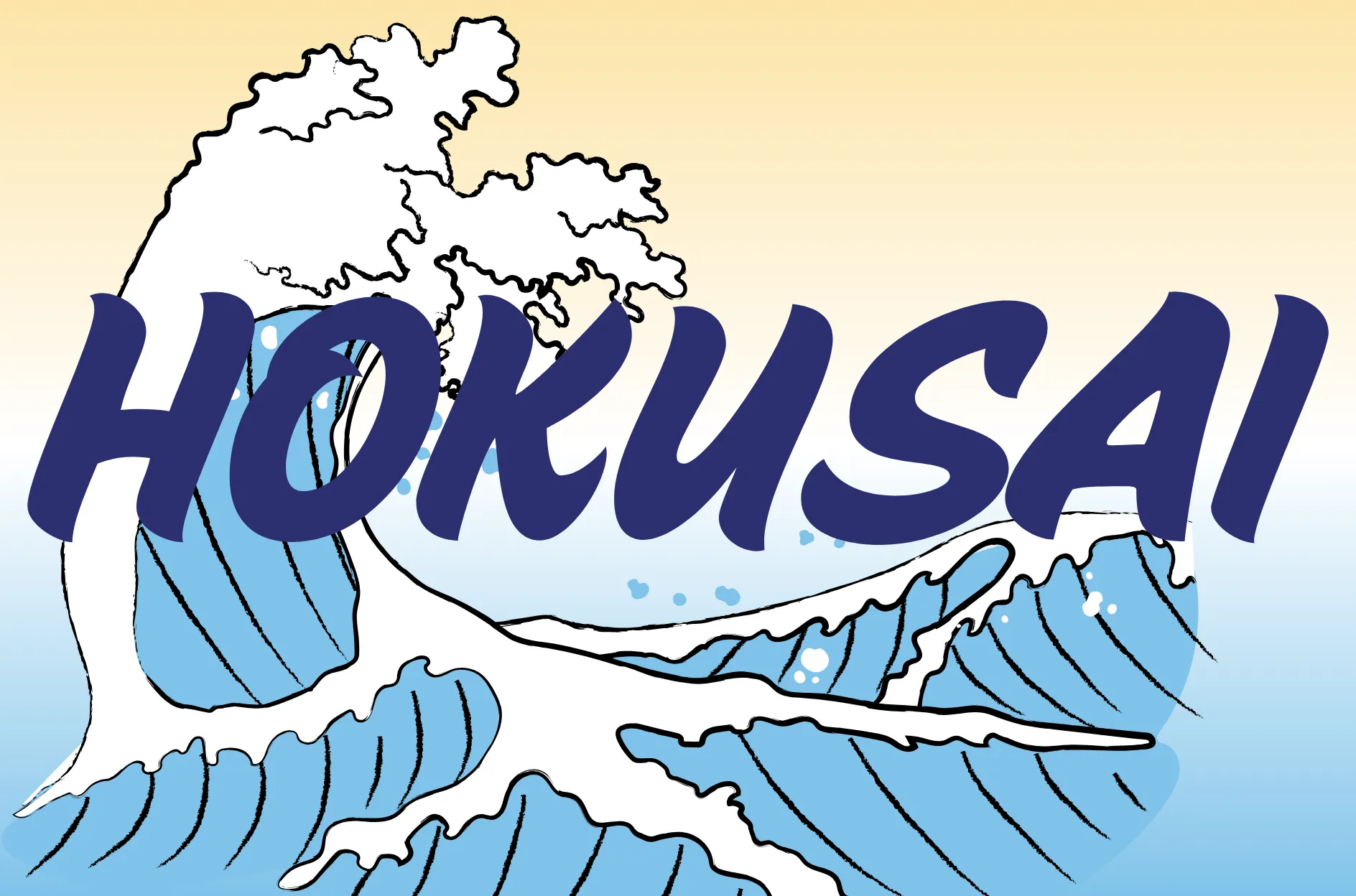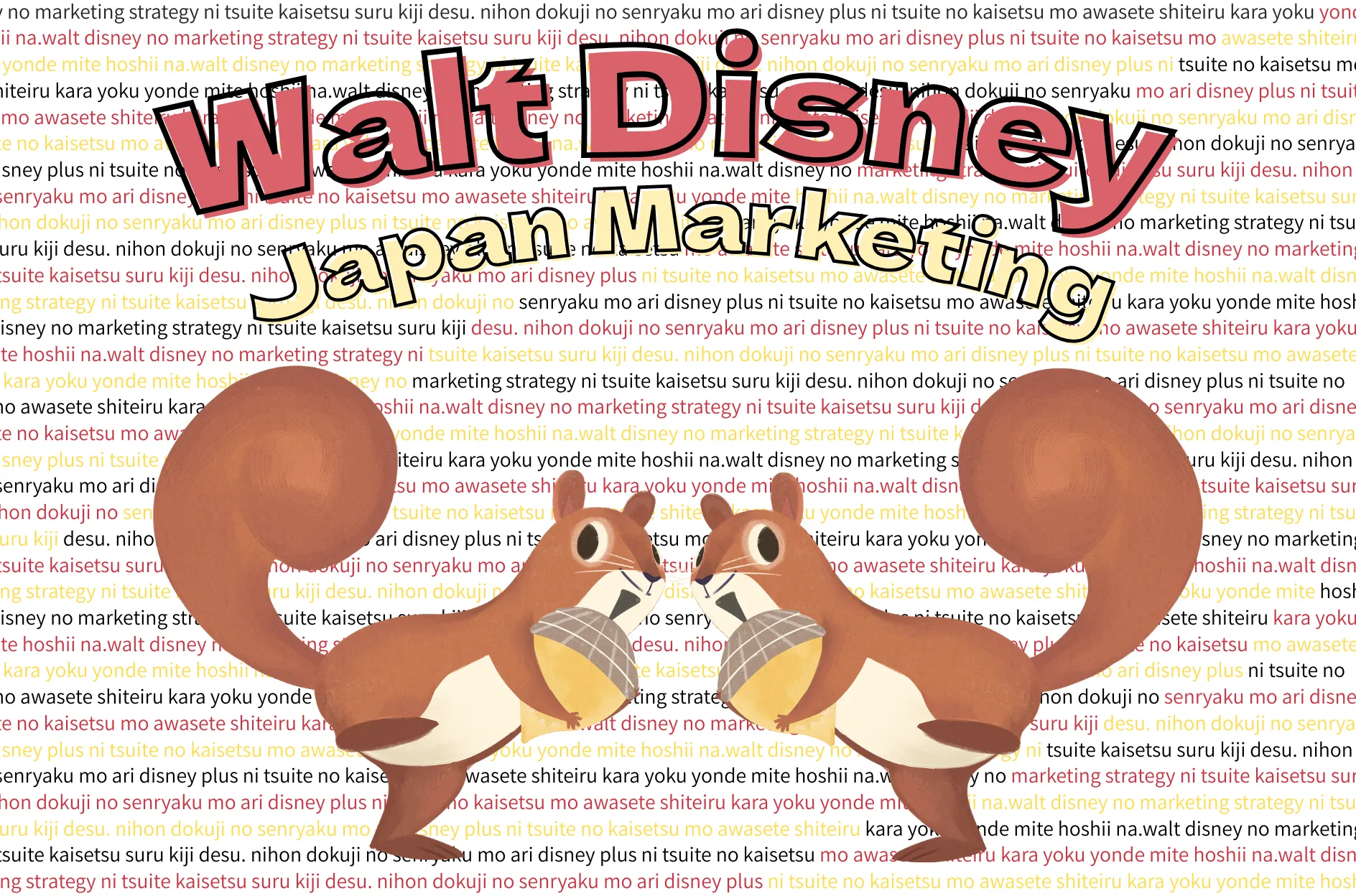IP活用
ラブブだけじゃない!中国発トイブランドPOP MART(ポップマート)のマーケティング戦略

今や知らない人はいないのではないかというほどの社会現象を巻き起こしたラブブ(Labubu)。2025年のトレンドを象徴するひとつであることは間違いないですが、昨年にはYahoo!検索大賞2024のネクストブレイク商品部門に選出されており、期待どおりの結果といえるかもしれません。
香港出身のアーティスト、カシン・ローン(Kasing Lung)氏の生み出したキャラクターであるラブブをヒットに導いたのは、中国発のトイブランドPOP MART(ポップマート)。キャラクターIP大国と呼ばれて久しい日本の立場が危ぶまれるほどの急成長を遂げる同社の時価総額は、現時点でサンリオの4倍といわれています。
今回はそんなラブブ、そしてPOP MARTのキャラクターマーケティング戦略をお伝えしていきたいと思います。
- POP MARTとは?ブラインドボックス文化を広めた立役者
- ラブブ(Labubu)とは?古参IPをヒット作に押し上げたのはBLACKPINKのLISA?
- POP MARTのマーケティング戦略
- グローバル展開と日本のサンリオとの比較
- POP MARTの成功が示す「IPマーケティングの未来」
- ラブブが教えてくれる、“好き”が経済を動かす時代

タレント×マーケティングで
成果を最大化
POP MARTとは?ブラインドボックス文化を広めた立役者

アートトイ領域における中国大手の泡泡瑪特国際集団(Pop Mart International Group、以下POP MART)は2010年創業。2015年に日本発のアートトイ「Sonny Angel(ソニーエンジェル)」の取り扱いを開始し、大きな利益を生んだことが転機となって、その後大きな飛躍を遂げます。
Sonny Angelは中身の見えないブラインドボックスに入ったミニフィギュアを中心に展開しているIP。これがコレクター心をくすぐり、複数買いをしたり、ファン同士で交換したりすることで話題性を広げていったのです。

そもそもアートトイとは、その名のとおりアートの性質とおもちゃの性質を持った、デザイン性と品質の高いコレクタブルトイのこと。デザイナーが独自にクリエイトすることから、デザイナーズトイとも呼ばれています。
POP MARTは多くの新進気鋭のデザイナー、クリエイターとタッグを組み、さまざまなアートトイを創出。
ラブブ以外にもクライベイビー(Crybaby)、モリー(MOLLY)、スカルパンダ(SKULLPANDA)、ディムー(DIMOO)といった世界的人気を誇るIPを多数抱えており、いずれもブラインドボックスで販売することで、ユニークな購買体験を生み出しました。
(▲クライベイビー)
(▲スカルパンダ)
くわしくは後述しますが、ブラインドボックスによって得られる効果は、ただ一時の話題づくりとなる以上の価値があるといえるでしょう。
2025年8月19日にPOP MARTが発表した同年上期の純利益は、前年比396.5%増の45億7,000万元(約960億円)であり、GUCCIなどハイブランドを数多く擁するフランスのケリング社の4億7,400万ユーロ(約820億円)を上回っています。
参照:36Kr Japan「中国POP MART、“LABUBU旋風”で1〜6月純利益5倍 時価総額8兆円で過去最高」
ケリングがしばらく不振続きなのも知られるところではありますが、それでもPOP MARTが世界的に大きく躍進していることはわかるでしょう。
ラブブ(Labubu)とは?古参IPをヒット作に押し上げたのはBLACKPINKのLISA?
ラブブは先述のとおり、香港出身のアーティスト、カシン・ローン(Kasing Lung)氏が生み出したキャラクターです。Yahoo!検索大賞2024のネクストブレイク商品部門に選出され、事実、同年には爆発的なヒットとなり、社会現象になりました。
ラブブの初登場は、カシン・ローンさんが北欧神話に強い影響を受けて2015年に発表した絵本『the Monsters(ザ・モンスターズ)』シリーズ。
ラブブ以外にリーダーのジモモ(Zimomo)や長いまつ毛が特徴的なモココ(Mokoko)、ラブブのボーイフレンドであるタイココ(Tycoco)など、さまざまなキャラクターが登場します。
いずれもグッズ展開されていますが、エルフ語で「特別」という意味を持つモココはその名のとおり特別レアな存在で、しばらくPOP MART公式テーマパーク「POP LAND」内でしか入手できませんでした。
手に入りにくいことで飢餓感を煽り、それがまた所有欲につながったことでしょう。
『the Monsters』シリーズは香港・台湾を中心に活動するアートブランドHOW2WORKよりフィギュア化されてリリース。ラブブは特に人気を集め、当時すでに、現在の一大ブームを予期させるような小さな芽が萌え出ていたといえるかもしれません。
その後フィギュアだけでなく、昨今街中でよく見かけるキーチャームを含む大小さまざまなぬいぐるみ、雑貨といったグッズを展開。数多くのIPを抱えるPOP MARTの中でも象徴的な存在として、認知度、人気ともに大きく成長していきます。
とはいえ、2015年に発表されて2024年ごろにブレイクしたことを考えると、意外にもラブブはリリース直後からすぐに現在の立ち位置に辿り着いたわけではありません。
ブームの火付け役となったのはBLACKPINKのリサさん。2024年に彼女がSNS上で自身のバッグにラブブを付けて投稿したことが話題になり、急速に広がったといわれています。
もともと彼女はPOP MARTのファンであることでも知られており、この投稿以外にもラブブの特大ぬいぐるみと一緒に写る写真や、ラブブをモチーフにした衣装を纏った写真も投稿されています。
ほかにもデュア・リパさんやレディー・ガガさん、リアーナさん、マーク・ジェイコブスさんといった錚々たるセレブたちがこぞってファッションに取り入れたことで、トレンドに敏感なアーリーアダプターの間で火がつきはじめたのです。
ラブブを持つことは一種のステータスのように認識されはじめ、いち早く手に入れたユーザーの多くはやはりSNS上で発信します。先述のとおりブラインドボックスで提供されるという仕様もSNSと相性が良く、開封してリアクションを見せる“開封動画”も波及的に広まりバイラル化しました。
そして現在の社会現象に至るわけですが、もとを辿れば、そもそもセレブたちがラブブを見つけるきっかけになったのは、POP MARTの戦略的なグローバル展開にあるといってもよいでしょう。
同社が海外展開をスタートさせたのは2018年ですが、2024年にベトナム、インドネシア、フィリピン、イタリア、スペインに1号店をオープンさせるなど加速度的に注力しはじめたのです。これにより海外セレブの目に留まりやすい地盤が整えられたと考えられます。
参照:東洋経済「中国発ラブブ「2027年にハローキティ超え」がおこがましすぎる理由。《狂乱相場崩壊?》“転売ヤー”の阿鼻叫喚」
POP MARTのグローバル戦略については後述しますが、一方で日本では2020年に日本限定商品の「LABUBU 招き猫」が販売され、2025年にはユニクロのグラフィックTシャツブランドUTとのコラボアイテムを数型発表。
参照:ロフト「『POP MART@渋谷ロフト』期間限定オープン!」
後者に関しては世界的ムーブメントの渦中だったことから、発売直後に完売してしまい、再販売されることになりました。年内に秋冬対応のスウェット地を用いた別アイテムの発売も発表されています。
POP MARTのマーケティング戦略

さて、いよいよPOP MARTが実際に行っているマーケティング施策について触れていきます。
マルチブランド展開による分散型IP展開
同じ領域の中で複数のブランドを展開することをマルチブランド展開といいますが、POP MARTはかねてよりこれを実施している点が第一の特徴といえます。
アーティストと独占契約したIPと自社開発したIPは合わせておよそ100種におよび、先述のとおりラブブを含めたthe Monstersシリーズのほかにクライベイビー(Crybaby)、スカルパンダ(SKULLPANDA)、モリー(MOLLY)、ディムー(DIMOO)など多くの人気IPを保有。
(▲ディムー)
今挙げたIPはいずれも異なるアーティストの手によって生み出されたもので、クライベイビーはタイ出身のモリー(Molly)さん、スカルパンダは中国出身の同名デザイナー スカルパンダ(ション・ミャオ(熊喵)とも)さん、モリーは香港出身のケニー・ウォン(Kenny Wong)さん、ディムーは中国出身のアヤン・ドンさんが手がけています。
それぞれストーリーやメッセージ性も異なるため、キャラクターのビジュアルだけでなく背景もふまえたうえで、共感性をもってファンを着実に増やしているのです。
タイプの違うIP、つまりファン目線でいうと常に新しい“推し”を発信しつづけることで、多くのユーザーにリーチすることが可能となるでしょう。
またIPホルダーの目線でいうと、マルチブランド戦略はひとつのIPに依存しないというメリットもあります。もしなんらかの理由で人気の高いIPの売り上げが減少してしまっても、他のIPにユーザーの関心が分散すれば大きなダメージは被りません。
また、トレンドは常に移り変わっていくものであり、同時に繰り返すものでもあるため、複数のIPを展開させていれば、一時的に落ち着いたIPもまたいずれ第二次、第三次ブームを起こす可能性を秘めています。
何度も話題を作ることができれば、いずれそれはトレンドを超えて普遍的に愛されるキャラクターとなりえるでしょう。
コレクタブル戦略でファンダムを形成
繰り返しになりますが、POP MARTの特徴はその人気アイテムのほとんどをブラインドボックスで提供しているという点。
これにより「ガチャ体験」を拡張させ、なにが出るかわからないというワクワク感を与えられるのはもちろん、欲しいものを引き当てられなかったり、重複してしまったりすることによって収集欲を刺激します。
ブラインドボックスはピース(単品)購入だけでなく、アソート(セット)購入もできるため、どうしても欲しいものがあるユーザーや全コレクションをコンプリートしたいユーザーは複数個、あるいは“大人買い”することで、売り上げの増加も見込めるでしょう。
いわゆるオフラインの体験に付加価値を見出す「コト消費」は、コロナ禍に制限されたこともあって今現在もなお多くの需要が感じられますが、POP MARTはオンライン上においても購入体験を強化。
2025年9月より「POP NOW」という、画面上でボックスの中身を確認することができるサービスを搭載したのです。
これを用いると、選択したボックスを5分間キープでき(ほかのユーザーが確保しているボックスも5分経てば購入できる)、その箱に入っていない種類を知ることができるヒント機能などを利用して中身を確認したうえで購入することができます。
参照:POP MART公式オンラインショップ「Welcome to POP NOW!」
また、日本限定商品などローカライズアイテムも積極的に販売。希少性の原理により、手に入りにくいことで高い価値を生み出し、より購買欲求を引き出しています。
UGC創出を促すSNSマーケティング
そもそもこのたびのPOP MARTバズは、先述のセレブたちがラブブのチャームを自身のバッグにつけてファッションに取り入れたことが発端。それを真似し、ハイブランドのバッグにつけて写真を撮り、SNSに投稿するのが一種のステータスとして流行りはじめました。
結果、ラブブを所有していることが羨望の対象となり、多くの人々を扇動します。インフルエンサーマーケティングなどのように企業が影響力のある人に依頼して話題づくりをしたわけではなく、自発的なUGCの創出に成功したのです。
ブラインドボックスの特性を生かした開封動画もシェアされやすく、インフルエンサーを含む多くの方がSNS上に投稿しています。これによりレイトマジョリティ層にも広まったといえるでしょう。
またPOP MARTのチャームは1箱2,000円前後と、Z世代など若年層も手の届きやすい価格帯ですが、この世代は「ぬい活」や「推し活」文化が盛んなことも知られています。
ぬい活とは、お気に入りのぬいぐるみを持ち歩いて写真を撮ったり、着せ替えたり、ぬいぐるみを通じて行う活動のこと。推し活とは、応援しているアイドルや俳優、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したりするさまざまな活動のこと。
推し活マーケティングについてくわしくはこちらの記事をご覧ください。
実際、着せ替えやペインティングによって自己流にカスタマイズしたラブブをSNS上に公開するファンもいるくらい、POP MARTのアイテムのほとんどはこれらふたつのカルチャーとの親和性が非常に高いといえ、それもまたUGC創出の手助けとなったことでしょう。
リアル×デジタルの体験の融合
POP MARTの実店舗の多くは、保有IPの巨大オブジェが飾られていたり、常設のフォトスポットがあったり、世界観を前面に押し出した没入感のある内装が特徴。購入予定がなくても、つい入店したくなるような特別なオフライン体験を提供してくれます。
また空港などには「ROBO SHOP」というPOP MARTのアイテムが購入できる自動販売機も設置されており、フライトまでの待ち時間などに気軽に立ち寄ることができ、これもまたPOP MARTを身近に感じさせる秘訣といえそうです。

(▲ロンドンのPOP MARTのROBO SHOP(出典:POP MART公式サイト))
一方で先述のとおり、公式アプリをはじめオンラインショッピング体験も充実。来店の難しいユーザーや遠方のユーザーを楽しませる仕掛けが施されています。
また2024年にはNFTを試験的に提供開始。現在はキーチャームや雑貨などファッションやインテリアに取り入れられるアイテムが人気ですが、いずれ物理的に入手するだけではなく、デジタル領域でそのクリエイティビティを楽しむ時代がやってくるかもしれません。
セブチやXG・sacai、他ブランドとのコラボによる新規ファンの取り込み
POP MARTは先述のユニクロだけでなく、他企業・ブランドとのコラボも積極的に行っています。
ラブブだけに絞って過去に実施された有名ブランドを挙げても、ユニクロ、コカ・コーラ、SFイラストレーターの横山宏さんが生み出した「Ma.K.(マネーシンクリーガー)」など、そのジャンルは多岐に渡ります。
最近では、K-POPボーイズグループSEVENTEEN(セブンティーン/愛称は「セブチ」)とファレル・ウィリアムスが設立したオークションプラットフォーム「JOOPITER(ジュピター)」とアパレルブランドのsacai(サカイ)がコラボアイテムを発表した中に、限定エディションのラブブのフィギュアが登場したことも話題になりました(2025年6月)。

また同年11月には日本発グローバルグループXGとスカルパンダのコラボも日本限定で販売開始。

XGとそのファンダム「ALPHAZ(アルファズ)」を象徴するオオカミからインスピレーションを得たというデザインはY3Kを想起させるような近未来的な印象もあり、瞳の中にはALPHAZのマークが入っているというこだわりっぷりで、メンバーも大喜びだったようです。
そもそもメンバー全員がスカルパンダのファン。過去には全員で一緒に購入してアンボクシング(開封)したこともあるらしく、その際は白熱のじゃんけん大会によって、どれを選ぶか決めたそうです。
このように複数の領域をブリッジしてコラボすることは、従来のPOP MARTファン以外の層にも届きやすくなるということ。より多くの方にリーチすることで、そのIPやコンテンツは一層マス化を目指すことができるようになるでしょう。
また人気の高いアーティストやブランドとコラボすることで、さらにPOP MARTのブランディングも強化することができます。確固たる地位を築くことで、新規ファンを取り込むだけでなくファンダムの醸成にもつながるのではないでしょうか。
グローバル展開と日本のサンリオとの比較

2025年10月現在、POP MARTは日本国内だけでもすでに10店舗以上の直営店を展開。さらに新店舗開発を加速させています。
今後、主要都市にその世界観を存分に演出できる大型店舗の出店計画もあり、ますます存在感を発揮することでしょう。
世界に目を向けると、30か国に550店舗以上の直営店を抱えており、グローバル展開に注力していることがわかります。
参照:engage「POP MART JAPAN求人ページ」
2025年8月に発表された同年上半期の売上高は139億元(約2,860億円)で、前年同期比3倍。
そのうちラブブをふくむthe Monstersシリーズは48億1,000万元(約1,000億円)と全体の約35%程度を占め、同シリーズがこのたびの業績上昇を押し上げたことがわかると同時に、ほかのIPも負けじと貢献していることがわかります。
さらに昨年の時点では時価総額がサンリオに追いつくかどうか注目されていたのに、今や4倍と遥かに差をつけています。
参照:WWD「「ポップマート」大阪・難波に国内最大店 巨大ラブブがお出迎え」
2027年ごろにはラブブ人気はハローキティのそれを超えるという見方もありますが、後者は2024年に50周年を迎え、“ご長寿IP”といえるほど長い間世代を超えて愛されてきたことも強みになっており、今後匹敵するほどアクティブユーザーの人口が増えても「肩を並べる」という表現のほうが適切かもしれません。
なおハローキティのほかにも多様なIPを擁するサンリオのマーケティング戦略については、こちらの記事をご覧ください。新興ブランドとはまた異なる、普遍的なキャラクターマーケティングの手法が見られます。
ただ語弊を招きたくないのは、そもそもPOP MARTとサンリオは競合となりえる存在でありながら、コラボアイテムを発表するなど、むしろ互いのブランド力を拡大させる同士のような関係性であること。
Sweet, edgy, and unmistakably 𝐒𝐊𝐔𝐋𝐋𝐏𝐀𝐍𝐃𝐀. With 𝐊𝐔𝐑𝐎𝐌𝐈 and 𝐌𝐘 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐃𝐘, two moods emerge—dark charm and soft warmth, all from the same spirit. 🖤💗
— POP MART (@POPMARTGlobal) December 19, 2025
𝐒𝐊𝐔𝐋𝐋𝐏𝐀𝐍𝐃𝐀 × 𝐊𝐔𝐑𝐎𝐌𝐈 𝐏𝐥𝐮𝐬𝐡
𝐒𝐊𝐔𝐋𝐋𝐏𝐀𝐍𝐃𝐀 × 𝐌𝐘 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐃𝐘 𝐏𝐥𝐮𝐬𝐡… pic.twitter.com/TpQjhdOGsT
2025年12月19日にはPOP MARTの公式SNSが、上述のとおりスカルパンダとサンリオのキャラクターであるマイメロディ・クロミのコラボを発表。同年12月26日にリリースされることがわかっています。
(なお、同コラボはこれまで長らく期待されてきたもので、マイメロディやクロミの着ぐるみ服を別途入手し、手持ちのスカルパンダに着せて“コラボ風”デザインを楽しむファンも多くいました)
サンリオが自社キャラクターの個性に寄り添ってそれぞれに合った他社コラボを積極的に行っているのは前述の別記事で触れているところですが、POP MARTもまた他社とのコラボを推進させることでキャラクタープラットフォームとしての位置を確立させています。
サンリオ以外にもディズニーやワーナー、パワーパフガールズなど、それぞれ世界的な人気を誇るIPホルダーとコラボすることで、自社ブランドを強固にし、その信頼感でもって世界中の新規ユーザーへのリーチを容易くしているのです。
ラブブブームの火付け役がBLACKPINKのリサさんといわれているのは前述のとおりですが、香港生まれでオランダ在住のカシン・ローンさんが生み出したキャラクターをK-POPグループのタイ出身メンバーが身につけるとは、なんともグローバリゼーションの体現といった風情でしょう。
POP MARTの成功が示す「IPマーケティングの未来」

POP MARTの成功の秘訣は、保有しているIPの魅力もさることながら、それらをただの一過性のヒット商品としてではなく文化として推し広めたことにあるでしょう。
手に入れることがゴールではなく、開封する様子やカスタマイズする様子を撮影してSNS上に投稿してユーザーコミュニティの交流を活性化させたり、バッグなどに付けてファッションの一部として楽しんだり、体験を作ることに成功しているのです。
ちなみにラブブが世界的に流行しはじめたのは2024年ですが、2023年の時点ですでにバッグにぬいぐるみをつけるスタイルが浸透しはじめていたのをファッションメディアなどから観測できます。
ぬい活の流れも汲んだうえで広まったカルチャーだったのかもしれませんが、最初は1点お気に入りのそれをつけるのが主流だったのが、Y2Kブームや平成レトロブームも相まって当時の女子高生がスクールバッグにしていたように、ぬいぐるみ以外のチャームも加えて「じゃらづけ」するのが一般的になり、その渦中にラブブが注目されたといえるでしょう。
このようにファッション文脈との親和性を高めたことで、トレンドに敏感な層から火がつき、乗り遅れたくないという深層心理を突いてブームが拡大していったのです。
結果、2025年の春ごろにはPOP MARTの公式サイトはアクセス過多により一時的にダウンし、正常な運営ができなくなったため約1か月間新商品の販売もストップ。
供給が追いつかずプレミアム価格での転売も促進することになり、偽装品も出回り、残念ながら市場は健全性を欠くようになりました。
しかしそんなブーム真っ只中の同年6月、POP MARTは突如ラブブの大量投入を決行します。これにより転売品は大きく値崩れし、転売ヤーに制裁が加えられたわけですが、当然ながらPOP MARTも株価暴落という傷を負いました。
ただこの事態を悲観視してはおらず、自らの手で正常な状態に戻したと判断できるでしょう。というのも、その後も販売可能な数だけ随時再入荷を繰り返されていたラブブは、10月にはついに予約販売を始めたのです。
本当に欲しいと思っている人に欲しいと思っている数が届けられるように、供給バランスを整えたと捉えることができます。
バブルはいずれ弾けるものです。ラブブもこれだけ大きく社会を動かしたのであれば、いずれブームは終焉を迎えるでしょう。ただその後も普遍的な人気を誇るキャラクターの座につけるかどうかは、ブランディングとユーザー体験にかかっているのではないでしょうか。
ユーザーのコレクション欲とSNS文化を掛け合わせたことでPOP MARTは大きく飛躍しましたが、多くのファンを獲得したあと、その熱量を中心に据えて適切に需要に応える販売方法に切り替えたことで、継続的なIP育成を見据えていることがうかがえます。
それはIPの資産価値を高めるだけでなく、ブランドひいては企業全体の資産価値を高めることにつながるでしょう。
ラブブが教えてくれる、“好き”が経済を動かす時代

ラブブ、およびPOP MARTの成功はファン主体にマーケティングを展開する現代の象徴といえるかもしれません。
ファン主体のマーケティング=ファンベースマーケティングについて、くわしくは以下の記事をご覧ください。
一方的に魅力的なIPを押し売りしてトレンドを作ることもできますが、ユーザー体験による共感を設計することこそがトレンドの契機となりうる時代だといえます。
キャラクターIPは今後のビジネス領域においても欠かせないものであることは間違いないといえ、ますますマーケティング戦略との融合が加速していくことでしょう。次はどんな体験が待っているのか、一IPファンとしても見守っていきたいところです。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
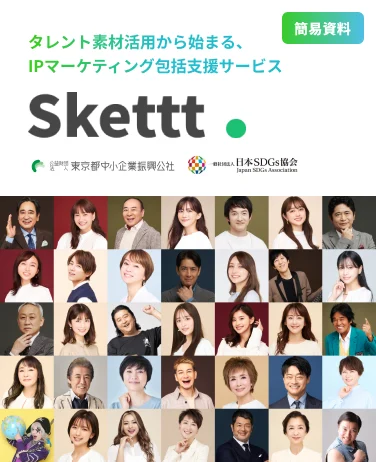
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag