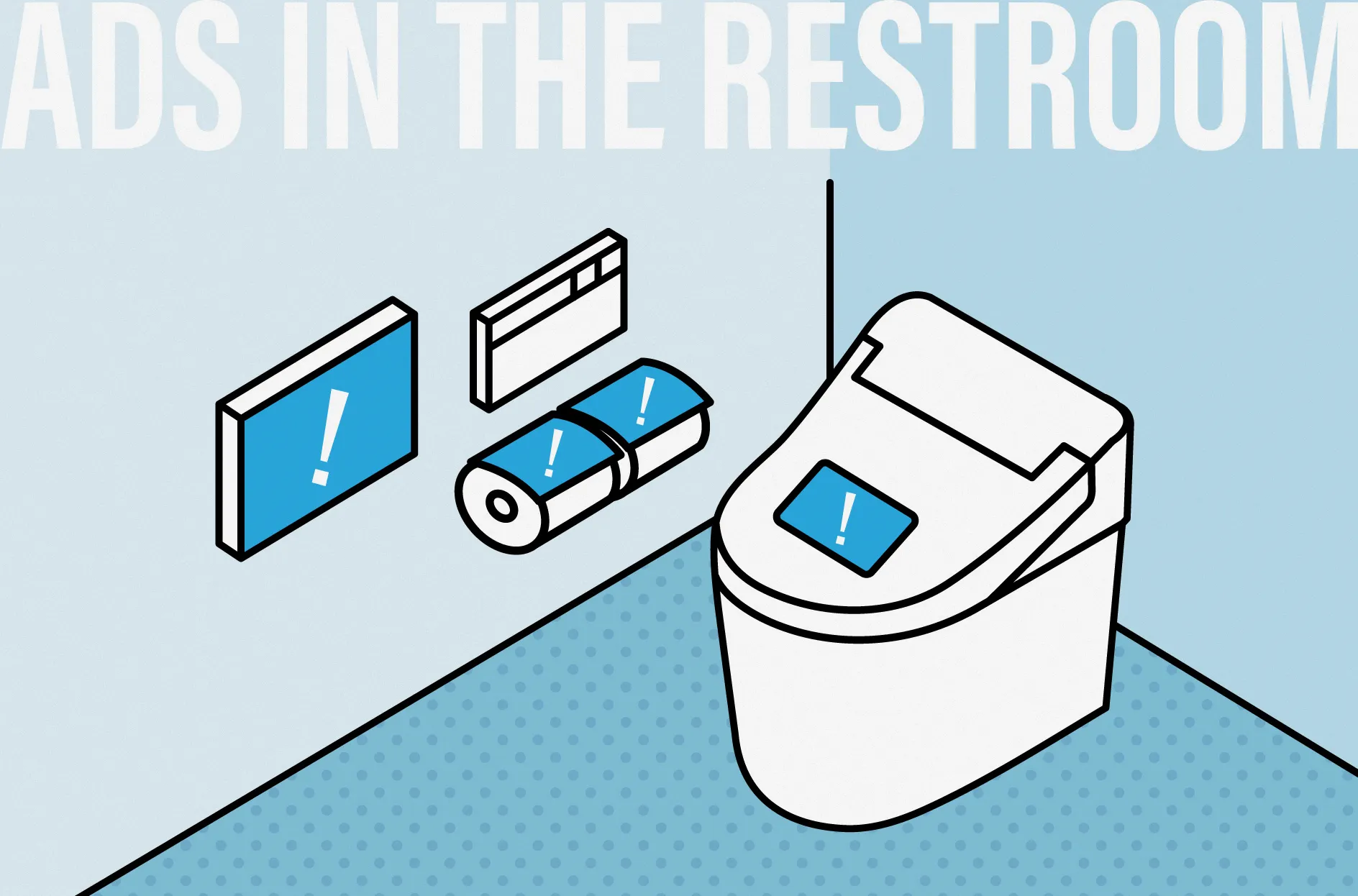マーケティング戦略
のぼりとは?旗との違いや意味・効果・活用法を知って集客に役立てよう!

街中や店頭に並ぶ「のぼり」は、目立つ配色やデザインで顧客の関心を引く販促資材です。店舗に限らず、神社仏閣やスポーツ施設でも使用されています。たとえば大相撲の開催場所で、力士名の入ったのぼりが並ぶのを目にした方は多いでしょう。
当記事では、さまざまな場面で活用されるのぼりの意味や「旗」との違い、種類と使い分け、効果などを解説します。自店舗の集客に悩んでいる方や外観を工夫したい方は、最後まで読んでください。
- のぼりとは?意味・旗との違いも解説
- のぼりの効果とは?
- のぼりの種類と使い分け
- のぼりの活用シーン
- のぼりについてよくある質問
- のぼりは「低コスト×高視認性」の万能ツール

タレント×マーケティングで
成果を最大化
のぼりとは?意味・旗との違いも解説

「のぼり」は、縦に長い布の上辺と長辺の片側をポールまたは竿で固定したもので、「のぼり旗」とも呼ばれます。
のぼりを作成する際は、左車線を通行する車両の視認性を考慮して、生地の左側をポールに固定することが多いようです。
のぼりの歴史的背景
のぼりのルーツは、平安時代の「流れ旗」だといわれています。流れ旗は上辺に竿や木を通した長い布を棒の上に吊したタイプの旗で、敵軍と区別し、自軍を誇示するために使われていたそうです。戦国時代には敵と味方を判別できるように、家紋や文字を入れた旗が普及しました。
同じ家紋の判別が厳しくなったことから、現代ののぼりに近い旗が使われるようになったといいますが、正確な時期ははっきりしていません。室町時代に現代のスタイルが確立したという説、江戸時代以降とする説があります。
現代では、のぼりの使用目的は変わったものの、視認性を高めてアピールする点は受け継いでいます。
参照:ホームメイト「合戦旗指物・幟写真」
現代の用途
のぼりには豊富な種類があり、現代では主に次の場所で活用されています。
- 店舗周辺(飲食店、理容院、小売店など)
- イベント会場(音楽イベント、地域イベントなど)
- 避難所
- スポーツ(大相撲、マラソン大会など)
- 神社(奉納のぼり、祈願のぼりなど)
そのほか、不定期に行われる催事の告知や、交通安全運動の呼びかけなどにも使用されます。
「のぼり」と「旗」の違い
のぼりと旗には大きな違いがあります。下の表にまとめました。
形状 | サイズ | 使用目的 | |
|---|---|---|---|
のぼり |
| 600×1800mmが一般的だが、用途に合わせてさまざまなサイズ展開をしている |
|
旗 |
| 応援団旗や手旗などがあり、サイズは特に決まっていない |
|
ほかに、のぼりには薄手で風になびきやすい生地、旗には厚手で丈夫な素材が使われることが多いという違いもあります。
のぼりの効果とは?

ここではまず、のぼりによって得られる効果を解説します。
大きなのぼりは視認性が高く、施された大胆なデザインは遠くからでも目立つため、通行人の足を止め、店舗へ立ち寄るきっかけを与える効果があります。デザインばかりでなく、のぼりが風になびく動きも人の目を引くでしょう。
設置したのぼりは「非接触型の営業ツール」として機能するため、スタッフの少ない店舗は顧客の呼び込みなどに人員を割く必要がなく、感染症対策にも有効です。
次に、チラシやWeb広告などでは得られない、のぼりならではのメリットを挙げます。
- 一度作成すると長期的に使用できる
- 店頭に配置することで、自店舗が扱っている商品を近隣住民に印象づけられる
→「新鮮な野菜ならこの店にあるな」などと、想起してもらいやすい
- インターネットをあまり使用しない層にも訴求できる
のぼりの種類と使い分け

のぼりは縦長が一般的ですが、近年はバラエティに富んだ形状やさまざまなサイズのものが存在します。どのようなものがあるか、タイプ別・素材別に解説します。
タイプ別のぼり紹介
タイプごとの概要を下表にまとめました。のぼりを選ぶコツは、どういう目的で使用するか、誰をターゲットにするか、どこに設置するかを明確にすることです。自店舗の環境に合うのぼりを選びましょう。
特徴 | サイズ展開 | 適した設置場所 | |
|---|---|---|---|
レギュラー | 上辺と長辺の片側を固定した縦長の長方形タイプ | 通常:600×1800mm | 屋内・屋外問わず、さまざまな場所で活用できる |
棒袋縫い | ポールの部分を包むように縫う分、広範囲にデザインできる | 通常:600×1800mm | 風の強い屋外でも使用しやすい |
大型のぼり | 印字部分はレギュラータイプの2倍以上ある | 900×2700mm | 野外のほか、店内装飾として活用できる |
神社のぼり・奉納のぼり | 神社のぼり:レギュラータイプより縦長 奉納のぼり:レギュラータイプと同じ | 神社のぼり(小): 神社のぼり(中): | 神社のぼり:入口の鳥居付近 奉納のぼり:参道など |
両面プリント | レギュラータイプと同じ形状で、両面にプリントできる | 通常:600×1800mm | 飲食店・小売店など |
ミニのぼり | 通常タイプのミニチュア版。クリップや吸盤スタンドで固定できる | 小:70×210mm | 小売店の商品棚や説明会場など、屋内で活用できる |
スウィングバナー(セイルのぼり) | 上部を湾曲させた、棒袋縫いタイプののぼり | 最小:390×1440mm | バイク・車販売店、カフェなど |
パピヨンバナー(フライングバナー) | スウィングバナーより上部がしなっていて、下辺はない。この形状から「Pバナー(Fバナー)」と呼ばれる | 小:670×1650mm | 街中で使われることが多い |
Rのぼり | 上辺はあるが、下辺をカーブさせたタイプののぼり | 通常:600×1800mm | 洋食店・カフェなど |
ストリームフラッグ(ベーシック型) | 上部が半円形で、下部は二等辺三角形を合わせたような形状 | 通常:970×2000mm | 風に強く、幅広い場所や用途に活用できる |
ストリームフラッグには、ベーシック型のほかにも、下部に段のついた「ギザギザ型」や、下の方まで幅広くデザインできる「ブレード型」、丸みを帯びた段がついた「バタフライ型」があります。
のぼりは、布の横と上についた輪(チチ)をポールに通し、任意の位置に置いた注水台に差し込んで設置します。通行を妨げずに内容を認識してもらうには、1.8m間隔で配置すると良いといわれています。
のぼりの素材について
次は、のぼりに使われている素材を解説します。
1:金巾(かなきん)
金巾は細めの糸を平織りした薄手の生地で、綿100%が一般的ですが、ポリエステル混紡の場合もあります。高級感のあるのぼりを作りたいときに使われることが多いようです。
【メリット】
- 手触りが良く、耐久性がある
- 使用環境によって異なるものの、約1年の長期使用が可能
- 手拭いにも使われる素材なので、渋い風合いがある
和食料理店や和菓子店、神社・祭りといった日本の伝統あるイメージを表現したい場面などに適しています。
2:テトロンポンジ
テトロンポンジはポリエステル100%の平織り生地で、「ポンジ」とも呼ばれる、のぼりの定番素材です。
【メリット】
- 糸が細いためインクが浸透しやすく、発色も良い
- 生地が薄いため、雨などに濡れても乾きやすい
- 加工が簡単にできる
- 安価
3:テトロントロピカル
テトロントロピカル(トロピカル)もポリエステル100%の糸を平織りした生地ですが、ポンジよりも若干厚く、長期使用に適しています。
【メリット】
- 文字や画像を綺麗にプリントできる
- 糸の太さがテトロンポンジの約2倍で耐久性が高い
4:トロマット
トロマットはポリエステル100%の平織り生地で、ポンジやトロピカルと比べて厚みと重みがあります。光沢のない、マットな質感が特徴です。
【メリット】
- 発色が良いため、繊細な表現が可能
- 背景の色が透けにくい
- テトロンポンジより厚く、しわがつきにくい
- ターポリンより軽量
- 乾きやすく摩擦に強い
5:ターポリン
ターポリンは、ポリエステル繊維の布を2枚の合成樹脂で挟み込んだビニール素材の生地です。
【メリット】
- 防水性に優れている
- 耐久性があり、色あせしにくい
ターポリンは他の生地より重めですが、メッシュ加工を施して軽量化した「メッシュターポリン」もあります。
6:遮光スエード
遮光スエードは、一般的に天然のスエードではなく、ポリエステル製のスエード生地を2枚重ねたものを指します。両面印刷が可能なことが特徴です。
【メリット】
- 遮光素材で反対面が透けず、表裏どちらでも視認できる
- 高級感のある素材で、多様なデザインに対応できる
のぼりの活用シーン

のぼりは店舗にかかわらず、イベントや説明会などにも効果を発揮します。のぼりの活用シーンを挙げたので、参考にしてください。
- 飲食店:テイクアウトや期間限定コラボメニューなどの訴求
- 小売店:セールや新商品、イベントの告知など
- 展示会や説明会、地域イベントの会場の目印
- スポーツや選挙活動などの応援グッズとして
企業や商品のイメージを反映して作成したのぼりは、ブランディングにも役立つでしょう。
なお、こういった屋外広告のことをまとめてOOHとも呼びます。くわしくは以下の記事をご参照ください。
のぼりについてよくある質問

ここでは、のぼりの制作でよくある疑問に回答します。
Q. のぼりの適切なサイズはどれぐらい?
店舗のイメージや設置場所の環境によって使用できるサイズは異なるため、近隣住民の通行状況などに配慮しつつ、目立つサイズののぼりを選ぶとよいでしょう。
小売店や飲食店でおすすめ商品などを紹介したい場合は、ミニのぼりを活用するのもおすすめです。
Q. 耐久期間はどのぐらい?野外使用はできる?
素材によって、のぼりの耐久期間は変動します。短ければ約3ヶ月、長いものは3年ぐらい使用可能です。野外、雨天時に使用できる素材もあります。
Q. のぼりは自分でデザインできる?業者に頼むべき?
デザインツールによるデザイン作成は可能ですが、のぼりの制作会社に依頼すれば、デザインから印刷、加工まで一貫して任せられるのでおすすめです。
Q. 価格の相場は?
枚数や印刷方法、制作会社によりますが、通常サイズ(600×1,800mm)1枚あたりの平均価格は以下のとおりです。
- 既製デザインの場合:970円
- オリジナルデザインの場合:1,296円
- デザインのデータ制作から依頼する場合:3,000円
加工ごとの平均価格は、1枚につき次のとおりです。
- 棒袋縫い:333円
- ほつれ防止加工:80~130円
- 防炎加工:443円
設置台やポールの価格、送料などを含めると、のぼり1本あたり3,300~4,000円で予算を組むとよいでしょう。なお、まとめて発注することで単価が安くなることもあります。
参照:のぼり製作所「のぼりの平均価格とは?」
Q. 複数使うと効果は上がる?
1本のみを使うより、店舗周辺に複数設置するほうが視認性は上がります。1.8m間隔で立てると圧迫感を与えず、通行人・ドライバーのどちらも認識しやすいといわれます。
のぼりは「低コスト×高視認性」の万能ツール

のぼりは導入しやすく、作成後すぐに使用できる集客アイテムです。形状やデザインの工夫次第でブランドイメージの向上にも活用できます。
おしゃれなデザインでブランディングを図りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。
店舗以外にもイベントや地域活動など、その活用シーンは無限大です。低コストで視認性の高いのぼりを、ぜひ取り入れてみましょう。
のぼりなどの販促アイテムを作るにあたって、自社・自店のアンバサダーやイメージキャラクターを起用したいとお考えの場合は、ぜひサブスク型オンラインキャスティングサービス「Skettt(スケット)」のご利用もご検討ください。
Sketttは最短契約期間1か月〜5,000名以上の著名人を自社プロモーションに活用することができます。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
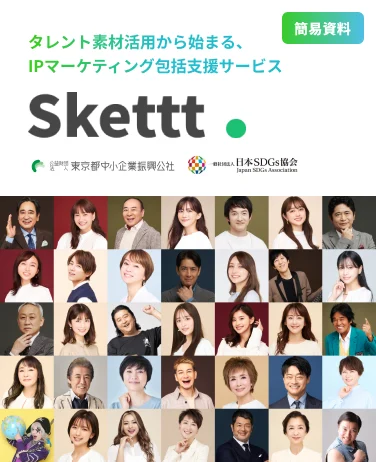
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag