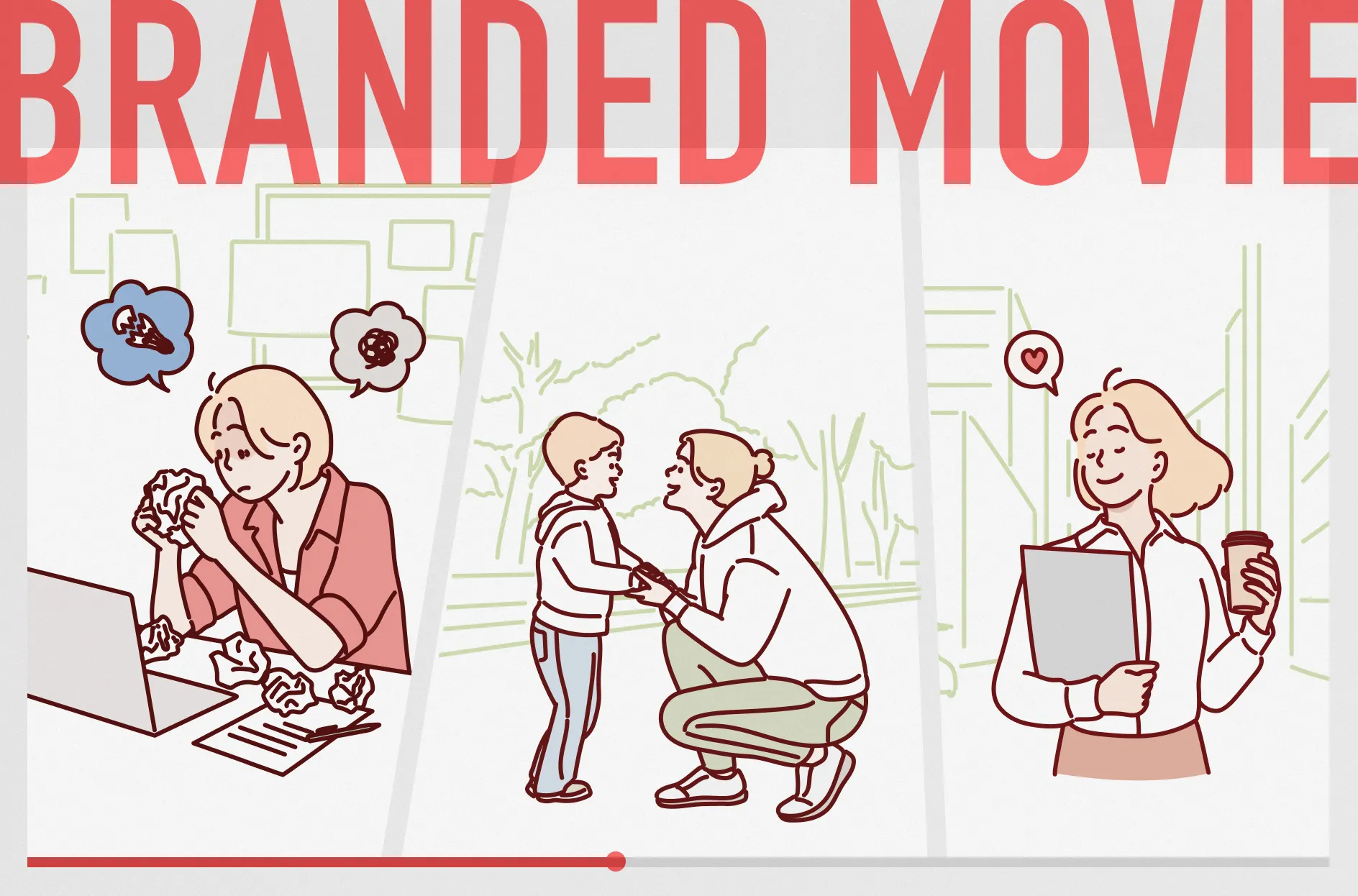IP活用
コダックアパレル・CHARMERA…“Kodak現象”はなぜ起きた?無形のIPによるブランドの再定義

「Kodak Apparel(コダックアパレル)」という名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「コダック」といえば、いわずと知れた米老舗カメラブランド。140年近い歴史を持つものの、デジタル化の波に乗りきれず、残念ながらすでに経営は破綻しています。
しかし2020年にその名を冠したアパレルラインが韓国より誕生し、今爆発的なブームを起こしているのです。
これは、コダックのロゴやブランドカラーが大きな認知と人気を獲得しているからこそ起こりえた事象。今回は、そんな“コダック現象”を紐解きながら、形を持たずとも、なお強く人々の記憶に残り続ける「IP」の力について考えていきましょう。
- コダックという伝説:ブランドの歴史と衰退
- Kodak Apparel:韓国発の再ブランディングにより、ロゴが動き出す
- 「無形のIP」という新しい価値:ブランドはプロダクトを超える
- “Kodak現象”が示すIPの未来

タレント×マーケティングで
成果を最大化
コダックという伝説:ブランドの歴史と衰退

コダック(イーストマン・コダック)が誕生したのは1888年のこと。ニューヨークにおいてジョージ・イーストマン氏が「You press the button, we do the rest. (あなたはシャッターを押すだけ、あとはわれわれにお任せください)」というスローガンのもと、シンプルなカメラを発売したのがはじまりでした。
世界で初めてロールフィルム、カラーフィルム、そしてデジタルカメラを開発したとあれば、写真業界、ひいては人々の日常生活に大きな革命をもたらしたことが伝わるのではないでしょうか。
1889年には商業用透明ロールフィルムを発表し、それを受けてトーマス・エジソン氏が世界初となる映画撮影用カメラを開発。コダックは映画産業への貢献が評価され、スタジオを除くと最も多い9体のオスカー像が贈られます。
また、1912年には印刷業界用のプロダクトを販売し、1950年代から60年代にかけて雑誌などの書籍におけるカラー化の波を加速化。
さらにはウィルヘルム・レントゲン氏がX線を発見して1年未満に、ヘルスイメージングにおけるビジネスをスタートさせ、医療業界においても多大な功績を残しました。
多方面に大きな影響をもたらしたコダックはしかし、自社こそが最初に発表したデジタルカメラの台頭とともに存在感を霞ませるようになり、2012年には米連邦破産法11条の適用を申請し、経営も破綻。
それでも長きにわたって時代を築いてきたブランド力は認知度も人気も衰えることなく、時を超えて2020年に韓国のHilight Brands(ハイライト ブランズ)がその偉大なネームを復活させます。
Hilight Brandsは、さくらんぼがモチーフの「KIRSH(キルシー)」や「FRUIT OF THE LOOM(フルーツ オブ ザ ルーム)」など人気ブランドを多数手がけるグローバルライフスタイルカンパニー。
日本をふくめアジア圏では現在、空前のレトロブームが続いています。ロゴやイエロー×レッド配色を見れば、多くの方がコダックだと認識できる歴史的なブランドは90年代以前の象徴であり、まさしく今のムードに合った魅力を備えているといえ、必然的に独り歩きを始めたのでした。
Kodak Apparel:韓国発の再ブランディングにより、ロゴが動き出す

コダックがいくら過去に大きな功績を残し、だれもが知る偉大なブランドとして依然存在感を放っていたとしても、かつての写真業界の巨人が凋落してしまったことは事実。全盛期後は徐々に「時代遅れ」の印象を持たれていた可能性も否定はできません。
このたびのような再ブームを築くには、プロダクトのデザインや素材といった仕上がりだけでなく、タイミングや打ち出し方といった戦略も重要だったことでしょう。
“カメラのコダック”から独立したアジア発の世界観

Kodak Apparelはもちろん、「コダック」というネームを活用したアパレルブランドであり、後述しますがKODAK CHARMERAなどに見られるように、そのフィルムカルチャーを創りあげた雄としての尊厳も継承してはいますが、地続きで同じファンが再注目しているわけではないでしょう。
Hilight Brandsがコダックとライセンス契約を結び、Kodak Apparelを立ち上げたのは2020年。ちょうど韓国をふくむアジア圏ではレトロブームが巻き起こりはじめたころでした。
(2000年ごろから昭和30〜40年代ごろのカルチャーが流行しており、それをレトロブームと指すこともありますが、当記事では2020年前後以降の、日本でいうところの「平成レトロブーム」を指します)
日本でもZ世代やミレニアルズを中心に、Y2K(2000年代を指す語。「Year 2000」の略)ファッションや90〜00年代の象徴ともいえるプリクラ、「写ルンです」を筆頭とした使い捨てカメラ、カセットテープといったアイテムが「エモい」(エモーショナル)という文脈で流行し、2025年もそのムードは引き継がれています。
コダックのロゴやイエロー×レッドの配色は今なおIP(知的財産)として生き続けており、それを再構築した現代的なストリートファッションは、若年層の目には新鮮に映り、「古くて時代遅れ」なのではなく、「ノスタルジック」なイメージにアップデートされたのです。
結果、明洞(ミョンドン)や聖水(ソンス)に旗艦店を構えるほか、話題のプロダクトを数多く取り扱うTHE HYUNDAIといったデパートを中心に韓国の主要都市を網羅。さらに上海・台湾・マカオなど海外にも進出し、その勢いはとどまりません。
2025年5月には原宿にも常設店を出店し、現在、韓国国内外で100店舗ほどを展開しています。同年11月には渋谷パルコにオープンしたポップアップストアも話題になり、連日行列ができていました。
市場全体が低迷して久しいアパレル業界において、ローンチして間もないブランドがこれほどまでの人気を得ることができたのは、ひとえに「コダック」という、すでに多くのユーザーと信頼関係に結ばれたIPのパワーによるところが大きいでしょう。
ただ、一言付け加えておきたいのは、Kodak Apparelにはコダックの表層的な部分だけでなく、アイデンティティも宿っているということ。
コダックといえば、前述のとおり、140年近くも昔に世の中に写真文化をもたらしたブランドです。くわえて、映画や印刷業界、さらには医療業界にまで及んで人々の暮らしを新時代に引き上げてきました。
そのチャレンジングなスピリットとクリエイティブマインドを継承して立ち上がったからこそ、これだけ多くの方に支持されているのです。若者だけでなく、かつてのコダックファンたちも懐かしさを覚えているのではないでしょうか。
カメラブランドとしての尊厳が蘇るKODAK CHARMERA

Kodak Apparelのどういった部分に、かつてのコダックと通ずるクリエイティブマインドが感じられるかというと、アパレルアイテムに全振りしているわけではなく、ファッションという新たな文脈を与えられたカメラも存在している点にあります。
その名も「KODAK CHARMERA(コダックチャーメラ)」。「小さな飾り」を意味する「CHARM」に「CAMERA」を組み合わせて名づけられました。
名前が示すとおり、その大きさは手のひらにおさまるほどで、付属のキーチェーンによってバッグやジーンズのベルトループなど好きなところに取り付けて、どこにでも気軽に持ち運べます。
ラブブに代表されるPOP MARTのマーケティング術についての記事でも触れましたが、90〜00年代の平成期において、キーホルダーの“じゃら付け”はアイコニックなトレンドのひとつであり、現在はレトロブームによってリバイバルされているため、時代にマッチしたアイテムといえるでしょう。
また、ラブブをふくむPOP MARTのほとんどのフィギュアは「ブラインドボックス」と呼ばれる、開封するまで中身の見えない箱に入っており、それがまたコレクション欲を刺激するのですが、CHARMERAも同様に7種のデザインのうち、どれが当たるかわかりません。

ブラインドボックスが持つ「ガチャ」的魅力については、こちらのPOP MARTのマーケティング戦略についての記事で解説したので当記事では割愛しますが、ユーザーに「買うか買わないか」ではなく、欲しいデザインの当選率を上げる目的で「1つ買うか2つ買うか」と自然に考えさせてしまう効果は、売り上げ貢献だけにとどまらないでしょう。
事実、CHARMERAは現在プレミア化するほどの人気を博し、取扱店では毎回発売と同時に即完売という状況が続いています。
先に挙げた渋谷パルコ内のポップアップストアでは、期間中毎日先着10名の方が購入できたのですが、連日開店前に上限人数をオーバーし、締め切られていたようです。
プロダクトとしての魅力は、デジタルカメラでありながらフィルムの雰囲気を感じさせる写真が撮れること。
スマホでも高画質の写真が撮影できる時代において、あえて抜け感を演出できるトイカメラや使い捨てカメラを選ぶ若者も増えていますが、CHARMERAは本格カメラブランドの名前を冠しながら、その脈絡もふまえているところが人気の秘訣でしょう。
Kodak Apparelはロゴの人気だけに頼らず、老舗カメラブランドとしての世界観を現代のニーズにマッチさせているからこそ、再評価されているわけです。それはKodak Apparelの母体でもあるコダックの根源的価値を復権させているといえるのではないでしょうか。
「無形のIP」という新しい価値:ブランドはプロダクトを超える

かつて一世を風靡し、衰退し、そして再び盛り返した“コダック現象”は、弱体化してしまっていたプロダクト以上に、ロゴやカラーリングというブランドの記号が価値を持っていたために起こりました。
その無形のIPがレトロブームと組み合わさり、さらにはカメラテックやユースカルチャーと絡み合ったことで、かつてのブランドの姿を取り戻すわけではなく、新たに別のブランドとしての道を切り拓くわけでもなく、もともとの魅力を再認識させながら新たなファンを取り込むことを成功させたのです。
ここまでの回復はなかなか見られないケースですが、形を持たないIPの成功例というのは、ほかにも存在します。
【ロゴが文化的記号として機能するケース】
- Nike(スウッシュ)
どんなプロダクトであっても、スポーツの文脈で成立する典型的無形IPの成功例 - adidas(パフォーマンスロゴ/トレフォイル)
パフォーマンスロゴは、アスリートのパフォーマンスを最高に引き出すことをコンセプトにしたEquipmentコレクションのロゴとして登場したこともあり、“adidasのスポーツライン”、一方のadidas originalsコレクションで使用される三つ葉のトレフォイルロゴは“adidasのカジュアルライン”と認識が棲み分けされている - PLAYBOY(ラビットヘッド)
成人向けの米娯楽雑誌名だが、ロゴ単体でファッション文脈において独り歩き。雑誌を読んだことのない人も着用している - THRASHER
スケーターに向けた米雑誌名だが、ロゴ単体でファッション文脈において独り歩き。スケーターではない人も着用する - Harley-Davidson
米発大型オートバイブランド名だが、ロゴだけが独り歩きしアパレルや雑貨なども展開。バイカーではない人も着用する、アメリカンカルチャーの表象 - Polaroid
米発インスタントカメラブランド、およびそのプロダクトの名称だが、ロゴだけが独り歩きし、コダック同様レトロブームにおける再解釈が進む - NASA
ロゴだけでなく、アメリカ航空宇宙局だからこそ持つ、宇宙服に使われる技術力を活用した機能性ウェアを展開。ファッションブランドとのコラボも盛ん
【概念がIPの記憶を持つケース】
- ミッキーマウスのシルエット
3つの円を用いて表したミッキーフェイスのシルエットだけでそれと認識できる - Roland:TR-808サウンド
1980〜1983年にかけて製造されたドラムマシン「TR-808」は特異なサウンドで主にアンダーグラウンドのミュージシャン間で爆発的な人気を博し、特に当時発展途上だったHIP-HOPの土台を築いたといわれる - スーパーマリオシリーズ:ジャンプ音など
1985年以降、愛されつづけるゲーム界の王者的存在「スーパーマリオ」シリーズにおける効果音は、それだけを聞いても認識できるほどの認知度を誇る
情報が飽和する現代において、新しくブランドを立ち上げ、それを成功させることは、どの領域においても非常に難しいといえます。
その点、すでに高い認知度と一定数のファンを擁するブランドは、もし現在低迷していたとしても、市場において集客面で一歩リードしているといえるでしょう。
特にそのブランドが、ロゴやカラー、サウンドからアイデンティティやストーリーまで想起させられるほどの強力なIPを保有していればなおさら。
多方面においてカテゴリーの垣根を超えたコラボが活発に行われる現代、IPは有形・無形どちらも数多く存在しており、特にあらゆるモノに柔軟に展開でき、新たな局面を迎えられる可能性を秘めているという点で、形を持たないIPの重要性が増していると捉えることもできます。
“Kodak現象”が示すIPの未来

コダック現象は、ロゴというIPの独り歩き、そしてアジア圏で巻き起こる空前のレトロブームのなかでのブランドの再解釈、そして「カメラ」というブランドの原点へのリスペクトが組み合わさって作用しました。
すべてのブランドの生存戦略に応用できるとはいえませんが、形を持たないIPがいかに大事であるかを指し示す、ひとつの大きな事例になったのではないでしょうか。
あえてブランディングとしてロゴやブランドカラーを持たない企業もあるかもしれませんが、今後のさらなる発展を見据えるのであれば、新たに創作してみてもよいのかもしれません。
また、コダックの場合は老舗ブランドとして歴史と多くの功績を持っているという点も、成功に導いたポイントといえるでしょう。多くの方に認知されているストーリーがあれば、過去の栄光も“遺産”ではなく“資産”になります。
それは、市場を変えても本質を損なわず、ブランドの軸となるプロダクトを新たな付加価値とともに蘇らせる余地があることを示唆しています。そして再生が叶えば、ブランドとしての奥行きが増し、なおさらその存在感を強めることができるのではないでしょうか。
タレントサブスク
サービス資料
ダウンロード
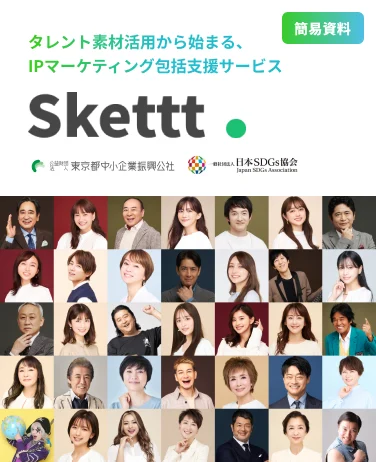
宣伝素材を事業成長の起爆剤に。
- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説
- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み
- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介
事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1
この記事の関連タグ
Related Article
関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!
Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.
IP mag